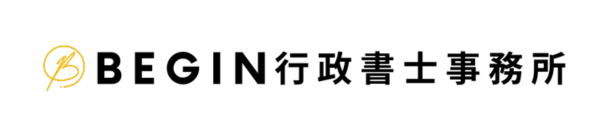改正の概要(令和7年10月16日施行)
🏛出入国在留管理庁は、「経営・管理」在留資格の上陸許可基準の改正を正式に公示し、令和7年(2025年)10月16日から施行されました。
出入国在留管理庁│在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
今回の見直しは、形式的な会社設立による在留資格の不正取得を防止し、日本で実質的に事業を行う外国人経営者のみを対象とすることを目的としています。
改正では、出資要件・雇用要件は、これまでの「どちらかを満たせばよい」という条件から、「両方を満たすこと」が必須要件になります。
📊 経営・管理ビザの新旧比較表
| 項目 | 従来の要件(~令和7年10月15日まで) | 改正後の要件(令和7年10月16日施行) | 主な変更点 |
|---|---|---|---|
| 出資・雇用要件 | 次のいずれかを満たすこと ① 事業規模が資本金500万円以上 ② 常勤職員2名以上を雇用 | 資本金3,000万円以上かつ常勤職員1名以上を雇用 | 「いずれか」から「両方」に変更。資本金要件は6倍に引き上げ。 |
| 経営者の適格性(新設) | 特段の学歴・職歴要件なし | 経営・管理に関する学歴または 実務経験が必要 ① 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること または ②経営・管理業務に関する3年以上の実務経験 | 新要件。経営の知識または実務経験が求められる。 |
| 日本語能力 | なし | 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有すること | 新要件。日本語能力が必須化。 |
| 事業計画書の取り扱い | 提出義務あり | 新規事業計画について経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付ける(上場企業相当規模の場合等を除く。) | 形式審査から実質審査へ。赤字想定・資金不明瞭は不許可リスク。 |
改正の目的と背景
出入国在留管理庁の公式説明によると、今回の改正の背景には、「経営・管理」の在留資格を利用した不正なビザ取得・実体のない事業設立の増加があります。
形式的に500万円の資本金を入金して会社登記だけを行い、実際には営業活動を行わない「ペーパーカンパニー型」の申請が相次いだため、次のような方針を示しています。
✅ 日本国内で実質的に経営・管理活動を行う者に限定する。
✅ 経営能力・資金力・雇用責任を明確に立証できる体制を整えた上での申請を求める。
これにより、経営実績・経営能力・事業継続性の立証が重視される制度へと変わります。
🧩 改正による主なポイント解説
① 出資要件の引き上げ(500万円 → 3,000万円)
改正後は、資本金3,000万円以上が必須です。
これは事業の初期運転資金・雇用維持費・賃料などをまかなうための現実的な基準として設定されています。
500万円基準のもとでは、設立直後に資金が枯渇するケースが多く、実際には経営実態を維持できない事例が相次いでいました。
② 雇用要件の変更(常勤職員1名以上の雇用)
従来は常勤2名または500万円資本金のどちらかでよかったのに対し、改正後は「資本金3,000万円+常勤職員1名以上の雇用」の両方が必要です。
「常勤職員」の対象
「常勤職員」の対象となるのは、日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限ります。技人国や技能ビザなど就労系ビザをもって在留する外国人はこの常勤職員の雇用要件の対象となりません。
③ 経営者の適格性要件の新設(学歴・職歴)
これまで要件がなかった「経営者本人の能力」について、令和7年改正で明文化されました。
次のいずれかを満たす必要があります。
- 経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること
- 事業の経営又は管理について3年以上の職歴を有すること(在留資格「特定活動」に基づく、貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所の確保その他の準備行為を行う活動(起業準備活動)の期間を含む)
この改正により、「経営経験のない方による形式的起業」は制限されます。
④ 日本語能力について
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
相当程度の日本語能力とは、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当すること。
- 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
- 中⾧期在留者として20年以上我が国に在留していること
- 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
⑤ 事業計画書の取扱い
事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認が義務付けられました。
📅 申請に関する取扱い
今回の改正では申請に関する取扱いについて、下記が示されています。
事業内容について
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。
事業所について
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
永住許可申請等について
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。
在留中の出国について
在留期間中、正当な理由なく⾧期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。
つまり、経営管理ビザを取得したとしても、実態として日本を拠点として経営活動を行わずに本国に戻るなどのケースでは在留期間更新申請で不許可になるリスクが高いということになります。
公租公課の履行について
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します。
① 労働保険の適用状況
・ 雇用保険の被保険者資格取得の履行
・ 雇用保険の保険料納付の履行
・ 労災保険の適用手続等の状況
② 社会保険適用状況
・ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
・ 上記社会保険料納付の履行
③ 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
・ 法人の場合
国 税:源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税:法人住民税、法人事業税
・ 個人事業主の場合
国 税:源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税:個人住民税、個人事業税
事業を営むために必要な許認可の取得について
申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。
在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新許可申請時に提出を求めます。
経営管理ビザの在留期間更新許可申請について
在留期間更新については、3年間の経過処置が行われます。
〇 既に「経営・管理」で在留中の方が施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断が行われます。なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出が必要になる場合があります。
〇 施行日から3年を経過した後になされた在留期間更新許可申請については、改正後の許可基準に適合する必要があります。改正後の許可基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好であり、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに改正後の許可基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断が行われます。
〇 「高度専門職1号ハ」(「経営・管理」活動を前提とするもの)についても、「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提となることから、上記と同様に取り扱われます。
🧾 経営管理ビザ申請の今後の準備について
今回の改正により、「経営・管理ビザ」は形式的な会社設立ではなく、実質的に経営を行う外国人経営者を対象とした在留資格へと明確に性格づけられました。
これまで「資本金500万円を用意し、ペーパーカンパニーを登記すれば通る」という水準ではなくなり、資金力・経営力・事業継続性を総合的に評価される制度へと進化した点が最大の変化です。
実務の現場では、特に以下の準備が不可欠になります。
① 経営経験・学歴の立証資料を丁寧に準備する
経営・管理ビザ改正後は、申請人本人に「経営・管理に関する学歴または3年以上の実務経験」が求められます。
この要件は形式的な履歴書だけでは不十分であり、具体的な裏付け資料を添付することが必要です。
【立証に有効な資料例】
- 経営学・国際ビジネス・会計等の学位証明書(学士・修士・博士)
- 前職での役職証明書、職務内容証明書(社長・取締役・部長など)
- 海外企業での経営参加を示す登記事項証明書、契約書
- 経営関連のセミナー受講証明、資格証(MBA、経営士、会計士など)
これらの資料は、日本語または英語翻訳付きで提出することが求められ、経営能力の「客観的証明」として非常に重要視されます。
② 事業計画書は「収益構造」と「雇用計画」の整合性を示すこと
改正後の審査では、「事業計画書」がこれまで以上に重視されます。
入管は、事業が実際に収益を生み出し、継続して雇用を維持できるかを定量的に判断します。
【重視される評価ポイント】
- 売上根拠の合理性(市場分析・販売チャネル・競合比較)
- 経費・人件費の妥当性(資本金3,000万円で維持できる運営か)
- 雇用計画の実現性(常勤職員1名の採用計画、給与設定の適正さ)
- 資金繰りの継続性(資金調達ルート・キャッシュフロー)
さらに、事業計画書には第三者専門家(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の確認書が必須となります。
③ 雇用・人事体制の実態証明を整える
新制度では「常勤職員1名以上」の雇用が必須となりますが、入管は単に雇用契約書があるだけでなく、実際に雇用が履行されているか(社会保険・給与支給・勤怠管理など)を確認します。
そのため、以下の書類を準備することが望ましいです。
- 社会保険加入証明書(健康保険・厚生年金)
- 給与支払い明細・雇用契約書
- 従業員の在籍証明・勤務スケジュール
- 労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所番号
これらの実態資料は、申請時だけでなく更新時の経営継続確認にも利用されます。
④ 「資本金3,000万円」の出所・維持を明確に示す
改正後の3,000万円資本金要件は、単なる一時的な入金では認められません。
資金がどのように調達され、どのように使用されるのかを具体的に説明する必要があります。
【提出が求められる可能性のある資料】
- 海外送金記録・残高証明書
- 投資契約書・出資同意書
- 会社設立時の資本金入金明細(銀行通帳コピー)
- 資金使用計画(設備投資・人件費・広告費等)
入管は「経営者本人が実際に事業リスクを負っているか」を見ています。他人資金・借入金を資本金に充てる場合は、その返済負担も説明が必要です。
⑤ 更新審査を見据えた「経営記録管理」が重要
改正施行後は、更新時にも「新基準に基づく確認」が予定されています。
許可取得後も、次の資料を定期的に整備しておくことで、更新リスクを大幅に軽減できます。
- 決算書・貸借対照表・損益計算書(税理士の署名入り)
- 社会保険・雇用保険納付書類
- 就労証明書・給与支払報告書
- 事業の契約書・請求書・取引記録
これらを整えておくことで、「事業が継続している=在留の正当性がある」という信頼を維持できます。
💬 申請取次行政書士からのアドバイス
令和7年改正により、経営・管理ビザは「誰でも取得できる」在留資格から「本格的な事業者のための制度」へと格上げされました。
裏を返せば、しっかり準備すれば、安定した許可・更新が可能な制度でもあります。
特にこれから申請する方には、
- 経営計画の実現性を専門家に確認してもらう
- 書類間の整合性(事業計画・契約書・資金証明)を徹底する
- 更新を見据えた「会計・雇用の証拠管理」を最初から始める
という3点が最も重要です。
行政書士が入ることで、「不許可リスクを事前に排除し、書類の信頼性を高める」ことができます。
改正後の審査は厳格になりますが、きちんと準備した事業者にとってはむしろ透明で公平な制度といえるでしょう。
当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。
👉経営管理ビザでお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。