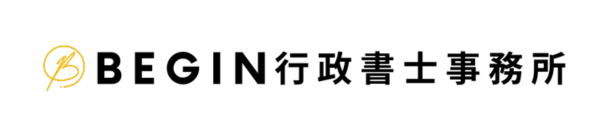在留資格一覧
29種類の在留資格
在留資格とは?
在留資格(Status of Residence)とは、入管法(出入国管理及び難民認定法)の別表第一・別表第二に基づき、外国人の方が日本で行える活動内容と在留期間を定める在留中の地位です。まず在留資格は29類型に整理されます。適切な在留資格を選定することで日本での就労・就学・生活を適法に行うことができます。
在留資格は、活動資格(教授・技術・人文知識・国際業務・特定技能 など)と、身分・地位に基づく居住資格(永住者・日本人の配偶者等・定住者 など)に大別されます。資格ごとに就労可否/活動範囲/在留期間が異なるため、不一致は不許可や不法就労助長につながります。雇用企業は在留カードの在留期限・就労制限の有無・資格外活動許可を確認・保管し、社内のコンプライアンスに反映させることが大切です。
在留資格とビザの意味
一般的にビザという言葉を使う場合、「在留資格」と「査証」の両方の意味で使われていますが、法的には別制度です。在留資格(Status of Residence)は在留中の地位であり、査証(Visa)は在外公館が発給する上陸審査のための推薦状です。なお、海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)を取得してから査証(Visa)申請を行うのが一般的です(有効期間は原則3か月、電子交付に対応しています)。
在留資格申請の基本(COE/変更/更新/オンライン申請)
海外から招聘する場合は在留資格認定証明書交付申請を行い在留資格認定証明書(COE)を取得し、在外公館で査証申請→上陸の流れになります。国内在留中の方は、活動内容に応じて在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行います。また、近年は在留申請オンラインシステムの対象が拡大しており、申請~結果受領までオンラインで完結できる手続が増えています。期限管理(在留期限の前倒し申請)と添付書類の疎明が実務のポイントです。
在留資格に関連する法律と規則
根拠法は入管法で、資格の定義は別表第一・別表第二に定められています。審査の細目は施行令・施行規則・基準省令・告示に加え、上陸許可基準(二の表・四の表対象)や出入国在留管理庁の手引・Q&Aで具体化されています。実務では最新版を必ず確認します。
上陸許可基準とは?
上陸許可基準とは、入管法にもとづき日本に入国(上陸)を許可するための最低要件を、在留資格ごとに具体化した基準のことです。
とくに、入管法「別表第一」の二の表(就労資格・上陸許可基準あり)、四の表(非就労資格・上陸許可基準あり)に掲げられている在留資格については、この基準に適合していなければ上陸許可が下りません。基準の内容は法務省令・告示等(いわゆる「上陸許可基準省令」など)で定められています。
上陸許可基準は次の趣旨で設けられており、審査段階で当該基準への適合が確認されます。基準に適合しない場合は不許可となることがあります。
・活動の適正化:申請人の予定活動が、その在留資格の趣旨に合っているかを担保します。
・公正な受入れ:学歴・実務、報酬水準、受入機関の体制などを客観化し、ミスマッチや不法就労を防ぎます。
・審査の予見可能性:求められる要件を明文化し、申請者・企業が準備すべき資料を明確にします。
上陸許可基準への適合は、COE審査・査証審査・上陸審査の各段階で確認されます。二の表(技人国・企業内転勤・経営・管理・特定技能など)では、職務記述書(JD)・雇用契約書・報酬(日本人同等以上)・社会保険加入等の立証が重要になります。
日本における在留資格の種類
在留資格の29種類は、入管法「別表第一」を中心に五つの“表”へ体系化されています。
ここでは、一の表(就労資格)/二の表(就労資格・上陸許可基準あり)/三の表(非就労資格)/四の表(非就労資格・上陸許可基準あり)/五の表(特定活動)という区分に沿って、何ができる資格なのか/どんなときに使うのかを分かりやすく説明します。あわせて、身分・地位に基づく別表第二(居住資格)を説明します。
在留資格一覧
| 区分 | 在留資格 | 本邦において行うことができる活動(要旨) | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|---|
| 就労資格 | 外交 | 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員等および家族の外交活動 | 大使・公使・総領事 等 | 外交活動の期間内 |
| 就労資格 | 公用 | 外国政府・国際機関の公務に従事する者とその家族 | 領事館職員 等 | 5年/3年/1年/3月/30日/15日 |
| 就労資格 | 教授 | 大学等での研究・研究指導・教育 | 大学教員 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 芸術 | 収入を伴う芸術活動(興行を除く) | 作曲家・画家・著述家 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 宗教 | 外国の宗教団体に派遣される宗教活動 | 宣教師 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 報道 | 外国報道機関との契約に基づく取材等 | 記者・カメラマン 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 高度専門職1号 | 高度人材による研究・教育/専門業務/経営・管理 | ポイント制該当者 | 最長5年 |
| 就労資格 | 高度専門職2号 | 上記1号の実績等を踏まえた拡張的活動 | 高度人材 | 無期限 |
| 就労資格 | 経営・管理 | 事業の経営または管理 | 代表取締役・管理者 | 5年/3年/1年/6月/4月/3月 |
| 就労資格 | 法律・会計業務 | 国内資格に基づく法律・会計の専門業務 | 弁護士・公認会計士 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 医療 | 国内資格に基づく医療業務 | 医師・歯科医師・看護師 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 研究 | 公私機関との契約による研究 | 研究員・R&D 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 教育 | 小中高・専修学校等での教育 | 学校教員 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 技術・人文知識・国際業務 | 自然科学・人文科学の専門知識や国際業務に基づく活動 | エンジニア・通訳・デザイナー 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 企業内転勤 | 海外拠点から日本拠点への社内転勤(技人国相当の業務) | 転勤者 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 介護 | 介護福祉士資格に基づく介護・指導 | 介護職 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 興行 | 興行活動・芸能活動・スポーツ等 | 俳優・歌手・ダンサー 等 | 3年/1年/6月/3月/15日 |
| 就労資格 | 技能 | 熟練技能を要する業務 | 外国料理人・スポーツ指導者 等 | 5年/3年/1年/3月 |
| 就労資格 | 特定技能1号 | 特定産業分野における一定の技能による就労 | 分野試験合格者 等 | 通算最長5年(個別指定) |
| 就労資格 | 特定技能2号 | 同分野における熟練技能による就労 | 熟練技能者 | 3年/1年/6月(更新上限なし) |
| 就労資格 | 技能実習1号 | 技能実習法に基づく第1号の講習・業務従事 | 実習生 | 個別指定(1年以内) |
| 就労資格 | 技能実習2号・3号 | 同法に基づく第2号/第3号の業務従事 | 実習生 | 個別指定(2年以内) |
| 非就労資格 | 文化活動 | 収入を伴わない学術・文化活動 | 研究者 等 | 3年/1年/6月/3月 |
| 非就労資格 | 短期滞在 | 観光・親族訪問・商談など短期活動 | 観光客 等 | 90日/30日/15日 |
| 非就労資格 | 留学 | 学校教育法に基づく教育機関での就学 | 大学・専修・日本語学校 等 | 在籍機関等に応じ、4年3月を超えない範囲で個別指定 |
| 非就労資格 | 研修 | 受入機関の下での研修 | 研修生 | 1年/6月/3月 |
| 非就労資格 | 家族滞在 | 就労系等の在留資格者の配偶者・子の帯同 | 配偶者・子 | 5年を超えない範囲で個別指定 |
| 特定活動 | 特定活動 | 法務大臣が個別に指定する特別な活動 | ワーキングホリデー 等 | 5年を超えない範囲で個別指定 |
| 居住資格 | 永住者 | 永住が認められた者 | 永住許可者 | 無期限 |
| 居住資格 | 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 | 夫/妻・子 | 5年/3年/1年/6月 |
| 居住資格 | 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者/本邦出生で在留継続の子 | 配偶者・子 | 5年/3年/1年/6月 |
| 居住資格 | 定住者 | 特別な事情を考慮して在留を認められる者 | 日系人 等 | 5年/3年/1年/6月/個別指定 |
一の表(就労資格)
何ができる資格なのか
学術・文化・公務や報道など、専門性や公共性の高い活動で報酬を得て従事できる在留資格が並びます。
主な該当例
・外交/公用:各国の大使館・領事館や国際機関の職員などが対象になります。
・教授:大学・高専等で教育・研究を行う教員の方が対象になります。
・芸術:作曲家・美術家・作家などが、収入を伴う創作活動を行います(いわゆる「興行」は別枠です)。
・宗教:外国の宗教団体から派遣され、日本で布教等を行います。
・報道:海外メディアの記者・カメラマンなどが日本で取材・編集を行います。
どんなときに使うのか
大学からの招聘、在日公館への着任、海外メディアの日本常駐など、所属先・派遣元が明確なケースで用います。証明書類(招聘状・公的文書・担当業務の説明)を丁寧にそろえることが大切です。
在留資格「外交」とは?
「外交」の在留資格は、外国政府の大使・公使・外交官級職員が日本で外交上の公務を行うための在留資格です。外務省が外交官として承認した者と同居の配偶者・子が対象で、取扱いは一般の就労系在留資格と異なります。活動は各種折衝・式典・報告など公務に限定され、営利的な就労は認められません。手続きは外務省所管でCOE(在留資格認定証明書)の対象外です。在留カードは交付されず、外務省発行の身分証(ID)が交付されます。
在留資格「公用」とは?
「公用」の在留資格は、外国政府の大使館や領事館、国際機関の職員、またはこれらの機関に派遣される者、その家族が日本で活動するために付与されるものです。具体的には、外交官や領事館職員、国際連合などの国際機関職員などがこの在留資格の対象となります。この在留資格は、日本と外国との間の良好な関係を維持し、国際的な活動を円滑に行うために重要な役割を担っています。対象となる活動は、主に公的な職務の遂行であり、一般の就労とは異なる特別な位置づけがされています。このため、申請には外務省からの証明書など、他の在留資格とは異なる特別な書類が必要となることが特徴です。
在留資格「教授」とは?
「教授」の在留資格は、日本の「大学」「大学に準ずる機関」「高等専門学校」で、教育または研究活動を行う外国人に与えられるものです。この在留資格は、専門的な知識や経験を持つ外国人が、日本の教育機関で教鞭をとることを可能にし、日本の学術レベルの向上や国際交流の促進に貢献することを目的としています。具体的には、大学の教授、准教授、講師などが対象となります。申請にあたっては、担当する教育機関からの招聘状や、自身の学歴・職務経歴を証明する書類の提出が求められます。この在留資格は、単なる語学教師とは異なり、高度な専門性を有する教育・研究活動に特化している点が大きな特徴です。
在留資格「芸術」とは?
「芸術」の在留資格は、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、工芸などの分野で、収入を伴う芸術活動を行う外国人に与えられるものです。この在留資格は、日本の文化や芸術の多様性を高め、国際的な文化交流を促進することを目的としています。具体的には、画家、作曲家、彫刻家、作家、写真家、舞台演出家などが対象となります。申請には、過去の芸術活動の実績や、日本での活動計画を証明する書類が必要です。ただし、単なるアマチュア活動や、観光を主目的とした滞在には適用されません。この在留資格は、専門的な芸術家が日本でその才能を発揮するための重要な手段であり、日本の芸術界の発展にも大きく貢献しています。
在留資格「宗教」とは?
「宗教」の在留資格は、外国の宗教団体から派遣され、日本国内で宗教活動を行う外国人に与えられるものです。この在留資格は、日本の信仰の自由を尊重し、国際的な宗教交流を促進することを目的としています。具体的には、宣教師、僧侶、牧師、神父などが対象となります。日本国内の宗教団体から受け入れ証明書や、派遣元の宗教団体の活動内容を証明する書類が必要となります。この在留資格は、あくまで宗教活動を行うためのものであり、宗教活動以外の就労は認められていません。また、宗教活動の内容が特定の思想やカルト的なものと見なされる場合は、在留資格の取得が困難となる場合があります。
在留資格「報道」とは?
「報道」の在留資格は、外国の報道機関(新聞社、通信社、放送局など)に所属するジャーナリストやカメラマンなどが、日本国内で取材活動を行うために付与されるものです。この在留資格は、国際的な情報流通を円滑にし、日本の情報を正確に世界に伝えることを目的としています。具体的には、記者、編集者、ニュースカメラマンなどが対象となります。申請には、所属する外国の報道機関からの派遣証明書や、具体的な取材計画を証明する書類が必要です。この在留資格は、単なる観光や一般的な業務での滞在とは異なり、高度な専門性と公共性を持つ報道活動に特化しています。また、報道の自由を保障する観点からも重要な在留資格です。
二の表(就労資格・上陸許可基準あり)
何ができる資格なのか
企業活動を中心に、専門性・熟練性に基づく就労ができます。上陸許可基準では、学歴(または相当実務)と職務の関連性、職務記述書(JD)、雇用契約の適法性、報酬の日本人同等性、受入機関の継続性(事業所の実在)などが確認されます。
主な該当例
・高度専門職(1号・2号):ポイント制で学歴・年収・研究実績などを総合評価し、優遇措置が受けられます。
・技術・人文知識・国際業務(技人国):エンジニア、通訳・翻訳、企画・マーケティングなど学歴(または相当実務)と職務の関連性が鍵になります。
・企業内転勤:海外拠点から日本拠点へ同一企業・グループ内での転勤に使います。
・経営・管理:日本で事業を経営・管理する場合に使います(事務所の実在性・事業継続性の立証が重要です)。
・法律・会計業務/医療/研究/教育/介護:国内の国家資格や専門性に基づいて就労します。
・興行:俳優・歌手・ダンサー、プロスポーツ選手などの興行・芸能活動を行います。
・技能:外国料理の調理師や貴金属加工などの熟練技能に従事します。
・特定技能(1号・2号):人手不足分野で一定以上の技能(1号)や熟練技能(2号)を持つ方が就労します。
・技能実習:技能移転を目的とする実習生の受入れに使います(将来的に新制度へ移行予定です)。
どんなときに使うのか
新卒・中途での採用、海外グループからの転勤、海外人材による日本での起業・経営など、企業での通常の雇用・転勤・起業等に広く利用します。職務記述書・雇用契約・学歴/実務の関連性を資料で説明することが重要です。
上陸許可基準チェック(技人国・経営管理など)
・学歴/専攻または相当実務と職務内容の関連性が説明できるか
・職務記述書(JD)と雇用契約書が整合しているか
・報酬が日本人同等以上で、社会保険加入・労働条件が適法か
・事業所の実在/継続性(経営・管理)を資料で示せるか
在留資格「高度専門職」とは?
「高度専門職」の在留資格は、日本の経済成長に貢献する高度な専門的な能力を持つ外国人に与えられるもので、ポイント制が採用されているのが特徴です。学歴、職歴、年収などの項目をポイント化し、合計点が一定の基準を満たすことで申請が可能です。この在留資格は、高度な能力を持つ外国人の受け入れを促進し、日本のイノベーションや国際競争力の強化を図ることを目的としています。他の就労系在留資格に比べ、在留期間が最長で5年と長く設定され、配偶者の就労や親の帯同が認められるなど、優遇措置が多数設けられています。
在留資格「経営・管理」とは?
「経営・管理」の在留資格は、日本で事業を経営、または管理に従事する外国人に与えられるものです。この在留資格は、日本国内で事業を立ち上げたい外国人や、すでに存在する事業の経営者、管理職として働く外国人に対して付与されます。具体的には、株式会社や合同会社の代表取締役、取締役、事業部長などが対象となります。申請には、事業計画書、会社設立の登記書類、事業所の賃貸借契約書など、事業の実態を証明する多くの書類が必要です。また、事業の安定性や継続性も審査の重要なポイントとなります。この在留資格は、日本の経済活性化や雇用の創出に貢献する外国人を積極的に受け入れることを目的としています。
在留資格「法律・会計業務」とは?
「法律・会計業務」の在留資格は、日本の国家資格を持つ弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの外国人が、日本国内で専門的な業務に従事するために付与されるものです。この在留資格は、専門的な知識と資格を有する外国人が、日本の法務や会計分野で活躍することを可能にし、国際的なビジネス活動を円滑に進めることを目的としています。申請には、日本の国家資格の証明書や、所属する事務所からの雇用契約書などが必要です。高度な専門性を要する業務であり、日本の国家資格の取得が前提となるため、在留資格の中でも特殊な位置づけにあります。
在留資格「医療」とは?
「医療」の在留資格は、日本の国家資格を持つ医師、歯科医師、看護師などの外国人が、日本国内で医療業務に従事するために付与されるものです。この在留資格は、日本の医療水準の維持向上と、国際的な医療分野における協力関係を促進することを目的としています。申請には、日本の医師免許や看護師免許などの国家資格の証明書と、勤務する医療機関からの雇用契約書が必要です。高度な専門知識と技術が求められる業務であり、日本の医療従事者と同様の資格が求められるため、非常に厳格な審査が行われます。
在留資格「研究」とは?
「研究」の在留資格は、日本の公的機関や民間の企業などで、研究活動を行う外国人に付与されるものです。この在留資格は、日本の科学技術の進歩や、新たな知見の創出に貢献する専門的な研究者を積極的に受け入れることを目的としています。具体的には、研究所の研究員、企業のR&D部門の研究者などが対象となります。申請には、研究機関からの招聘状や、自身の研究計画、学歴・職務経歴を証明する書類が必要です。この在留資格は、特定の研究テーマに特化した専門的な活動が前提となり、高度な知識や技術を持つ外国人の活躍を支援します。
在留資格「教育」とは?
「教育」の在留資格は、日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校などで教育活動を行う外国人に付与されるものです。これは、日本の子どもたちに外国語や国際的な視点を教えることで、国際理解教育を促進することを目的としています。具体的には、公立・私立学校の教員や、特定の専修学校の教員などが対象となります。申請には、所属する教育機関からの雇用契約書や、自身の学歴・職務経歴を証明する書類が必要です。この在留資格は、在留資格「教授」とは異なり、大学などの高等教育機関以外の教育機関での活動に特化している点が特徴です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業などでエンジニア、デザイナー、通訳、マーケティング担当者など、幅広い職種で働く外国人に最も多く取得されている在留資格です。この在留資格は、専門的な知識や技術を持つ外国人が、日本の産業界で活躍することを目的としています。技術分野では、情報処理や機械工学、人文知識分野では、企画・営業・経理、国際業務分野では、語学力を活かした通訳や翻訳、海外取引業務などが含まれます。申請には、大学等の卒業証明書や、従事する業務との関連性を証明する書類が必要です。日本の企業にとって、多様な人材を確保する上で非常に重要な在留資格です。
在留資格「企業内転勤」とは?
「企業内転勤」の在留資格は、外国にある本社や支社などから、日本の事業所に転勤する外国人に付与されるものです。この在留資格は、国際的な企業活動を円滑にし、企業グループ内での人事異動を柔軟に行うことを目的としています。具体的には、海外の支社で働く従業員が、日本の本社や支社に転勤する場合などが該当します。申請には、転勤元と転勤先の会社間の関係性、本人の職務内容、職務経験などを証明する書類が必要です。転勤前の業務内容と日本での業務内容が関連していることが求められます。この在留資格は、単なる新規採用とは異なり、企業グループ全体でのグローバルな人材活用を可能にするものです。
在留資格「介護」とは?
「介護」の在留資格は、日本の介護施設などで介護福祉士の資格を持つ外国人が、専門的な介護業務に従事するために付与されるものです。この在留資格は、深刻な人手不足に直面する日本の介護分野において、質の高い外国人材を受け入れることを目的としています。申請には、日本の介護福祉士の資格証明書と、勤務する介護施設からの雇用契約書が必要です。2017年に新設された比較的新しい在留資格であり、介護分野における外国人材の活用を促進するための重要な制度です。また、介護福祉士養成施設を卒業した外国人もこの在留資格の対象となる場合があります。
在留資格「興行」とは?
「興行」の在留資格は、演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行活動を行う外国人に付与されるものです。この在留資格は、日本のエンターテイメント業界の活性化と、国際的な文化交流を促進することを目的としています。具体的には、外国人アーティスト、ミュージシャン・歌手、俳優、タレント、モデル、ダンサー、プロスポーツ選手などが対象となります。申請には、興行を行う主催者からの契約書や、公演の概要を証明する書類が必要です。また、報酬額や公演日数など、細かな要件が定められている場合が多く、専門性の高さが求められます。
在留資格「技能」とは?
「技能」の在留資格は、日本の産業において特殊な熟練した技能を要する業務に従事する外国人に付与されるものです。この在留資格は、日本の伝統文化や産業の技術を維持・発展させることを目的としています。具体的には、外国料理の調理師、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ、貴金属加工職人などが対象となります。申請には、従事する業務に関して原則10年以上の実務経験を証明する書類が必要です(ただし、外国料理の調理師の場合は職務経験が10年、航空機の操縦士の場合は1,000時間以上の飛行経歴、スポーツ指導者の場合は3年以上の実務経験または国際的な競技会出場経験、ソムリエの場合は5年以上の実務経験かつ国際ソムリエコンクール出場経験などの例外があります) 。
在留資格「特定技能」とは?
「特定技能」の在留資格は、中小企業等における深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野で一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れることを目的として、2019年4月に新設されました。この在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、1号は特定の産業分野で相当程度の知識または経験を要する業務に従事する外国人、2号は熟練した技能を要する業務に従事する外国人が対象となります 。現在、介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業分野で外国人の受け入れが行われています 。
在留資格「技能実習」とは?
「技能実習」の在留資格は、日本の企業で働きながら、日本の優れた技能や技術、知識を習得し、母国に帰国後、その国の経済発展に役立てることを目的としたものです。この在留資格は、国際貢献の一環として位置づけられています。技能実習生は、原則として3年間の実習期間中に、農業、漁業、建設業、食品製造業など様々な分野で実践的な技術を学びます。申請には、日本の受け入れ企業や監理団体、本人の母国にある送り出し機関との間で、実習計画を定めた書類が必要です。技能実習制度は、技術移転を通じた国際貢献を目的としていますが、新制度「育成就労制度」へ2027年6月頃までに移行される予定です 。
三の表(非就労資格)
何ができる資格なのか
就労を目的としない滞在が対象です。報酬を得る活動は原則できません。
主な該当例
・文化活動:収入を伴わない研究・芸術修業・伝統文化の習得などを目的とする滞在です。
・短期滞在:観光・親族訪問・商談・会議参加など、短期間の訪日に使います。
どんなときに使うのか
招へい・見学・短期商用など、短期かつ非就労の目的で来日する場合に使います。
謝金や費用弁償の可否は内容・金額・性質等により取扱いが分かれます。報酬を得る活動は原則できませんので、具体的な支給設計は事前に確認することをおすすめします。短期来日の講演・会議参加などで謝金や費用弁償が見込まれる場合は、短期滞在の許容範囲と契約文言を事前に確認します(報酬活動は原則不可)。グレーな場合は受入機関のガイダンスを整えておくと安全です。
在留資格「文化活動」とは?
「文化活動」の在留資格は、収入を伴わない学術上または芸術上の活動を行う外国人に与えられるものです。この在留資格は、日本の文化や社会について学ぶ外国人、日本の伝統文化を体験する外国人などを対象としており、国際的な文化交流を促進することを目的としています。具体的には、学校に在籍せず、雇用契約も伴わない個人の研究・芸術修業・伝統文化の習得などが該当します。この在留資格は、収入を伴う活動は原則として認められていません。申請には、受け入れ機関からの証明書や活動計画書が必要です。学校で正規に就学する場合は「留学」が原則です。
在留資格「短期滞在」とは?
「短期滞在」の在留資格は、観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習、業務連絡、市場調査など、日本に短期間滞在する外国人に与えられるものです。滞在可能日数は90日/30日/15日の区分です(ビザ免除国もあり)。報酬を得る活動や事業経営は原則不可のため、謝金・費用弁償の扱いは事前に個別確認することをおすすめします。ただし、報酬を得る活動や事業の経営は原則として認められていません。短期滞在ビザは、日本への入国目的が明確であり、滞在期間中に違法な活動を行わないことが条件となります。
四の表(非就労資格・上陸許可基準あり)
何ができる資格なのか
学業や研修、帯同家族など、活動内容が明確に限定された非就労資格です。上陸時に基準適合が確認されます。
主な該当例
・留学:大学・専修学校・日本語教育機関などで学びます(原則就労不可。アルバイトは資格外活動許可で週28時間以内)。
・研修:受入機関で技能・知識の習得を目的に研修します。就労活動は一切できません。
・家族滞在:就労系等の在留資格を持つ方の配偶者・子が帯同します(原則就労不可。アルバイトは資格外活動許可で週28時間以内)。
どんなときに使うのか
留学生の受入れ、企業での職業訓練、就労者の家族の帯同などに使います。在籍証明・研修計画・扶養関係など、裏付け資料の整備が大切です。
在留資格「留学」とは?
「留学」の在留資格は、日本の大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、日本語教育機関などで教育を受ける外国人に付与されるものです。この在留資格は、日本の教育機関で専門的な知識や技術を習得し、将来的に母国や日本で活躍する人材を育成することを目的としています。申請には、在籍する教育機関からの入学許可証や、学費や生活費の支払い能力を証明する書類が必要です。原則として、学業に専念することが求められますが、資格外活動許可がある場合に限り、原則週28時間以内のアルバイトが可能です(長期休業中は別基準)。
在留資格「研修」とは?
「研修」の在留資格は、日本の公的機関や民間企業で、座学・見学などの非生産的な方法で技能や知識を学ぶ在留資格です。雇用契約に基づく労務提供や生産活動には従事できません(技能実習とは制度趣旨・枠組みが異なります)。この在留資格は、研修生が習得した技術を母国に持ち帰り、その国の産業発展に貢献することを目的としています。具体的には、日本の技術やノウハウを学ぶために企業に受け入れられる場合などが該当します。申請には、研修を受け入れる機関からの研修計画書や、研修生の学歴・職務経歴を証明する書類が必要です。あくまで「研修」であり、単純労働を目的としたものではありません。技能実習と似ていますが、研修は雇用契約に基づかない場合が多いという点で異なります。
在留資格「家族滞在」とは?
「家族滞在」の在留資格は、就労系や留学などの在留資格を持つ外国人が日本に滞在する場合、その配偶者や子が日本で生活するために付与されるものです。この在留資格は、外国人が日本で安心して生活できるよう、家族の帯同を可能にすることを目的としています。具体的には、日本で働く外国人の妻や夫、子どもが対象となります。申請には、扶養者との関係を証明する書類や、扶養者の収入証明が必要です。この在留資格を持つ方は、原則として就労することはできませんが、資格外活動許可がある場合に限り、原則週28時間以内のアルバイトが可能です)。
五の表(特定活動)
何ができる資格なのか
法務大臣が個別に指定する特別な活動が対象です。指定書(告示・個別指定)に就労可否・活動範囲・期間などが細かく記載されます。
主な該当例
・ワーキング・ホリデー:休暇を目的としつつ、一定範囲で就労が可能です(対象国との協定に基づきます)。
・外交官等の家事使用人:外交官・公館職員に帯同する家事使用人が対象です。
・経済連携協定(EPA)関係:外国人看護師・介護福祉士候補者などが該当します。
・本邦大学卒業者の特定活動(いわゆる「46号」など):日本の大学等を卒業後、一定要件のもとで幅広い業務に従事できます。
どんなときに使うのか
既存の在留資格に当てはまらないが、政策目的に照らして受入れが相当とされるケースで使います。指定条件を一字一句確認し、雇用契約・業務内容を適合させることが重要です。
在留資格「特定活動」とは?
「特定活動」の在留資格は、他の在留資格に該当しない特別な活動を行う外国人に、個別の状況に応じて付与されるものです。この在留資格は、法律や制度の枠組みに収まらない多様なケースに対応するため設けられた、いわば「特別な在留資格」です。具体的には、ワーキング・ホリデー、インターンシップ、経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者など、告示や個別指定で活動内容が定められます。申請には、活動内容に応じた詳細な計画書や証明書類が必要となります。
別表第二(居住資格)
何ができる資格なのか
身分・地位に基づく在留で、活動に原則制限がありません。どの分野でも就労できます。
主な該当例
・永住者:在留期間の上限がなく、最も安定した在留が可能です。
・日本人の配偶者等/永住者の配偶者等:配偶者・実子などが対象で、活動制限はありません。
・定住者:特別な事情を考慮して定住が認められる方が対象で、期間は個別に指定されます。
どんなときに使うのか
家族関係や長期居住などの事情に基づき、自由度の高い在留が必要な場合に使います。
永住者・日本人の配偶者等・定住者などは活動制限なしのため、雇用側は在留カードの資格欄「就労制限なし」を確認し、就業規則・労働法の範囲で運用します。在留期限の有無(永住者は期限なし)も人事台帳で区分管理すると実務がスムーズです。
在留資格「永住者」とは?
「永住者」の在留資格は、日本での在留期間に制限がなく、活動内容にも制限がない、最も安定した在留資格です。この在留資格は、日本に長期にわたり居住し、日本の社会に貢献している外国人が、日本で永続的に生活することを可能にするものです。申請には、原則として10年以上の日本での在留歴、納税義務の履行、公的年金や健康保険の支払い、安定した生活基盤など、厳格な要件が定められています。永住許可を取得すると、就労活動に制限がなくなり、住宅ローンなども組みやすくなるなど、様々なメリットがあります。
在留資格「日本人の配偶者等」とは?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者(夫または妻)、または日本人の実子・特別養子である外国人に付与されるものです。この在留資格は、日本国民と密接な関係を持つ外国人の日本での生活を保障し、家族としての生活を円滑にすることを目的としています。申請には、婚姻関係や親子関係を証明する書類、夫婦の交流歴を証明する写真や手紙、日本人の扶養能力を証明する書類が必要です。この在留資格を持つ外国人は、活動内容に制限がなく、原則としてどのような職種でも就労することができます。
在留資格「永住者の配偶者等」とは?
「永住者の配偶者等」の在留資格は、永住者の配偶者(夫または妻)、または永住者の実子である外国人に付与されるものです。この在留資格は、永住者とその家族が日本で安定した生活を送ることを可能にし、家族としての結びつきを保障することを目的としています。申請には、永住者との婚姻関係や親子関係を証明する書類、永住者の扶養能力を証明する書類が必要です。この在留資格を持つ外国人は、活動内容に制限がなく、原則としてどのような職種でも就労することができます。ただし、永住者本人が永住許可を取り消された場合、この在留資格も影響を受ける可能性があります。
在留資格「定住者」とは?
「定住者」の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮し、個別に定住を認める外国人に付与されるものです。この在留資格は、他の在留資格では日本での滞在が困難な特別な事情を持つ外国人の生活を保障することを目的としています。具体的には、日系二世や三世、外国人の子の連れ子、難民認定申請中の者や特定地域の出身者など、様々なケースがあります。定住者の在留資格は、個々の事情に応じて柔軟に判断されるため、非常に多様な事例が存在します。活動内容に制限がなく、就労も可能です。
まとめ:在留資格を正しく理解し、適切に申請を進めることが重要
日本の在留資格は 29種類 に細分化され、それぞれに「できる活動」と「求められる要件」が明確に定められています。
- 活動に基づく資格(教授・技人国・技能・特定技能など)
- 非就労資格(留学・短期滞在・文化活動など)
- 特定活動(個別に法務大臣が指定する活動)
- 身分・地位に基づく資格(永住者・日本人の配偶者等・定住者など)
在留資格は単なるラベルではなく、就労範囲や在留期間、家族帯同の可否に直結する重要な制度です。誤った申請や条件不一致は、不許可や不法就労のリスクにつながります。
当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。
👉在留資格・ビザ申請でお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。