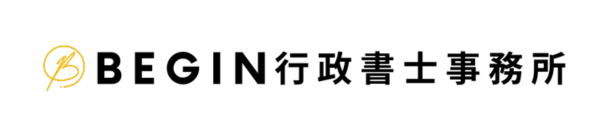はじめに|永住資格は「ゴール」ではなく「スタート」
永住資格(永住権)は、日本に長期的かつ安定的に暮らすための最も強力な在留資格です。就労や活動の制限がなく、在留期間の更新も不要なため、多くの外国人が目指すゴールのひとつとなっています。
しかし、永住資格は「一度許可されれば一生安泰」というものではありません。
実際には永住資格にも 「取り消し」というリスク があります。特に2024年の入管法改正により、その取り消し事由は大幅に拡大しました。従来は重大な犯罪や虚偽申請が中心でしたが、現在は税金や社会保険料の滞納や不払い、重大な犯罪歴、入管法上の義務違反といった「生活上の不備」も永住資格の取り消し対象となります。つまり、永住資格は「守る資格」であり、日々の生活において適切に義務を果たさなければ維持できません。
本記事では、永住資格の基本的な仕組みから取消事由、具体的事例、家族への影響、そして再取得の可能性や予防策までを徹底解説します。永住資格をお持ちの方、これから申請を検討している方、またご家族に永住資格保持者がいる方にとって必読の内容です。ぜひ最後までご覧ください。
永住資格とは?帰化との違いを理解する
まずは「永住資格」とは何かを正確に押さえておきましょう。永住者は確かに安定した立場を得られますが、帰化と同じではありません。両者の違いを理解することが、取り消しリスクへの正しい備えにつながります。
永住資格の定義と特徴
入管法上の「永住者」とは、法務大臣が「その者の永住を認めることが適当」と判断した外国人に与えられる在留資格です。一方で、日本国籍を取得したわけではありません。国際的にはあくまで「外国人」として扱われ、入管法の管理下にあります。
永住権の特徴
- 在留期間の制限がない(更新不要)
- 就労制限がなく、どの業種にも従事可能
- 日本での生活に大幅な自由が与えられる
- 配偶者や子どもの在留資格取得が容易になる
帰化との違い
帰化は国籍法に基づいて日本国籍を取得する手続きであり、日本人としての権利と義務を持つことになります。
- 永住資格 → 外国籍のまま日本に住む権利
- 帰化 → 日本国籍を取得し、完全に日本人として扱われる
永住権と帰化はどちらも日本に住むための権利ですが、大きな違いがあります。
永住権は「在留資格」の一種で、日本国籍は取得せず、外国籍のまま日本に無期限で在留・就労ができる権利です。外国籍のまま日本で生活の基盤を築きたい場合に適しています。
帰化申請は「国籍を日本に変える」手続きであり、外国籍を放棄し日本国民としての権利義務を負うようになります。日本人として生活を送りたい場合に選択します。
| 項目 | 永住権 | 帰化 |
| 国籍 | 外国籍のまま | 日本国籍に変更 |
| パスポート | 外国のパスポートを使用 | 日本のパスポートに切替 |
| 公民権(選挙権など) | なし | あり |
| 再入国許可 | 原則必要 | 不要(日本人扱い) |
従来から存在した永住資格の取消事由
永住資格は「一度取れば一生安泰」と誤解されがちですが、従来から取り消し規定が存在します。ここでは、2024年の改正前から規定されていた典型的な取消事由を解説します。
再入国許可を超過した場合
永住資格者が海外に出国する際は、原則「再入国許可」または「みなし再入国許可」を取得します。
これを超過すると、永住資格は自動的に失効します。
典型事例
母親の介護のため一時帰国しましたが、再入国許可の有効期限を誤って解釈し、半年遅れて帰国となった場合は、結果的に永住資格を失い、再度日本に戻るためには新しい在留資格を申請し直すことになった。

退去強制処分を受けた場合
重大な犯罪を犯した場合、退去強制の対象となり、永住資格も自動的に取り消されます。
典型事例
長年日本に住んでいたものの、犯罪で実刑判決を受け、収監後に退去強制処分となり、資格を保持できなくなった。
虚偽申請
永住許可の際に提出した書類が虚偽であることが後に発覚すると、資格は取り消されます。
典型事例
収入証明など書類を偽造して永住ビザを取得し、数年後の税務調査で虚偽が発覚し、永住資格を失った。
2024年入管法改正で拡大した取消事由
2024年の入管法改正は、日本に住む永住者に大きな影響を与えるものでした。従来、永住資格が取り消されるのは「虚偽申請が発覚した場合」や「重大犯罪を犯した場合」にほぼ限定されていました。しかし改正後は、 日常生活に直結する社会的義務の不履行も取消事由に含まれる ようになりました。
背景には、日本に住む永住者の人口が年々増加していることがあります。法務省のデータによれば、永住者は在留外国人全体の約半数を占めるまでになっています。その一方で、永住者の中には「税金や社会保険料を長期間支払わない」「住所変更の届出を怠る」など、日本人であれば当然守るべき義務を果たしていないケースが社会問題化していました。
政府はこうした状況を踏まえ、永住者に対して「権利と同時に日本人と同じ義務を負う」ことを求める姿勢を鮮明にしています。改正法により、単に「犯罪歴がない」ことだけでは永住資格を維持できず、誠実に社会的義務を果たすこと が新たな条件となったのです。
税金・社会保険料の不払い
もっとも大きな改正点のひとつが、税金や社会保険料を 故意に支払わない行為 が取消対象となったことです。ここでいう「故意」とは、支払能力があるにもかかわらず意図的に納税や保険料納付を怠るケースを指します。経済的困難による一時的な滞納や、分納・猶予を申請している場合は直ちに対象にはなりません。
- 対象となる税金:住民税、所得税、消費税(事業者の場合)など
- 対象となる保険料:国民健康保険、国民年金、厚生年金保険料、社会保険料
典型事例
個人事業主として活動していた外国人永住者が、数年間にわたり住民税や国民年金を納めていなかったことが調査で発覚しました。税務署からの督促にも応じず、資金は十分にあるにもかかわらず納付を回避していたため、入管は「悪質な不払い」と判断し、永住資格の取り消し手続が開始されました。
重大犯罪による拘禁刑
従来から重大犯罪は取消理由のひとつでしたが、改正法では「拘禁刑(懲役・禁錮など自由刑)」を受けた場合が明確に規定されました。刑期の長さや犯罪の性質が考慮されますが、社会的に強い非難に値する行為であれば、刑期終了後でも資格の取り消しが行われる可能性があります。
典型事例
飲酒運転の末に人身事故を起こし、過失致死罪で懲役刑を言い渡された外国人永住者がいました。刑期を終えて出所した後、入管は「永住者としての品行要件を満たさない」と判断し、永住資格を取り消しました。その後、退去強制の対象となり、家族にも大きな影響が及びました。
入管法上の義務違反
さらに、入管法で定められている日常的な義務を怠った場合も取消対象に追加されました。具体的には以下のような行為です。
- 住居地の届出を怠る:引っ越し後14日以内に新住所を届け出る義務があります。
- 在留カードを携帯しない:常に携帯義務があり、提示を求められたときに応じなければなりません。
- 資格外活動の繰り返し:例えば「技人国ビザ」で単純労働を継続的に行うなど。永住者であっても、虚偽活動や義務違反が繰り返されれば取消のリスクがあります。
典型事例
ある外国人永住者は引っ越し後に住居地変更届を出さず、1年以上も旧住所のまま放置していました。その間、役所や税務署からの通知も届かず、調査で発覚。入管は「社会的義務を軽視した悪質な違反」と判断し、永住資格の取消対象としました。
家族への影響と配慮
永住資格の取り消しは本人だけでなく、配偶者や子どもなど家族の在留資格にも直結直結します。家族が日本で生活基盤を築いている場合、突然の取消は大きな混乱をもたらします。永住資格を失った後も、本人の事情や家族関係に応じて他の在留資格への切替えて、日本で生活を続けられる可能性はありますが、その場合、許可が保証されるものではありません。
影響のパターン
- 日本人配偶者がいる場合
永住資格を持つ外国人本人が取消されても、日本人配偶者との婚姻を継続していれば「日本人の配偶者等」へ切替できる可能性があります。 - 子どもが日本で生まれ育っている場合
子どもが未成年で日本での生活歴が長ければ「定住者」資格に切替できる可能性があります。 - 専門性のある職務に従事している場合
就労系在留資格(技術・人文知識・国際業務など)へ切替できる可能性があります。 - 家族全員が外国籍の場合
取消後に他の在留資格が認められなければ、全員が帰国を余儀なくされるケースもあります。
取り消し後の再申請の可能性とハードル
一度取り消された永住資格を再度取得することは可能ですが、道のりは平坦ではありません。取り消し理由を解消し、数年間の誠実な生活実績を積むことが必要です。再申請には「過去の取消事由を完全に解消した」という客観的証拠が不可欠です。
再申請の最低条件
- 税金・社会保険料を数年間きちんと納付する
- 犯罪歴がなく、素行に問題がないことを証明する
- 安定した収入と生活基盤を持つ
取り消しを防ぐための予防策
永住資格の取消を防ぐには「日常生活の小さな注意」が大きな違いを生みます。下記のような予防策を行い、「誠実な生活態度」を可視化することが永住資格維持の最も有効な手段です。
- 税金・保険料は口座振替や給与天引きで確実に納付する
- 住居地変更届を速やかに提出する
- 軽微な交通違反も繰り返さない
- 行政からの通知を無視しない
まとめ|永住資格を守るために大切なこと
永住資格は「一生安泰の権利」ではなく、社会的義務を誠実に果たすことで維持される資格です。取り消しを防ぐためには、税金や保険料を期日通り納めること、法令を遵守して生活すること、そして入管や役所からの通知を決して軽視しないことが不可欠です。
万が一、取り消しの通知を受けた場合でも、弁明や在留資格変更の余地はあります。専門家の助言を受けながら、適切に対応することが生活基盤を守る最善策となります。
当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。
👉永住許可申請でお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
永住許可申請は窓口申請しか認められておらず、オンライン申請はできません(2025年8月現在) 。
現在、当事務所では、永住許可申請のご依頼について、東京出入国在留管理局の管轄区域(東京都、神奈川県、新潟県、埼玉県、群馬県、千葉県、茨城県、栃木県、山梨県、長野県) にお住まいの方、東京出入国在留管理局立川出張所の管轄区域(東京都、神奈川県相模原市、山梨県) にお住まいの方を中心に、ご相談、ご依頼をお受けしております。