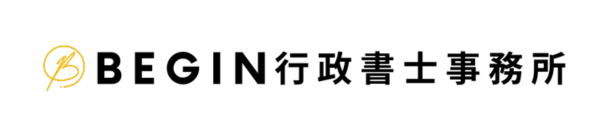Q&A
技人国ビザに関するよくある質問
基礎知識・適格性(定義/要件/日本語/学歴)
技人国ビザとは何ですか?
「技術」「人文知識」「国際業務」に該当する知的・専門的な業務に従事するための就労資格です。大学等の学位や相当の実務経験10年(「国際業務」分野の場合は3年以上で可)を根拠に、職務内容との関連性、日本人同等待遇、受入体制が総合的に審査されます。現場作業や単純労働が主な配置は対象外です。
技人国で必要な日本語レベルはどの程度ですか?
業務での使用場面に依存します。顧客対応・稟議・契約交渉が多いならN2〜N1が目安、開発中心で社内英語運用ならN3前後でも成り立つ場合があります。審査では「どの場面で、どの頻度で、どんな精度で使うか」の具体化が重要です(職務記述書に明記します)。
主な許可要件を教えてください。
①専門性の根拠(学位/実務年数) ②職務との関連性(専攻→実務の論理接続) ③待遇の同等性(賃金規程・同職比較) ④受入体制(登記・事業実態・社保加入)。この4点を数値・書面で裏づけると安定します。
学位と職務の関連性は厳密一致が必要ですか?
厳密一致は不要ですが、“学術知見を業務にどう適用するか”を説明できれば評価されます(例:心理→UX調査、経済→データ分析、機械→生産技術)。現業比率が高く見える記載は不利です。業務比率(%)で「知的業務が主」を示してください。
海外大学の学士でも申請できますか?
可能です。学位の実在性・専攻内容・成績証明を提出し、職務との接続を理由書で明示します。英語書類は日本語訳を添付します。
学歴や職歴が不足している場合でも取得できますか?
「技術・人文知識・国際業務」などは原則として大学卒業または実務経験10年以上が要件です。ただし、職種によっては専門学校卒業や短大卒業でも認められる場合があります。特定技能や技能ビザは学歴要件がなく、試験合格や技能実習経験などでカバー可能です。在留資格の種類や個別のケースごとに条件を確認します。
専門学校卒でも対象になりますか?
職種により得意・不得意があります。IT・デザイン等は履修内容と作品/実装実績で補強すれば通ることがあります。専攻と業務の橋渡しを具体的に行ってください。
実務10年で学歴要件を代替できますか?
可能です。在籍証明・職務証明・雇用契約の写し・納税証憑などで期間と内容を裏づけます。担当領域・成果物の説明を年表にして出すと通りやすいです。
どの職種が対象ですか?
例としてシステム開発、データ分析、設計、研究、翻訳通訳、広報、マーケ、法務、会計、企画、貿易実務(国際取引)、語学教員(民間)など技人国ビザの対象となる職種は非常に幅広く、多くの業界で必要とされています。。共通点は知的・専門的であることです。
理由書は必ず必要ですか?
理由書は出入国在留管理庁(入管)のホームページでは必須ではありませんが、許可を得るためには理由書の提出を強く推奨します。採用の背景、業務内容の詳細、職務の専門性、専攻/職歴との整合、待遇、受入体制等の詳細を論理的に説明するもので、補正が減り審査も安定します。
日本人と同等以上の待遇はどう示したら良いですか?
賃金規程・等級基準・職種レンジ・同職比較を添付し、基本給・固定残業の算定根拠や超過精算まで明記します。社会保険の適用も不可欠です。
企業側の準備・体制(書類/派遣・請負/新設会社)
採用時に会社が用意すべき資料は何ですか?
①法人資料(登記事項、会社案内、決算または資金計画)②雇用資料(雇用契約、就業規則、賃金規程、社保加入)③業務資料(職務記述書、組織図、業務フロー、成果物例)④派遣/請負なら三者契約・指揮命令の所在・偽装請負の回避策などを用意します。
派遣会社(派遣就労)でも採用可能ですか?
可能ですが厳格に審査され難易度があがります。派遣許可、指揮命令は派遣先、成果物の帰属、ID管理、多重派遣の抑制などを契約で明確化する必要があります。
新設・赤字法人でも採用できますか?
可能ですが資金力と継続性の説明が必須です。12か月の資金繰り計画、受注見込み、雇用の必要性、社保適用を具体化する必要があります。数値と根拠書面が弱いと不許可になりやすいです。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」はなぜ要るのですか?
実際に給与を支払っている体制(雇用の実体・同等待遇)を客観確認するためです。初採用で提出困難なら代替資料(賃金規程、過去の給与支払実績、見込み)を丁寧に用意します。
申請ルート・スケジュール
海外採用の基本的な流れを教えてください。
在留資格認定証明書申請(COE申請)→交付→在外公館で査証→入国・在留カード交付の順です。入社日から逆算して、1〜3か月の審査+査証・渡航準備を見込み、早めに着手します。
国内在留者の切替ではCOEは不要ですか?
はい、原則在留資格変更許可申請で切替できます。審査観点はCOEと同じため、職務記述書(JD)・待遇・受入体制を同じ精度で整えます。
卒業見込みの時点で申請できますか?
可能です。国内の大学等の卒業見込みであれば、卒業見込証明書・内定書を添付し、在留資格「留学」からの在留資格変更許可申請を行います。許可は卒業を前提に判断されます。
卒業証明書や成績証明書は原本が必要ですか?
はい。原本が必要です。卒業証明書や成績証明書は大学の事務所窓口などで手数料を支払うことで発行してもらえます。
審査期間はどれくらいかかりますか?
ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
在留期間更新許可申請:2週間〜1.5か月
混雑状況や追加資料の要請があれば、さらに時間がかかる場合があります。
転職・配置転換・届出
転職しても同じ在留資格で働けますか?
職務が引き続き技人国の範囲なら可能です。転職後14日以内に「契約機関に関する届出」を入管に提出する義務があります。転職先の業務内容が現在の在留資格に合致していれば、そのまま更新可能です。任意申請ですが、新しい勤務先でも現在保有している在留資格の範囲内で就労できることを証明するための転職にあたり就労資格証明書を取ると次回更新が安定します。
現在の在留資格と職種が異なる場合は就労するために「在留資格変更許可申請」が必要です。
就労資格証明書はいつ取得すべきですか?
転職・出向・配置転換・M&A等の事情変更時には就労資格証明書交付申請が推奨されます。現行資格で適法かを先に確認でき、更新時の不確実性を下げるメリットがあります。社内監査や顧客説明の証跡にも有効です。
配置転換で現場作業比率が増える予定です。注意点はありますか?
知的・専門業務が主である必要があります。業務比率を定量化し、現業は補助的だと明記する必要があります。前後の職務記述書(JD)を比較して資料化してください。
雇用を終了した場合の会社側の手続きは?
中長期在留者の雇用終了届(ハローワーク/入管届出)を期限内に実施します。本人側も契約機関届出が必要です。
転職時に給与が下がると不利ですか?
転職による給与の低下が在留資格の許可・更新に不利益となる可能性があります。転職先の活動内容との関連性や企業が受入水準を満たしているかどうかが判断されます。日本人と同等待遇が原則のため、合理的説明(等級や地域差、試用期間の扱い)が必要です。最低でも生活維持できる水準を示し、賃金テーブルで根拠づけます。
在留期間・更新・出入国
在留期間はどのくらいですか?
5年・3年・1年(場合により6か月)のいずれかです。初回は1年で付与されることが多めですが、安定就労・納税・法令遵守が見えると長期が付与されやすくなります。
技人国ビザの更新申請はいつから可能ですか?
在留期間満了日の3か月前から更新申請が可能です。期限ギリギリでは不許可や再申請のリスクが高まるため、早めの準備をおすすめします。特に転職後の初めての更新は審査が厳しくなる傾向があります。
在留資格更新審査中に働けますか?また出国も可能ですか?
はい、従前の活動を継続可能です。また申請後は出国は可能ですが、審査中に入管から追加資料を求められたり連絡がある場合に連絡が取れる状態でないと審査に影響してしまうリスクがあります。出国するとしても、必要最小限の出国にとどめて頂くのが安全です。
出張で海外にいる間に在留期限が来ます。海外で更新申請できますか?
在外での更新は不可です。帰国→更新申請が原則です。どうしても必要な場合は早めに計画を見直してください。
更新時に審査が厳しくなることはありますか?
はい、特に以下の場合は更新審査が厳しくなります。
転職後の初めての更新
直近の納税記録や社会保険加入状況に不備がある場合
業務内容や勤務条件が大きく変わった場合
このため、更新前に就労条件や会社の経営状況を確認し、必要に応じて就労資格証明書の取得をおすすめします。
学生からの切替(留学ビザから技人国ビザへ変更)
留学生のアルバイトや就職内定時の注意は何ですか?
留学ビザの学生は在学中は資格外活動許可(週28時間、休暇中は学校規程)の範囲内でのみ可能です。内定→在留資格変更申請→入社の順で、フルタイム就労は在留資格変更許可後に開始となります。
大学を中退して就職したい場合は申請できますか?
大学を中退して「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは、基本的に困難ですが、中退前に母国で大学を卒業している場合や、中退した大学以外で日本の専門学校を卒業している場合は、取得の可能性があります。
家族帯同・身分関係
家族は帯同できますか?
配偶者・未成年の子は家族滞在で帯同可能です。生計要件・同居実態の資料(収入、住居、保険等)を用意します。
配偶者は働けますか?
家族滞在+資格外活動許可で週28時間以内の就労が可能です。
働き方・就業形態
国内で在宅勤務やフルリモートは可能ですか?
可能ですが、業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることと、受入機関が日本、労務管理が実効していることが条件です。テレワーク規程、勤怠・情報管理、評価運用を資料化してください。
海外クライアント向けの越境テレワークは海外からでもできますか?
「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」などの就労資格では、活動内容の要件として「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」活動であることが求められており、日本国内での居住と活動拠点であることが前提となっています。一時的な海外滞在ではなく、リモートワークを理由とした長期の日本離脱や海外に居住したままでは、在留資格の趣旨に反する可能性があり、慎重に検討する必要があります。
副業や兼業は可能ですか?
本務の在留資格範囲から逸脱しないことが前提となります。別法人の就労は原則不可で、資格外活動の検討が必要となります。就業規則も確認する必要があります。
パートタイム勤務でも技人国ビザは取得できますか?
技人国ビザは、基本的にフルタイムでの常勤雇用を前提としています。パートタイムやアルバイトでの雇用契約形態によっては認められない場合があります。週30時間未満の勤務や期間限定契約では、安定性や生計維持能力の観点から不許可となる可能性が高くなります。どうしても短時間勤務で申請する場合は、生活費の裏付け資料や雇用の必要性を十分に説明する必要があります。
フリーランスや個人事業主でも取得できますか?
技人国ビザは原則として雇用契約に基づく就労が対象です。フリーランスの場合、複数の企業との継続的な契約や安定した収入を証明できれば、例外的に許可されるケースもあります。ただし、契約書や業務委託内容、報酬の支払い証明など詳細な資料が必要です。
リスク対応・不許可リカバリー・違反
リスク対応・不許可リカバリー・違反
職務が現業中心、専攻との関連不明瞭、待遇が同等でない、社保未加入、契約の整合性崩れ(派遣・請負の線引き不明)などです。比率・数値・書面で立証できるようにする必要があります。
不許可になった場合、再申請は可能ですか?
可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが必要です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低くなります。JD再設計、待遇根拠の強化、体制図解、遵法証憑追加等を検討し、証拠資料や業務説明、契約条件の修正などを行ったうえで、再申請を検討します。
周辺資格との比較(高度/経営・管理/46号/技能)
高度専門職ビザとの違いは?
高度専門職ビザはポイント制の優遇(長期在留・家族帯同拡充・永住短縮等)。要件が満たせるなら高度の方がメリットは大きいです。職務自体は技人国と重なる領域が多いです。
経営・管理ビザとの違いは?
経営・管理ビザは経営そのものが活動となります。技人国は専門実務が主になります。役員でも実務が主なら技人国、ガバナンス・予算統括が主なら経営・管理です。
特定活動46号との違いは?
特定活動ビザ46号は日本語を中核とする顧客対応職を想定(販売・接客等を含みうる)。直接雇用・日本語上位レベルが前提です。職務設計でどちらが本質に近いかを選びます。
業務別(教育/通訳翻訳/営業・貿易/製造)
語学教師は技人国ですか?
民間語学学校等なら技人国が典型です。カリキュラム設計・教材開発・評価など知的業務を強調すると良いです。大学であれば在留資格「教授」、小学校、中学校、高等学校、専修学校の教員であれば「教育」、民間の英会話スクールであれば「技術・人文知識・国際業務」と別の在留資格になります。
通訳・翻訳は技人国の対象ですか?
対象です。専門領域(法務・医療・IT)や品質管理・用語集運用まで担う設計にし、成果物とKPIを提示してください。
営業・マーケ・貿易実務はどう説明すれば良いですか?
データ分析、企画書作成、価格戦略、契約・物流・通関調整など知的要素を中心になっている必要があっります。接客・現場作業がある場合は比率は低く保ち、比率を明示する必要があります。
製造現場の作業が一部あります。技人国の対象外ですか?
主が設計・工程改善・品質解析で、現場は確認・検証レベルなら技人国ビザの対象になり得ます。現場滞在は補助的であることを比率と業務例で明確にしてください。
申請実務(必要書類/オンライン申請等)
申請先はどこになりますか?
在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。
申請はオンラインでも可能ですか?
はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。
必要書類は何が必要ですか?
ビザの種類によって必要書類は異なります。「技術・人文知識・国際業務」の場合は、雇用契約書、会社の概要資料、職務内容説明書、学歴や職歴を証明する書類(卒業証明書・職務経歴書)などが必要です。日本語以外の書類は必ず翻訳文を添付します。当事務所では、ヒアリングを行い、お客様の状況に合わせた必要書類リストを作成します
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。