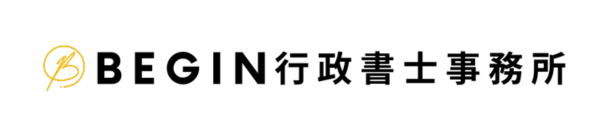「ビザとは何か?」を正しく掴む
はじめての申請でつまずきやすいのは、用語の誤解と段取りの抜け漏れです。本稿では「ビザとは何か」「在留資格・在留カードとの違い」を土台に、ビザ申請の全体像、不許可の典型要因、申請代行の使いどころまでを、初めての方でも迷わず進められる順番で整理します。読みながらご自身や自社の状況に当てはめてお使いください。
ビザとは?——入国のための“推薦状”、在留資格の通称
日常会話やニュース、多くのWEBサイトなどでビザという言葉が2つの意味で使われています。
1つは、査証(ビザ/VISA)で日本に入国する際に必要となる「入国のための推薦状」です。在外公館(日本大使館や領事館)で発行され、入国審査の際に「この人は日本に入国しても問題ありません」と証明する役割を持っています。ただし、最終的な上陸可否は空港の入国審査官が判断します。査証(ビザ/VISA)があるだけでは日本に滞在できるわけではなく、入国時に空港などで上陸審査を受け、在留資格が認められて初めて日本での活動が可能となります。
2つ目は、日本で何をしてよいか、どのくらい滞在できるかを決める在留資格そのものを通称でビザと呼んでいます。例えば、在留資格「日本人の配偶者等」のことを配偶者ビザや結婚ビザ、就労系の在留資格のことを就労ビザ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」であれば技術・人文知識・国際業務ビザや技人国ビザという具合に通称で呼んでいます。
在留資格とは、外国人が日本でどのような活動(就労・留学・家族滞在など)を行うか、その活動内容に応じて法務大臣が与える「資格」を意味します。「日本人の配偶者等」「技術・人文知識・国際業務」「経営管理」「留学」「家族滞在」など、活動内容ごとに細かく分類されています。
そして、在留カードは、日本に中長期間(3か月を超えて)滞在する外国人に交付される「身分証明書」です。
在留カードには氏名、生年月日、在留資格、在留期間などの情報が記載されており、日本国内での身分証明や、就労・住居手続きなど様々な場面で必要となります。
まずは三つの役割分担を押さえましょう。
- 査証(ビザ/VISA):在外公館が発給する入国のための「推薦状」です。
- 在留資格(通称ビザ):日本での活動内容(就労・留学・家族など)に応じて法務大臣が与える「資格」です。
- 在留カード:在留資格・期間・就労可否等を記載するICカード「身分証明書」です。
主要なビザ/在留資格のカテゴリー
どの在留資格に当てはまるかは、日本で実際に行う活動と要件(学歴・職歴・雇用契約など)で決まります。
まずは大きな地図を確認し、必要に応じて個別の詳しいビザ申請サービス紹介ページへお進みください。
- 就労系:技術・人文知識・国際業務(技人国)/高度専門職/経営・管理/技能/企業内転勤 など
- 身分・家族系:日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/家族滞在 など
- 学業・研修系・その他:留学/研修/特定活動(インターン等の類型あり)
- 長期定住系:定住者/永住者 など

ビザ申請の全体像——流れ・期間・費用の目安
ビザ申請は「要件を固める → 証拠を集める → 審査に出す」の三段階で進みます。在留資格は入国管理局(入管)の判断による審査が行われ、申請すれば自動的に認められるものではなく、申請側が書面で立証する必要があります。繁忙期や追加資料の要求でスケジュールが延びることもありますので、前工程の詰めが成功率と所要期間を左右します。以下は就労ケースの在留資格認定証明書(COE)申請の標準フローです。
要件整理と在留資格の選定
在留資格の選定での判断ミスは、その後のやり直しに直結します。就労系ビザであればどの在留資格に該当するかの判断を行い、活動内容・雇用契約・学歴/職歴の関連、受入企業の体制(信用力・カテゴリー)を言語化し、選定根拠を用意しておきましょう。
- 職務内容(Job Description)がどの在留資格の想定業務に合うかを対応付けます。
- 学位・専攻・職歴と職務の合理的関連性を、成績・職務証明・研修計画などの証拠で補強します。
- 企業側の所属機関カテゴリー(1〜4)や就労環境の整備状況を確認します。
書類収集・作成
審査は提出書類で判断されます。書類は“語る証拠”です。何が必要かを冒頭で洗い出し、逆算スケジュールを組みましょう。
- 申請人:旅券、写真、学位証明、職歴証明、語学・資格、履歴書 など。
- 企業:雇用契約、職務記述書(JD)、登記事項証明、直近決算、会社案内、法定調書合計表 など。
- 用語・数字・肩書の完全一致(英日翻訳を含む)を徹底します。
在留資格認定証明書(COE)の申請(日本側)
海外から外国人を呼び寄せるケースでは受入機関や代理人が入管に申請します。実体性(事業の実在・雇用の現実性)と整合性(書類間の矛盾のなさ)が主要論点になります。
- 審査期間の目安:就労系で1〜3か月程度です(時期・案件難度で変動します)。
- 追加資料の要求を想定し、回答パッケージ(補足説明書+証拠)を事前に準備しておくと安心です.
ビザ申請(海外の日本公館)
COEを基に、各国の日本大使館・総領事館で査証申請を行います。必要書類と所要日数は公館ごとに違いがありますので、事前確認をおすすめします。
- 審査目安:数日〜2週間程度が一般的です。
- 書類不備やCOEの有効期限切れにはご注意ください。
入国・上陸許可・在留カード受領
空港で上陸審査を経て在留カードが交付されます。入国後は住民登録・年金・健康保険・税務などの初期手続きを時系列で進めるとスムーズです。
- 就業開始日と社会保険手続の整合を担保してください。
- 家族帯同がある場合は、学校や住宅の手配も前倒しで進めると安心です。
よくある不許可の典型要因
不許可は要件不足だけでなく、説明不足や資料の矛盾からも生じます。典型例を先に把握しておくと、準備段階で対策しやすくなります。
- 在留資格の取り違え:実務が単純作業寄り、または専門性説明が弱いケースです。
- 企業側資料の弱さ:企業カテゴリー3やカテゴリー4で事業の実態の裏付けが薄い、赤字が続くなどです。
- 書類の不整合:契約・JD・履歴書・求人票の数字や役割が一致していないケースです。
- 翻訳ミス:肩書・資格・日付の誤訳は致命的です。
- スケジュール遅延:更新期限間際で、追加資料に即応できないケースです。
ビザ申請を自力で本人が行う?それともビザ申請代行を使う?
ビザ申請の成否を分けるのは、適切な在留資格の当てはめと証拠の設計、そして書類間の一貫性です。
本人申請が向くケースとしては、要件が明快で、要件を読み解け、時間的余裕がある場合は自走しやすいです(単純な更新、資料が十分揃っている場合など)。諸法令、入管の公開要領を読み、ご自身で整合性チェックができることが前提になります。
自力で十分な案件もありますが、入管法、省令、施行規則、ガイドラインなどの最新情報を正確に把握していく時間を取ることはハードルが高い面もあります。また、入管が公表している令和6年の在留資格認定証明書(COE)の申請は許可率は92%となっており、8%程度は不許可という統計データがあります。
ビザ申請では個別状況に応じて用意する書類をアレンジして証明していくことを申請者側が行う必要があるため、時間的余裕がない方、本人申請では不安な方、難易度が高いとお考えの方などは専門家のビザ申請代行の活用が合理的です。
申請取次行政書士とは?
入管への申請を申請人本人が出頭せずに進められる制度が「申請取次制度」です。申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。申請取次行政書士に委任すると、地方出入国在留管理局への提出・受領等の手続を任せることができます。
- 資格要件と届出
- 行政書士が法務省が定めた専門研修を修了し、所定の効果測定に合格したうえで、入管へ申請取次の届出を行うことで取次が可能になります。
- 事務所名と取次者番号が付与され、依頼者との委任契約にもとづき申請手続を行います。
- 取次できる主な手続
- 在留資格認定証明書交付申請(COE)
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 資格外活動許可申請、就労資格証明書交付申請、在留資格取得許可申請 など
※ 事案により本人の同席・出頭を求められることがあります。
- メリット
- 本人の出頭免除(原則)により、業務や学業の中断を最小化できます。
- 書類の整合性設計と追加照会への即応で、手戻りを抑制できます。
- 入管窓口とのやり取りを一本化できます。
- 注意点
- 最終判断は入管であり、結果の100%保証はできません(様々なケースを把握しているため不許可リスクを軽減できます)。
- 虚偽申請の依頼には応じられません(守秘義務・職業倫理があります)。
- 出頭指示があれば本人が出頭する必要があります(同席の要否は事案次第です)。
BEGIN行政書士事務所 ビザ申請代行サービス
BEGIN行政書士事務所は東京都立川市の行政書士事務所です。オンライン相談・オンライン申請に対応しておりますので、全国対応しています。
申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。
在留資格・ビザ申請でお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
当事務所の提供サービス
✅初回のご相談は無料です。状況を丁寧にヒアリングした上で、プランのご提案とお見積りをご提示します。
✅全国対応・オンライン申請対応:オンライン面談と郵送手続きにより、全国どの都道府県からでもご依頼が可能です。遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけます。
✅申請取次行政書士が一貫して対応:当事務所は「申請取次行政書士」として、初回の無料相談から書類作成・入管への申請まで一貫して対応いたします。すべてを専門家に一任できる安心感を提供します。
✅審査傾向を踏まえた戦略的サポート:当事務所では、個別状況をふまえてどのように説明を補強するべきかを検討し、審査官が重視する観点を踏まえた構成で書類を整え、理由書を含めた申請書類を作成します。不許可リスクを下げ、許可に近づけるための「戦略的な書類作成」を重視しています。
✅お客様の状況に応じて難易度も確認:明朗な料金体系で内容と見積り金額をしっかりご案内いたします。後から事前合意していない請求をすることはございませんのでご安心ください。
✅不許可の場合は、全額返金保証制度:万が一、不許可となった場合には、追加料金無しでの再申請または全額返金する制度があります。安心してご依頼いただける制度を整えております(返金規定・プランによりますので初回の無料相談でご説明します)。