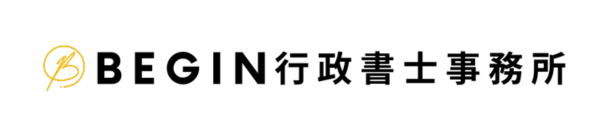はじめに
外国人が日本で会社を設立して経営を行う、あるいは既存の会社に参画して経営管理に携わる場合に必要となるのが「経営・管理ビザ」です。日本市場の魅力やアジア拠点としての立地条件から、多くの外国人起業家や経営者が関心を寄せています。
しかし一方で、経営・管理ビザは資本金要件や事務所の実態性、事業計画の現実性など、細かい基準を一つでも満たさないと不許可となる可能性が高いのです。単に会社を登記しただけでは認められず、オフィスの確保、資本金3,000万円以上の投資、1人以上の常勤職員を雇用、そして実現可能な事業計画が揃って初めて許可が下りるという厳しい性質を持ちます。
加えて、2025年10月には、在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正がされ、審査が厳格化していくこととなりました。そのため、これから経営・管理ビザを目指す方は、最新の情報にあわせて準備することが不可欠です。
本記事では、経営・管理ビザの基本から要件、会社設立の流れ、必要書類、審査の観点、不許可回避の方法までを体系的に行政書士の視点で徹底的に解説します。
経営・管理ビザとは
まずは経営・管理ビザの概要を理解しましょう。このビザは、日本で会社を設立し、経営者や管理者として活動する外国人に与えられる在留資格です。2015年の法改正以前は「投資・経営」と呼ばれ、出資そのものに重点が置かれていました。しかし改正後は、投資額に関係なく「経営」や「管理」の実務に関与していることがより重要視されるようになりました。
経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)は、外国人が日本で次のような活動を行うために必要となる在留資格です。
- 経営:会社を設立して事業を自ら運営すること
- 管理:経営者に代わって事業を統括・管理すること
具体的には、飲食店の開業、IT企業の設立、貿易会社の運営などが対象となります。また、日本の既存企業に投資して経営に参加する場合や、投資家に代わって管理者として会社運営を担う場合も該当します。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「経営・管理」 | 出入国在留管理庁
他の就労ビザとの違い
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:会社に雇用され、専門的知識をもって働く場合に必要。
- 高度専門職ビザ:高度な学歴・年収・研究実績などをポイントで評価される優遇ビザ。
- 経営・管理ビザ:雇用されるのではなく、自らが「会社の経営者・管理者」となる場合に必要。
つまり、他の就労ビザが「雇用される立場」を前提としているのに対し、経営・管理ビザは「自らが経営する立場」に立つことが大きな特徴です。
これらのケースに共通しているのは「経営実態が存在すること」です。名義だけの役員や出資のみの立場では許可されず、実際に経営や管理の意思決定に関わる必要があります。
経営・管理ビザで認められる3つの活動パターン
経営・管理ビザでは、次の3つの活動パターンが認められています。
① 日本で新規事業を立ち上げ、経営を行う場合
第一に「新規事業の開始」です。たとえば外国人が日本で株式会社や合同会社を設立し、自ら代表取締役や代表社員として事業を経営するケースです。これは最も典型的な申請パターンであり、資本金3000万円以上の投下や、1人以上の常勤職員を雇用を伴う事業計画が前提となります。
例:外国人が日本で株式会社を設立し、飲食店や貿易会社を運営するケース。
② 日本の会社に投資し、経営に参加する場合
第二に「既存事業への参画」です。すでに日本で活動している会社に出資し、その経営に参加する形です。この場合は、単なる出資ではなく、取締役や執行役員などの経営ポジションに就任し、経営判断に関与することが必要です。
例:既存の日本法人に資本金を出資し、取締役に就任して経営に参画するケース。
③ 投資者に代わって経営管理を行う場合
第三に「経営の代行」です。たとえば外国人投資家が海外に居住しており、日本で事業を行うにあたり、別の外国人が管理者として派遣される場合などがこれに該当します。このケースでは、派遣される管理者が経営経験を持ち、一定の報酬を受けることが条件になります。
例:外国人投資家に代わり、経営経験をもつ別の外国人が会社の管理業務を担うケース。
経営・管理ビザの取得要件(全体像)
経営・管理ビザを取得するには、単に会社を設立すればよいわけではありません。入管は厳格に審査を行い、「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」「相当性」の3つの観点から総合的に判断します。
在留資格該当性
ここからは、経営・管理ビザの審査で必ず確認される「要件」の一つ一つを掘り下げていきましょう。まずは「在留資格該当性」です。
まず、その活動が「経営・管理」に当たるかどうかが判断されます。経営者として会社を運営する、または管理者として事業を統括する活動でなければなりません。単に出資するだけで経営に関与しない株主は該当しません。在留資格該当性とは、申請者が行おうとしている活動が入管法で定められた「経営・管理」の範囲に当てはまるかどうかを審査する基準です。具体的には次のような条件が確認されます。
- 会社を自ら設立し、その代表者や役員として経営に関与すること
- 日本の会社に投資し、取締役などの立場で経営に参画すること
- 投資家に代わって管理者として経営を担うこと
重要なのは「実際に経営・管理に携わっているかどうか」です。単なる名義上の役員や、株主として出資しているだけでは該当しません。つまり、「意思決定権を持ち、経営上のリスクを負い、組織を統括する立場にあること」が必要です。
たとえば「支店長」や「工場長」のように、経営者から委任されて事業を管理する立場も対象に含まれます。ただしその場合は、管理業務の実績や経験を裏付ける資料(職務経歴証明など)が求められます。
上陸許可基準適合性
次に審査されるのが「上陸許可基準適合性」です。これは、経営・管理ビザを持つにふさわしい事業所の実態や事業規模が適正であるかを確認する基準であり、非常に重要です。具体的には以下の条件があります。
- 日本国内に事業所を確保していること
日本国内に実態のあるオフィスを用意する必要があります。自宅兼用の住所では基本的に認められません。シェアオフィスやバーチャルオフィスも原則不可で、固定的な事務所を契約する必要があります。 - 事業規模が一定以上であること
次の両方を満たす必要があります。
- 1人以上の常勤職員を雇用していること(日本人、特別永住者及び法別表第二の在留資格、いわゆる身分系在留資格をもって在留する外国人(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)に限る)
- 資本金の額または出資の総額が3,000万円以上であること
- 経営者又は常勤職員のいずれかの日本語能力
経営者又は常勤職員があることを証明する必要があります。 - 経営者の経験要件
経営者が事業の業務に必要な学歴または過去に3年以上の経営・管理経験があることを証明する必要があります。 - 管理者の経験要件
申請人が「経営」ではなく「管理」を行う場合には、過去に3年以上の経営・管理経験があることを証明する必要があります。 - 報酬要件
管理者として活動する場合、日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。
これらの基準は形式的に満たせばよいというものではなく、実態が伴っていることを入管が厳しくチェックします。たとえば、資本金3,000万円を口座に入金した直後にすぐ引き出してしまうようなケースでは、不自然な資金運用として審査に悪影響を与えます。また、従業員の雇用についても実際の雇用契約書や給与明細などで裏付けが必要です。
相当性
最後に、経営管理ビザにおける「相当性」とは、申請が「在留資格に該当する」という要件に加えて、日本に継続的に在留するに足る「適当と認めるに足りる相当の理由」があるかどうかという入管法上の審査基準のことです。申請者の過去の在留状況や事業の安定性・継続性などが求められます。
事業計画書の重要性
経営・管理ビザの申請において、最も重視される資料のひとつが「事業計画書」です。単に会社を設立し、資本金を払い込んだだけでは入管は納得しません。この会社が日本で安定的かつ継続的に事業を運営できるのかどうかを客観的に示すための根拠が、事業計画書だからです。
事業計画書には、以下のような観点が求められます。
- 事業の目的やビジョンが明確であること
- 提供する商品・サービスの内容が具体的であること
- 市場分析(競合他社・ターゲット層・需要予測)が行われていること
- 収益計画や資金計画(資本金の使途、運転資金、収益モデル)が現実的であること
- 将来の雇用計画が描かれていること
たとえば飲食店であれば、店舗の立地条件や周辺の競合店、ターゲット顧客の層、メニュー構成、原価率、売上予測などを数字で示さなければなりません。IT企業であれば、サービスの差別化ポイントや契約予定先、システム開発のスケジュールなどが必要になります。
事業計画書は一般的にはA4で10ページ程度で作成します。ここで注意すべきは、事業計画書は単なる「作文」ではないということです。入管は計画が実際に実行可能かどうかを厳しく見ます。そのため、契約書の写し、見積書、予約済みのオフィスの賃貸契約など、計画の裏付け資料を添付することが不可欠です。

経営管理ビザ申請では、事業計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかの事業計画書の確認書が必須となります。
事業計画書の作成ポイント
それでは、事業計画書を作成する際の具体的なポイントを見ていきましょう。単なる形式的な計画ではなく、審査官を納得させる「実効性ある計画」にすることが重要です。
事業目的とビジョンを明確にする
最初に必要なのは、事業の目的を端的に示すことです。「何を目指して日本で事業を行うのか」を明確に書くことで、計画全体の説得力が増します。単に「日本で飲食店を開きたい」では弱く、「地域住民向けに健康志向のベトナム料理を提供し、外国人観光客の需要も取り込む」と具体的に示す必要があります。
市場分析を具体的に行う
次に重要なのが「市場分析」です。競合他社の状況、ターゲット顧客層、業界全体のトレンドを調査し、自社がその中でどのようにポジションを取るのかを明示します。数字や統計資料を用いることで信頼性が増します。その上で事業の特徴、提供する商品・サービス内容、どのように集客・顧客獲得していくかを整理します。
収益計画を現実的に立てる
売上高、費用、利益の予測を最低1年、できれば3年分程度示すことが一般的です。この際、根拠のない売上見込みは逆効果となります。契約済みの顧客や仕入れ先との合意書を添付すると、数字の裏付けとして効果的です。
資金計画を明示する
資本金をどのように使うのか、具体的に示すことが大切です。内訳としては「オフィス賃料」「人件費」「設備投資」「広告費」「運転資金」などを記載します。
採用計画を盛り込む
入管は「雇用創出」を重視します。したがって、将来どのタイミングで何名の従業員を雇うのかを明記しましょう。雇用契約予定者がいれば、その履歴書や意向確認書を添付するのも有効です。
裏付け資料を添付する
事業計画書だけではなく、実際に動いている証拠を提出することが肝心です。たとえば「店舗の賃貸借契約書」「仕入れ先との見積書」「顧客からの予約確認書」などです。これにより計画が単なる空想ではなく、実際に実行されていることを示せます。
これらを整理し、事業概要、ビジョン、会社・事業の特徴、提供する商品・サービス内容、集客・顧客獲得方法、取引先・販売先、収益計画、資金計画、従業員の採用計画等を事業計画書としてまとめていきます。
経営・管理ビザ取得の流れ
経営・管理ビザの取得には、会社設立のプロセスと、その後の在留資格申請が密接に関わっています。特に株式会社を設立して申請するケースが多く見られますが、合同会社の場合は一部手続が簡略化される点があります。
会社設立からビザ申請までの通常の流れ
経営・管理ビザを取得するための基本的なステップは次のとおりです。株式会社を基本形として説明し、合同会社の相違点は〔合同会社:〜〕の形で補足します。
① 会社の基本事項を決定
商号(会社名)、本店所在地、事業目的、資本金額、役員構成を決定します。事業目的は入管が厳しくチェックするため、ビザ要件や必要な許認可との整合性を必ず確認する必要があります。
〔合同会社:同様に必要。ただし役職名は「代表社員」となる〕
② 定款の作成
会社の基本ルールを定める定款を作成します。株式会社では公証役場での認証が必須です。
〔合同会社:定款作成は必要ですが、公証役場での認証は不要〕
③ 定款認証(株式会社のみ)
作成した定款を公証役場で認証します。手数料は約5万円、発起人の印鑑証明書や本人確認資料が必要です。
〔合同会社:この工程は不要〕
④ 資本金の払い込み
発起人の個人口座に資本金を振り込みます。経営・管理ビザ申請には3,000万円以上が必要です。振込明細や通帳コピーを証拠として残します。
⑤ 法人設立登記
法務局で登記を行い、会社を設立します。登記事項証明書と印鑑証明書を取得し、会社の法的存在を確立させます。
⑥ 各所への届出
税務署や都道府県税事務所、社会保険関連の届出を行います。従業員を雇用する場合は労働保険・雇用保険の手続きも必要です。
※営業許可が必要な業種の場合は、経営管理ビザ申請前に許認可の取得を済ませる必要があります(例:飲食業、建設業、不動産業など)。
⑦ 経営・管理ビザの申請
上記の準備を完了させたうえで、入管に在留資格認定証明書の交付申請を行います。会社の実態、資本金、事務所、事業計画を総合的に審査されます。
4か月の経営・管理ビザビザについて
経営管理ビザ申請以前に、会社設立手続き、事務所や店舗の賃借、法人開設届等の税務手続き等、許認可が必要な業種の場合には許認可取得、会社名義の銀行口座の開設手続き、各種保険手続き等を日本語で行う必要があり、日本に協力者がいないと事業の準備が非常に難航します。日本在住の方に協力者になってもらい申請する方法が一般的です。
日本に協力者がいない場合には「4か月の経営・管理ビザ」を活用して入国・準備を進める方法も存在します。このビザは、会社設立や事業開始の準備を目的として日本に滞在できますが、在留期間は4か月のみで延長不可のため慎重な計画が不可欠です。
経営・管理ビザの審査で重視されるポイント
経営・管理ビザの審査は、単なる会社設立登記の有無を確認するものではありません。入管は「この事業が日本で本当に継続できるのか」「申請者が責任を持って経営を担えるのか」を多角的に検証します。したがって、資本金や事務所の有無だけではなく、事業計画の現実性、過去の在留状況、素行、そして受入体制まで含めた総合判断が行われます。ここでは、特に審査官が重視する5つの観点を解説します。
事業所の実態性
経営・管理ビザでは「事業所の確保」が必須です。レンタルオフィスは個室で、電話・机・常駐スタッフなどの実態が確認できなければ不許可となります。
資本金・事業規模
従来は資本金3,000万円以上もしくは、従業員1名以上の常勤雇用が必要です。事業規模の裏付けとして、雇用契約書等が必要です。
事業計画の現実性
入管は、単に「売上予想」を見るのではなく、それが市場調査や過去の経験に基づいているかを確認します。
- 誰に(ターゲット顧客)
- 何を(商品・サービス内容)
- どのように(販売ルート)
- どれくらいの規模で(売上・利益予測)
といった要素を、論理的かつ数値で示さなければなりません。
経営者・管理者の適格性
「3年以上の経営管理経験」が求められます。また、管理者は日本人と同等以上の報酬を受けられる契約でなければ認められません。
素行・在留履歴の適正性
過去にオーバーステイや資格外活動違反がある場合は大きなマイナス要素になります。さらに、税金の滞納や社会保険未加入も不適格と判断されやすいため、事前に解消してから申請することが重要です。
経営・管理ビザの不許可になりやすい典型ケース
経営・管理ビザの不許可率は、他の就労系ビザに比べて高い水準にあり、要件も厳格化されています。その理由は「形式的な会社設立」だけで申請するケースが多く、入管が求める事業実態を裏付ける証拠が不足しているからです。ここでは、実務で頻発する不許可の典型例を整理します。
資本金不足や証明不備
- 3000万円に満たない資本金で申請
- 資本金はあるが、送金経路が不明瞭(海外親族から現金持参など)
- 通帳コピーが不完全で、入金の証明にならない
資本金要件は「金額」だけでなく「出所の透明性」も重視されます。
事務所の要件を満たさない
- バーチャルオフィスのみで、実際の事業スペースが存在しない
- レンタルオフィスを借りたが、机・備品が整っていない
- 自宅兼事務所で、生活スペースと区別できていない
入管は「事業所の写真」や「賃貸借契約書」で実態を確認するため、誤魔化しは通用しません。
非現実的な事業計画
- 初年度から数千万円の売上を見込んでいるが、顧客や契約の裏付けがない
- 業界知識が不足しているのに高度な事業を掲げている
- 経費計算に大きな矛盾がある
事業計画の数字が空論と判断されると、不許可に直結します。
経歴や素行に問題がある
- 経営経験が虚偽、職務経歴証明が不正確
- 過去にオーバーステイ歴がある
- 納税や社会保険の未加入
入管は申請者の「信用性」を重視するため、経歴や素行に疑念があれば不許可になります。
書類の不備・矛盾
- 登記簿と事業計画書で会社所在地が異なる
- 資本金額が通帳と理由書で一致しない
- 添付資料の不足や署名漏れ
書類の不整合は「信用できない」とみなされ、即座に不許可の理由となり得ます。
不許可を回避するためのポイント
経営・管理ビザの審査は「疑わしきは不許可」という姿勢で運用されています。したがって、不許可を避けるためには「疑念を持たれないこと」「疑念を持たれても証拠で打ち消せること」が必要です。ここでは、実務上有効な回避ポイントを詳しく解説します。
書類の一貫性を徹底する
会社登記簿、資本金払込証明、事務所契約、事業計画など、すべての資料に矛盾があってはなりません。例えば資本金額が通帳コピーと理由書で異なれば、それだけで不許可になります。
事業計画を「数字」で補強する
事業計画は最重要資料です。売上・経費・利益の予測を市場調査の数値で裏付け、取引先候補や契約書の写しを添付することで「実現可能性」を証明できます。
過去の在留履歴や素行を説明する
オーバーステイや納税滞納がある場合でも、改善証明(納税証明書・反省文)を提出することで信頼回復の余地があります。黙っているよりも、正直に説明したほうが評価されます。
専門家のサポートを活用する
行政書士は、過去の不許可事例や最新の入管実務を把握しています。自己申請では気付けない矛盾や不足を事前に補強できるため、依頼することで許可率は大幅に上がります。
経営・管理ビザの更新手続き
経営・管理ビザは初回で1年が付与されるのが一般的です。その後、更新を繰り返すことで3年、5年と長期在留資格へとつなげることができます。しかし、更新審査では「設立時の形式要件」だけでなく「事業の実績と継続性」が問われるため、初回許可以上に厳しいチェックが入る場合があります。ここでは更新の流れと審査で見られる観点を整理します。
更新手続きの流れ
- 在留期限の 3か月前から申請可能。
- 管轄の入管局に「在留期間更新許可申請書」を提出。
- 必要書類は決算書、確定申告書、納税証明、従業員の給与台帳、社会保険加入証明など。
- 通常1〜3か月で審査結果が出る。
更新時の審査基準
- 事業の継続性:売上や取引先が実際に存在するか。
- 事業の活動実態:業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱われます。在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。
- 雇用の実態:従業員を雇用しているか、給与が支払われているか。
- 納税・社会保険状況:未納がないか。在留期間更新時には、納税・社会保険等の支払義務の履行状況が確認されます。
- 生活基盤の安定:経営者自身の生活費を賄える収入があるか。
更新が認められやすいケース
- 黒字経営で売上が安定している場合
- 社会保険や税金をきちんと納めている場合
- 複数年契約の顧客や継続取引先がある場合
赤字決算でも更新できる?
経営・管理ビザの更新で最も不安視されるのが「赤字決算」の場合です。結論から言えば、赤字だからといって必ず不許可になるわけではありません。入管は「一時的な赤字か」「将来の改善見込みがあるか」を総合的に判断します。
不許可になる赤字ケース
- 設立以来、売上ゼロが続いている
- 赤字が3期以上連続し、改善の兆しがない
- 従業員を雇用せず、社会保険も未加入
- 経営者自身が生活費を賄えない
許可される可能性のある赤字ケース
- 開業初年度で投資負担が大きく、赤字は一時的なもの
- 新規事業立ち上げで時間がかかっているが、契約や顧客が増えている
- 研究開発型のビジネスで、投資先行が合理的に説明できる
赤字をカバーするための証拠資料
- 将来の売上予測を示す事業計画書の更新版
- 実際の顧客契約書や注文書
- 投資回収計画や資金繰り表
- 銀行残高証明や資金援助契約
共同経営の場合の注意点
外国人2名以上で共同経営するケースや、日本人と外国人がパートナーを組むケースも増えています。しかし、共同経営は「責任分担が不明確」「経営実態が見えにくい」として、入管から厳しく審査されやすい傾向があります。ここでは共同経営に特有の注意点を整理します。
出資比率の明確化
共同経営では、各人の出資比率が不透明だと「名義貸し」と疑われます。株主名簿や出資証明を提出し、資本金の出所を明確に示すことが必須です。
経営責任の範囲
複数の外国人が取締役に就任する場合、それぞれが「経営に実質的に関与」している必要があります。単なる名義上の役員では認められません。議事録や職務分担表を用意して説明することが効果的です。
代表権の所在
共同経営でも、誰が代表取締役として責任を負うのかを明確にしなければなりません。代表権を持たない場合でも、日常の経営判断にどのように関与するのかを説明する必要があります。
日本人との共同経営
日本人と外国人が共同で会社を設立する場合、日本人側に経営経験や信用があると審査にプラスになります。その場合でも、外国人側が「経営実務を担っている」ことを必ず立証しなければなりません。
経営・管理ビザから永住権へのルート
経営・管理ビザを取得した方の多くは、将来的に「永住権(永住許可)」の取得を目指します。永住権が認められると、在留期間の更新が不要となり、安定的に日本で生活・事業を続けることが可能になります。ただし、経営・管理ビザから永住へ直結するのは簡単ではなく、収入・納税・事業継続性といった複数の条件を満たす必要があります。
永住許可の基本条件
- 原則として 10年以上の在留歴(ただし経営管理ビザの場合、活動実績や収入水準によって短縮の可能性あり)
- 安定した収入(事業の黒字化、役員報酬の支給、家族を養える程度の年収)
- 納税・社会保険の適正な履行(滞納や未加入があると致命的)
- 素行善良(交通違反や資格外活動の違反歴がないこと)
経営者に特有の審査ポイント
- 会社の健全性:赤字が続いていないか、債務超過に陥っていないか。
- 雇用実績:日本人や永住者などの常勤職員1名以上。
- 役員報酬の安定性:毎年継続的に役員報酬を得ていることが重要。
行政書士に依頼するメリット
経営・管理ビザは、数あるビザの中でも特に申請難易度が高いといわれています。会社設立の段階から法務・税務・入管の要素が複雑に絡むため、自己申請では不許可になるリスクが高いのです。ここでは行政書士に依頼するメリットを整理します。
要件の整理と適合性の判断
行政書士は「在留資格該当性」「上陸許可基準適合性」「相当性」を条文レベルでチェックし、申請が成立するかを事前に確認します。これにより「出す前から不許可確定」という無駄を防ぐことができます。
書類作成の精度向上
入管の審査は「書類審査」が基本です。理由書、事業計画書、経歴証明などは、単なる形式ではなく「説得力あるストーリー」としてまとめなければなりません。専門家が関与することで、整合性のとれた申請書類を作成できます。
不許可リスクへの対応策
過去の事例から、不許可になりやすいパターンを熟知しているため、事前に補強資料を追加することが可能です。特に赤字決算や共同経営など難易度の高いケースでは、専門家の戦略が結果を大きく左右します。
ワンストップ支援
会社設立登記、定款認証、資本金の払い込み、税務署への届出、そしてビザ申請まで一気通貫でサポートできるのは、行政書士事務所の強みです。依頼者は本業に集中でき、法的な不備を防ぎながらスムーズに手続きを進められます。
行政書士に依頼することで、単に「書類作成を代行する」だけでなく、「不許可リスクを下げるための戦略立案」が可能になります。安心して経営活動をスタートさせたい方にとって、専門家の関与は大きな価値があります。
まとめ
経営・管理ビザは、日本で起業や経営を行う外国人にとって欠かせない在留資格です。しかしその審査は極めて厳格であり、単なる形式的な会社設立では許可が下りず、入念な準備と専門的な知識が不可欠です。
在留資格該当性・上陸許可基準適合性・相当性の3要件をすべて満たし、事業計画や資本金、オフィス、雇用計画を実体として整えることが必須です。また、2025年10月より資本金要件の引き上げ(3000万円)となり、審査は厳しくなる見込みです。
更新や永住権取得を視野に入れる場合は、事業の安定性・継続性を数値と証拠で示すことが不可欠です。特に赤字決算や共同経営のケースでは、不許可リスクを事前に想定し、対策を講じることが大切です。
当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、会社設立から経営管理ビザの書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。
👉 経営管理ビザでお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。