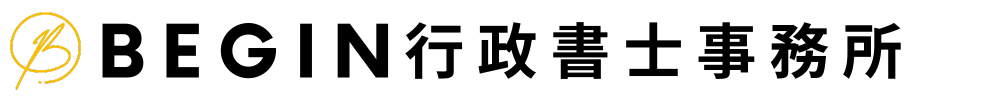Q&A
文化活動ビザに関するよくある質問
文化活動ビザで認められる具体的な活動例は何ですか?
茶道・華道・書道・日本舞踊・能楽・歌舞伎・和楽器・武道(剣道・合気道など)の修得、民俗芸能や伝統工芸の研究、大学等での“無報酬の”研究員(客員・研修的ポジション)としての学術研究などが典型です。いずれも非営利・無報酬が大前提で、受入機関や指導者の受入承諾と活動計画の妥当性が重視されます。
在留中に報酬を得ても良いですか?
対価性のある謝金や出演料・指導料・販売代金など報酬を得る活動は不可です。一方、交通費や材料費などの実費弁償、審査を経る奨学金・助成金は趣旨上許容されることがあります。金銭の名目や支払根拠が不明確だと就労性と判断されるおそれがあるため、明細・根拠資料の整備が重要です。また継続的な収入を得る活動は別在留資格で検討が必要です。副収入が必要なら資格外活動許可の可否を個別検討します。
海外からの印税・広告収益(YouTube等)を受け取っても問題ありませんか?
“日本で行う活動の対価”に当たるとみなされる場合は不可です。過去の作品に対する海外源泉の既存印税など、日本での活動と結びつかない収入は例外的に説明可能なこともありますが、課税関係・実態の整理と理由書による明確化が必須です。曖昧な運用は避けてください。
作品を販売しても良いですか?
販売や受託制作など対価を得る創作は文化活動の範囲外で、原則「芸術」の在留資格での検討対象になります。
ボランティア活動は可能ですか?
純粋な無償奉仕で、受入側の営利活動に実質的に寄与しない範囲なら可能です。ただし“無給インターン”であっても売上に貢献する作業やシフト勤務のような実態は就労性が高く不適です。活動内容・頻度・受入体制を活動計画書で明確にしてください。
留学との違いは何ですか?
学位取得・授業履修が主目的なら留学の在留資格となります。文化活動は無報酬の修得・研究に特化した活動になります。
受入機関がない個人でも申請できますか?
理論上は可能ですが、受入承諾書・指導計画・設備が整う案件に比べ立証のハードルが高いです。個人申請では、誰から・どこで・どの頻度で指導を受けるか、発表機会や学習方法、自己管理の仕組みまで詳細に示す必要があります。
活動計画書はどの程度具体的に書くべきですか?
期間・場所・指導者、週あたりの時間割、使用施設、年間の目標と評価指標(例:段位・免状の取得、論考の発表、作品の発表会等)、必要経費と資金計画(貯蓄・奨学金・経費支弁者)を時系列で記載します。曖昧だと補正や不許可のリスクが高まります。
期間・場所・指導者、週あたりの時間割、使用施設、年間の目標と評価指標(例:段位・免状の取得、論考の発表、作品の発表会等)、必要経費と資金計画(貯蓄・奨学金・経費支弁者)を時系列で記載します。曖昧だと補正や不許可のリスクが高まります。
法定の一律基準はありません。ただし、家賃・生活費・学習費をカバーできる6〜12か月分程度の資金を内訳付きで示すのが実務上の目安です。経費支弁者(スポンサー)が支援する場合は、支弁誓約書・収入証明の提出が有効です。
“経費支弁者(スポンサー)”とは誰のことですか?
申請人の生活費や学習費を負担する者です。親族や受入機関、財団等が該当します。支弁誓約書に加え、収入・残高・納税等の支払い能力の資料を添えます。文化活動ビザでは就労収入が不可のため、支弁者の実在性と継続性が審査の要点です。
資格外活動許可を取ればアルバイトは可能ですか?
原則週28時間以内での資格外活動許可が検討できます。ただし、文化活動の主目的を阻害したり、就労性が強い配置(深夜帯・長時間・単純労働中心など)は不適です。勤務先・職務内容・時間を理由書に整理し、生活費補填の補助的手段であることを示してください。
展覧会や発表会に出ることはできますか?(販売なし)
無償の発表・成果公開は可能です。販売・受注が伴うと就労性が生じるため不可です。コンテスト応募・学会発表も通常は可能ですが、賞金が対価と評価されないよう要注意です(規約と目的を説明できるようにしておきます)。
無給インターンや研究補助は文化活動に含まれますか?
受入機関の収益や業務に寄与する無給実務は、無給でも就労と判断されることがあります。純粋な研修・聴講・見学に留まる設計でなければ、留学や就労系在留資格等で検討すべきです。
オンライン授業やハイブリッド型の修得は対象になりますか?
日本国内での活動実体が中心で、指導・稽古・研究の主要部分が日本で行われるなら、補助的にオンラインを併用しても差し支えありません。海外居住ベースやオンライン主体だと適合性に疑義が生じます。
途中で方針転換し、芸術・興行・就労へ切り替えることはできますか?
活動内容が変わる前に、在留資格変更で適切な在留資格に切り替えます(例:創作+印税中心→芸術、観客向けの有償出演→興行、事務・調査・翻訳等の有給業務→技術・人文知識・国際業務)。無断で有償活動へ移行すると資格外活動違反のリスクがあります。
受入機関や指導者を変更したい場合の手続きは?
変更が活動計画の核心に関わる場合は事前に相談のうえ、活動機関に関する届出や在留資格変更が必要になることがあります。住所変更は市区町村・入管の双方への届出が必要です。
一時出国(里帰り・海外公演の見学など)はできますか?
みなし再入国許可(1年以内)の利用や再入国許可により可能です。在留カード・パスポートの携行、活動継続性(帰国後も同一計画で継続)の説明可能性を確保してください。長期離日が続くと在留継続性に疑義が出ます。
更新時に評価される“実績”とは何ですか?
出席・稽古記録、師範・指導者の指導記録・所見、成果物(論考・作品)、発表会・学会の参加証跡、計画との達成度、資金の健全な運用、法令遵守(納税・保険)が主要ポイントです。初回より次回更新の方が活動実態を厳密に見られる傾向があります。
理由書は必要ですか?どのような効果がありますか?
様式上の必須ではありませんが、非営利性の根拠、活動計画、受入体制、資金の内訳、資格外活動許可の要否などを一体的に説明する理由書は、補正予防・審査の迅速化に非常に有効です。グラフ・時間割・資金フロー等の定量化が推奨です。
家族は帯同できますか?家族滞在で帯同する配偶者は働けますか?
はい。配偶者・未成年の子は「家族滞在」で帯同可能です(生計要件・同居実態の確認があります)。配偶者が働くには資格外活動許可(週28時間以内)が必要です。帯同者側の収入が主となり申請人の文化活動が副次になると、更新審査で不利になることがあります。
在留期間はどのくらいですか?更新はできますか?
付与される在留期間は3年・1年・6か月・3か月のいずれかで、活動の継続性・非営利性・生計維持・遵法性を満たせば更新可能です。
申請先はどこになりますか?
在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。
申請はオンラインでも可能ですか?
はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。
必要書類は何ですか?
本人:履歴書、活動計画書、資金証明、住居予定、旅券・在留カード写し(国内)、受入側:受入承諾書、指導計画・時間割、団体概要、指導者の経歴・資格等が基本になります。当事務所では個々の状況を確認して必要書類をご案内します。
審査期間はどれくらいかかりますか?
ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
在留期間更新許可申請:2週間〜1.5か月
混雑状況や追加資料の要請があれば、さらに時間がかかる場合があります。文化活動ビザの場合も、活動の適合性(収入を伴わない学術・芸術上の活動であること)や非営利性・生計維持の立証が不十分だと補足要求が入ることがあります。余裕を持ったスケジュールをおすすめします。
不許可になった場合、再申請はできますか?
可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが必要です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低くなります。追加の補強資料を準備したうえで、再申請を検討します。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。