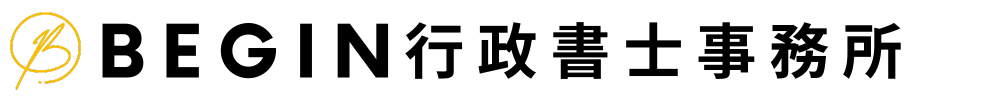Q&A
芸術ビザに関するよくある質問
芸術ビザが取れる人・取れない人の違いは何ですか?
提出書類は外国語のままでも大丈夫ですか?
日本語訳の添付が必要です。翻訳者の氏名・連絡先・作成日を明記し、要約訳ではなく審査に必要な部分は正確に翻訳します。作品レビュー記事や契約書、受賞証明、学位記、銀行残高証明等も同様です。
所属機関がなくフリーランスですが申請できますか?
可能です。委託契約書・発注書・出演/制作依頼レター・印税契約・活動計画(制作スケジュール・発表予定)・見込み収入の根拠をそろえ、継続性を示します。日本側の受入れ先(ギャラリー・出版社・音楽出版社・プロダクション等)があると説得力が増します。
芸術ビザの審査ポイントは何ですか?
①活動が芸術の創作/指導に該当するか活動の適合性、②実績・能力の裏付け(ポートフォリオ・受賞・レビュー・販売/再生数など)、③収入の持続可能性(契約・印税・助成・貯蓄)、④活動計画の具体性(場所・期間・発表形態・権利処理)、⑤遵法性(納税・社保・前歴なし)です。これらは理由書と裏付け資料で一体的に説明します。
どんな収入があれば許可されますか?金額の目安はありますか?
明確な金額基準はありません。受託報酬・印税(ロイヤリティ)・販売代金・出演料・オンライン配信収益などの合算で生活維持できる計画が示せれば足ります。過去1~2年の入金記録や契約書、将来の発注見込みで継続性を立証します。足りない部分は貯蓄残高・スポンサー支援などで補強が必要になる場合があります。
なぜ「芸術ビザは難しい」と言われるのですか?
作品の価値や実績の評価が定量化しづらいため、客観資料の揃え方で許可率が左右されやすいと考えられます。創作“主”、興行“従”の線引きも要点です。実績年表・作品リスト・メディア掲載・販売/再生データ・推薦状・契約群を体系化し、理由書で整合を取ることが重要です。
「芸術」と「文化活動」の違いは何ですか?
芸術:収入を伴う創作/指導が主。対価の受領が前提です。
文化活動:無報酬の研究・文化的活動・受入機関の支援で滞在。原則就労収入は不可です。活動実態と対価の有無で選択が変わります。
芸術収入が不安定な場合はどうなりますか?
印税の変動は一般的です。最低限の生活費を満たす資金計画(契約・過去実績・貯蓄・支援誓約・住居の確保)を示し、支出側の明細(家賃・制作費)も添えます。四半期単位のキャッシュフロープランを作成するなどは有効です。
私はフリーの作曲家ですが、芸術ビザは取れますか?
可能です。作曲委嘱契約・出版/配信契約・演奏使用料/二次利用料(JASRAC等)・制作スケジュール・作品リストで立証します。編曲・サウンドデザイン・ライブラリ提供も、創作の比重が主であれば対象に含められます。
学歴や学位は必要ですか?
必須ではありません。ただし、専門教育・受賞歴・著作・レビュー・指導歴などの総合評価です。学位は加点資料としては有効です。
「実績」とは具体的に何を指しますか?
個展/グループ展・フェス/ビエンナーレ・受賞/入選・出版/配信・映画祭/上映歴・レビュー/批評掲載・コレクション収蔵・販売/再生/視聴データ・著作権収入の実績など。第三者評価がある資料を重視します。
「創作活動を行う芸術家」とは?
自ら作品を創作し、発表・販売・受託制作で対価を得る者です。美術家、作曲家、作家、写真家、映像作家、振付家、詩人、イラストレーター等が典型です。
「芸術上の指導を行う者」とは?
芸術分野の教育・指導(講座・ワークショップ・スタジオレッスン等)で報酬を得る者です。シラバス・受講料設定・施設/受入機関の概要・実施実績で裏づけます。
※大学等での教育が主なら「教授」在留資格が適切な場合があります。
作曲家として活動しながら大学の非常勤講師をする場合は?
大学での教育活動が主なら「教授」を検討します。創作が主で、短時間の指導が従であれば「芸術」で説明できる場合もありますが、活動比重・契約形態で判断が分かれます。
実績が国内の小規模展覧会のみですが申請できますか?
申請自体は可能ですが実績評価で難易度はあがることが想定されます。展覧会の回数・選考性・キュレーター評価・販売状況・メディア掲載などを積み上げていくことで将来性を補強していくことも重要です。
収入がロイヤリティ中心で変動します。どう立証すればよいですか?
過去の分配明細・出版社/配信事業者の契約・使用実績・今後の配信/出版計画・最低保証を提示し、年間の幅をレンジで示します。不足分は貯蓄やスポンサー支援誓約でカバーします。
短期滞在から「芸術」へ在留資格変更はできますか?
原則は認定(COE)→査証→入国が安全ですが、やむを得ない事情や十分な立証がある場合に変更申請が受理・許可される余地があります。受理可否は個別判断のため、事前相談と書類設計が重要です。
留学から「芸術」へ在留資格変更は可能ですか?
可能です。在学中の実績・受賞・出版/発表・卒業後の契約/依頼見込みを中心に、主たる活動が創作であることを示します。副業的な興行・就労が主にならないよう活動設計に注意します。
在留期間更新で注意すべき減点ポイントは?
実績の停滞・収入の無根拠な減少・活動計画の曖昧さ・納税/年金の滞納・報告資料の不整合です。前回許可後の達成実績(発表・売上・印税・受賞・指導回数)を年次レポート化すると有効です。
在留資格認定証明書(COE)で海外から呼ぶ際の注意点は?
受入機関の実在性・契約条件(報酬/期間/作品の権利)・住居/制作拠点・活動計画(会場押さえ、制作スケジュール)を先出しで整えると審査がスムーズです。展示会場の予約証明やレーベルの承諾書が効果的です。
フリーランス(複数クライアント)でも取得できますか?
可能です。複数の契約書・発注書・ロイヤリティ見込みなど、収入の継続性を示す資料を整えます。請求〜入金のフローや納税の見通しも併せて示すと安定性の評価につながります。
在留中に執筆以外のアルバイトはできますか?
原則できません。芸術以外の就労を行う場合は資格外活動許可が必要です(可否は内容・時間等により判断されます)。
パフォーマンスも少し行います。芸術で申請できますか?
創作(芸術)が主、出演が従であれば芸術で説明可能な場合があります。観客相手の出演が主となる場合は「興行」での検討が安全です。案件ごとに最適な在留資格を設計します。
家族は帯同できますか?
はい。配偶者・未成年の子は「家族滞在」で帯同可能です(生計要件・同居実態の確認があります)。
申請先はどこになりますか?
在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。
オンライン申請は使えますか?
はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。
審査期間はどれくらいかかりますか?
ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
在留期間更新許可申請:2週間〜1.5か月
混雑状況や追加資料の要請があれば、さらに時間がかかる場合があります。芸術ビザの場合も、活動の適合性(創作が主で興行ではないこと)や実績・収入根拠の立証が不十分だと補足要求が入ることがあります。余裕を持ったスケジュールをおすすめします。
必要書類は何ですか?
本人:履歴書、ポートフォリオ(作品・掲載・受賞・販売)、推薦状(任意)、在留カード・旅券写し(国内)/受入先:契約書、会社概要(登記事項証明・事業説明)、報酬根拠(支払条件・印税率等)、スケジュール・活動計画 等が基本です。当事務所では個々の状況を確認して必要書類をご案内します。
理由書はどの程度重要ですか?
非常に重要です。創作=主/興行=従の線引き、実績・契約・収入計画、年間スケジュール、権利処理・安全配慮を図表+数値で整理し、証拠資料との対応表を付けると効果的です。
在留期間はどのくらいですか?更新はできますか?
付与される在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、要件を満たせば更新可能です。更新時は、活動の実態が引き続き「芸術上の創作活動」に該当しているか、創作実績(展覧会・出版・受賞・販売)や収入(報酬・印税等)の継続性、契約・依頼の見込み、制作体制・活動拠点の維持、申請人の納税・法令遵守状況などが総合的に確認されます。雇用契約型の案件がある場合は、受入先の体制や契約の継続性も併せて確認されます。
不許可になった場合、再申請はできますか?
可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが必要です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低くなります。追加の補強資料を準備したうえで、再申請を検討します。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。