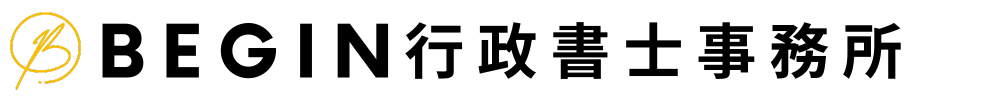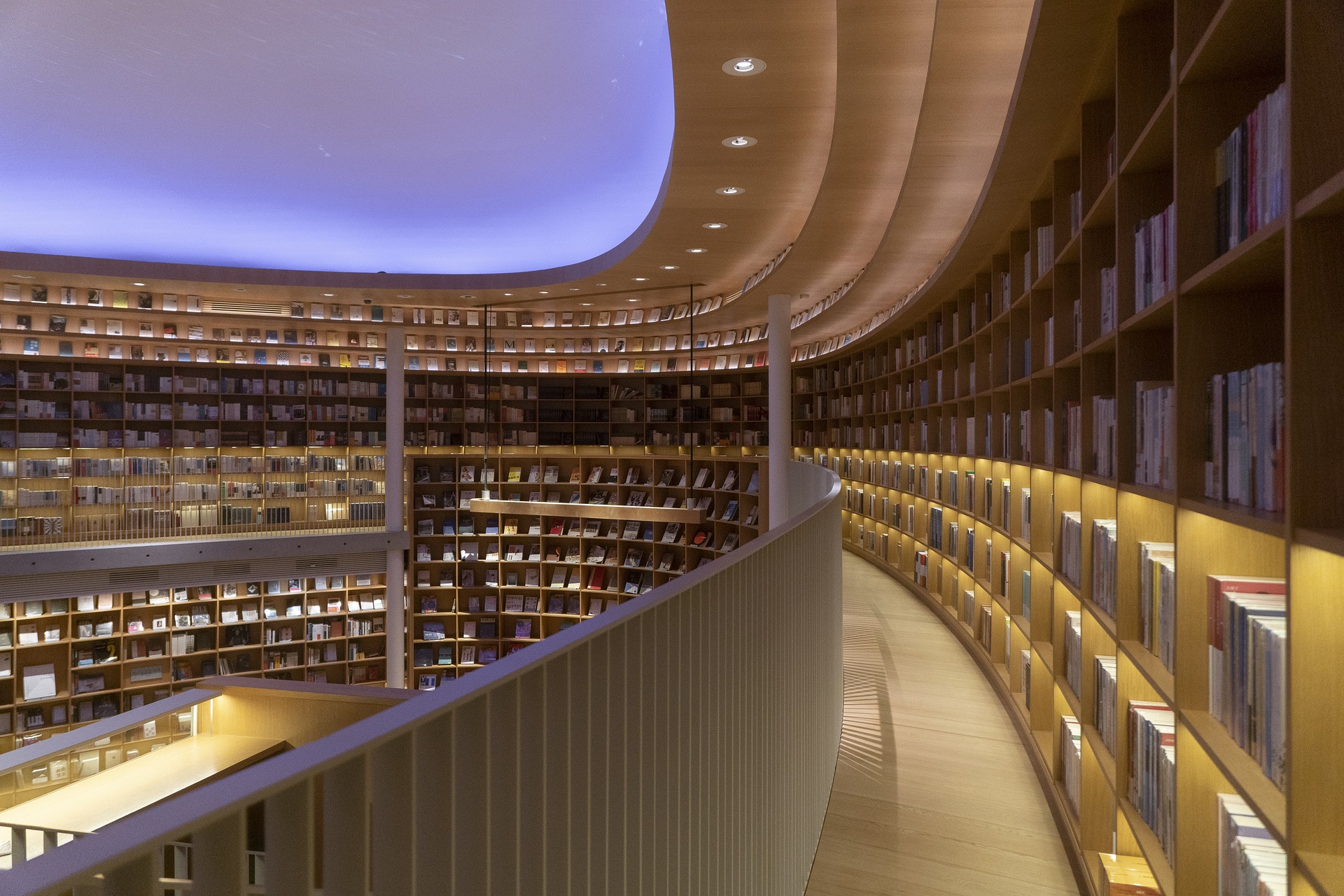Q&A
特定活動ビザ(46号)に関するよくある質問
どのような人が「特定活動(46号・本邦大学等卒業者)」の対象になりますか?
日本の大学・大学院などを卒業(学位取得)した方で、日本語による円滑なコミュニケーションを前提とする業務に従事する就職が決まっていることが要件の中心です。いわゆる「技術・人文知識・国際業務」では取り扱いにくい販売・接客・一般事務・営業支援などの職種も、業務実態として日本語運用が本質となる場合は対象になり得ます。反対に、単純作業が主となる職務は対象外です。
どんな職種が想定されますか?販売・接客でも大丈夫ですか?
「日本語による円滑な意思疎通」を中核とする顧客対応・社内調整・営業支援・一般事務などが典型です。販売・接客も、説明・提案・クレーム対応・多言語サポートなど日本語運用が要となる実態であれば対象になり得ます。反対に、流れ作業等の単純作業が主となる配置は認められません。
日本語試験(JLPT)の合格は必須ですか?
原則として 日本語試験(JLPT) N1 又は BJT 480 点以上が求められます。 実務上の日本語使用(顧客説明・社内調整・文書作成)の証跡で補強すると評価が安定します。
給与や雇用条件の基準はありますか?
日本人と同等額以上の報酬が必要です。雇用契約書とともに、賃金規程・賃金テーブル・同職比較など数字で示す資料をご用意ください。社会保険加入や労働法令の遵守も必須です。
家族は帯同できますか?
原則として、配偶者・未成年の子は在留資格「家族滞在」での帯同が可能です(生計要件・同居実態の確認があります)。配偶者が就労する場合は、資格外活動許可等の手続きが必要です。
転職や配置転換は可能ですか?届出はありますか?
転職・配置転換は、職務が引き続き「46号」の趣旨(日本語を用いたコミュニケーションを中核とする業務)に適合していることが前提です。雇用先が変わる場合は14日以内に「契約機関に関する届出」が必要です。業務実態が46号の枠から外れる場合は、在留資格変更が必要になり得ます。
新卒内定で「留学」から切り替えるタイミングは?
通常、卒業見込みが出た段階で内定書等を添付して在留資格変更許可申請が可能です(許可は卒業を前提として判断)。採用予定日・試用期間・配属先など、実務に踏み込んだ職務設計を理由書に整理しておくと審査がスムーズです。
派遣就労はできますか?
原則できません。特定活動(46号)は受入機関との直接雇用を前提とします。派遣契約のように指揮命令が派遣先に移る働き方は不可です。自社雇用のまま客先で作業する場合でも、請負・業務委託の適法性(指揮命令・責任分界)を理由書で明確化し、偽装請負の回避を資料で示す必要があります。
パート・アルバイト(短時間勤務)でも取得できますか?
不可です。46号はフルタイム相当(週30時間以上が目安)の直接雇用が原則です。短時間勤務・日雇い・登録型は適合しません。
業務委託(フリーランス)や個人事業主契約は可能ですか?
不可です。特定活動(46号)は雇用契約が前提で、請負・業務委託のみでは認められません。フリーランスで働く場合は、別の在留資格の検討が必要です。
『技術・人文知識・国際業務(技人国)』と『特定活動(46号)』はどちらが適切?
技人国:専門知識(情報・機械・金融・企画・通訳翻訳 等)を要するホワイトカラー職が中心で多くの方が取得している在留資格です。
46号:日本語での顧客対応・社内外調整・営業支援・一般事務など、日本語運用が業務の中核となる職種。販売・接客でも提案・説明・クレーム対応など日本語コミュニケーションが本質なら46号が適合し得ます。両立する要素がある場合は、職務記述書(JD)と業務フローを分解し、最も整合する在留資格を選びます。
特定活動(46号)で副業・兼業はできますか?
原則不可(主たる雇用先でのフルタイムが前提)。やむを得ず副業が必要な場合は、内容・時間帯・就業地を特定した資格外活動許可(個別/包括)の可否を事前に確認してください。主従逆転や就労時間の超過は更新不利や取消事由となり得ます。
特定活動(46号)から永住を目指せますか?
可能です。要件は永住一般要件(素行善良・独立生計・将来の在留安定性 等)。永住許可申請における在留歴は一律ではなく、46号だけで満たす必要もありません。社会保険加入・納税・年収水準・雇用の継続性を定点管理し、理由書で生活基盤の安定を示すことが重要です。
試用期間中でも申請・許可は出ますか?
可能です。ただし本採用前提で、職務・報酬・就業時間が契約書に明記され、日本人同等以上の待遇であることが前提になります。試用終了後の配属や評価指標も、業務の日本語中核性が維持される設計で示します。
未経験職種でも大丈夫ですか?
可否は“業務が日本語中心であること”で判断されます。学位との厳密な専門一致は技人国ほど強く要求されませんが、履修歴・インターン・接客経験などで実務遂行の具体性を補強するのが安全です。
クライアント先常駐や多店舗ローテーションは問題ありませんか?
派遣でなければ可。勤務先・指揮命令系統・就業場所を契約書に明記し、常駐の法的根拠(請負/業務委託の適法性)と日本語コミュニケーション中心の職務を資料化します。多店舗勤務は配属一覧・移動基準を付けると審査が安定します。
受入企業がスタートアップや小規模でも申請できますか?
可能です。ただし、登記事項・事業計画・資金繰り・決算書等で事業実体と継続性、社会保険加入、コンプライアンス体制を数値で示すことが重要です。
在留期間更新の審査で見られるポイントは?
職務の適合性(“業務が日本語中心であること”が継続)・雇用継続・報酬推移・人事評価・納税/社保・法令順守です。職務変更が大きい場合は就労資格証明書で事前確認すると安全です。
退職・内定取消になった場合の対応は?
14日以内に「契約機関に関する届出」が必要です。3か月以上活動しないと在留資格取消のリスクがあります。継続就職活動が必要な場合は、特定活動(継続就職活動)等への在留資格変更を早めに検討してください。
不許可になりやすいのはどんなケースですか?
実質が単純作業、指揮命令が顧客側(派遣同等)、待遇が日本人同等未満、日本語要件の根拠が薄い、企業の社会保険未加入、説明資料が抽象的等です。理由書で“業務が日本語中心であること”を業務フロー・KPIで可視化し、賃金規程・同職比較で数値立証しましょう。
COE(在留資格認定証明書)は必要ですか?在留資格変更で足りますか?
国内に在留中(例:留学から切替)の方は、原則として在留資格変更許可申請で切り替えます(COE不要)。海外在住の方や卒業後に一度出国した方は、COEを取得してから査証申請・入国となります。どちらのルートでも、審査で見られる観点(学位・職務内容・待遇など)は同じです。
申請先はどこになりますか?
在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。
申請はオンラインでも可能ですか?
はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。
必要書類は何が要りますか?
案件により変わりますが、一般的には次のような書類が中心です。
本人側:卒業(見込)証明書・学位記の写し、履歴書、在留カード・旅券の写し(国内申請時)、日本語能力を示す資料(任意:JLPT/N1・N2、大学での日本語履修実績など)
企業側:雇用契約書(職務内容・勤務時間・報酬)、会社の概要資料(登記事項証明書、事業内容)、賃金規程や同職比較など日本人と同等以上の待遇を示す資料、職務記述書(Job Description)・業務フロー等
※日本語以外の書類には日本語訳を添付します。当事務所で案件ごとの必要書類リストを作成します。
COEと在留資格変更、用意する書類に違いはありますか?
大枠は同じですが、COEは新規入国前の審査のため、受入体制の説明資料(住居・入社日・オリエンテーション等)をより丁寧に添えるとよいです。国内の在留資格変更では、現行の在留状況(留学の在籍・成績、資格外活動の有無等)も確認されます。
審査期間はどれくらいかかりますか?
ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
在留期間更新許可申請:2週間〜1.5か月
混雑状況や追加資料の要請があれば、さらに時間がかかる場合があります。余裕を持ったスケジュールをおすすめします。
在留期間はどのくらいですか?更新できますか?
在留期間は5年・3年・1年(場合によっては6か月)のいずれかが付与され、要件を満たしていれば更新可能です。更新時も、職務の適合性・雇用継続性・待遇の同等性・法令遵守状況などが確認されます。
不許可になった場合、再申請はできますか?
可能です。不許可通知書の記載を踏まえ、職務の適合性(日本語運用が業務の中核であること)、待遇の同等性、企業側の体制など、指摘点を補強したうえで再申請します。同じ資料のまま再提出しても結果は変わりにくいため、理由書の再設計と証拠資料の追加が重要です。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。