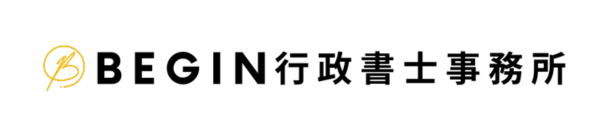Q&A
家族滞在ビザに関するよくある質問
家族滞在ビザとは何ですか?誰が対象になりますか?
家族滞在ビザは、就労・就学などの在留資格で日本に在留する本人(扶養者)の配偶者(法律上の婚姻)と未成年・未婚の子が生計を同じくして帯同するための在留資格です。日本人や永住者の家族は「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」など別区分になります。父母や兄弟姉妹、事実婚・同性パートナーは原則対象外です。
家族滞在ビザで働くことはできますか?
原則として、家族滞在ビザの活動は扶養を受けることに限られており、就労は認められていません。しかし、入国管理局から「資格外活動許可」を取得すれば、週28時間以内であればアルバイトなどのパートタイム就労が可能です。恒常的に働く場合は就労系在留資格への変更を検討します。
扶養者の収入が少ない場合でも申請できますか?
扶養者の経済力は、審査において最も重要なポイントです。収入が少ない場合でも、預貯金など、家族全員の生活を支えられることを客観的に証明する必要があります。当事務所では、お客様の状況に合わせてどのような資料を提出すべきかアドバイスいたします。
家族滞在ビザを申請する際に、婚姻関係を証明する書類は必須ですか?
はい、婚姻証明書や結婚証明書などが必須となります。また、偽装結婚を疑われるケースでは、家族写真や交際の経緯を説明する理由書を添付することで、信憑性を高めることができます。
親を呼び寄せることはできますか?
原則として、家族滞在ビザの対象は配偶者と子のみであり、親や兄弟姉妹は対象外となります。特別な事情がある場合は、「特定活動」などの別の在留資格を検討する必要があります。
何歳までの子を呼ぶことが出来ますか?
一般的には義務教育の14歳までです。15~17歳は高校に通っている場合は家族滞在ビザが許可される場合があります。18歳以上は家族滞在ビザは難しく、留学ビザや就労ビザを検討する必要があります。
扶養者になれるのはどの在留資格ですか?
代表的には技術・人文知識・国際業務(技人国)/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理/留学など、中長期の在留資格を持つ本人が扶養者になれます。特定技能でも可能ですが、雇用・収入の安定性や受入体制の説明がより重要になります。
事実婚・同性パートナーは家族滞在の対象ですか?
家族滞在は原則「法律上の婚姻」が必要です。同性パートナーや事実婚は原則対象外ですが、特定活動で個別に配慮される例があるため、関係の継続性・扶養実態・母国の婚姻制度等を踏まえた「特定活動ビザ」が認められる場合があります。
配偶者が現地で退職して専業主婦(夫)として帯同することは可能です
可能です。家族滞在は就労を目的としない帯同資格ですので、配偶者の就労有無は問いません。生計維持能力(収入・貯蓄)の立証が重要です。
日本に短期滞在で来ている配偶者を家族滞在に「変更」できますか?
短期滞在から他の在留資格への変更はできないのが原則ですが、例外的に「やむを得ない特別な事情」が認められる場合(未就学児の養育、妊娠・出産、やむを得ない事情の一体立証など)に在留資格変更許可が認められることがあります。一律可ではないため、特別な事情を理由書と証拠資料で必要性を丁寧に示す必要があります。
国内在留中(例:留学や就労)から家族滞在への変更はできますか?
配偶者や子として帯同に切り替える実態があり、同居・扶養が成立するなら在留資格変更許可は可能です。在留期限に余裕を持って申請し、活動の実態変化(学業→帯同など)を理由書で説明します。
家族滞在ビザの申請要件は?
主に①身分関係の真正(婚姻・親子)、②同居・扶養の実態、③生計維持能力(収入・資産)、④扶養者の在留の安定性と遵法性(納税・社保)です。偽装防止の観点から交際・同居の実態も確認されることがあります。
別居中でも申請できますか?
原則は同居が前提です。やむを得ない単身赴任・転勤・進学などは、期間・往来・仕送り・オンライン面談等を資料で補強し、同居に向けた計画を明示します。恒常的な別居は不許可のリスクがあります。
在留期間はどのくらいですか?初回から3年や5年は出ますか?
在留期間は5年・3年・1年・6か月のいずれかで、扶養者の在留期間・雇用安定性等に連動します。初回は1年付与が多め、継続実績に応じて3年・5年が見込めます。
更新(在留期間更新)のポイントは?
同居・扶養の継続、収入・納税・社保の遵法性が重要です。前年課税・納税証明、在職証明、住民票(同一世帯)を整え、子の就学実績や医療保険加入など生活の実態を示すと安定します。扶養者の転職直後は、就労資格証明書の取得で安定性が高まります。
扶養者の在留資格が変わったら場合(例:留学→技人国)、家族は手続が必要ですか?
家族滞在の在留資格自体は継続できますが、更新時に新しい在留状況(雇用・収入など)で再評価されます。在留カード情報や届出(住居地変更・所属機関変更)は14日以内に行ってください。
扶養者が失職した場合、家族滞在はどうなりますか?
直ちに失効ではありませんが、生計維持能力の見通しが焦点になります。再就職活動の状況、貯蓄、補助などを準備し、更新前に雇用確定できると安心です。長期無収入は不利となります。
子どもの就学や医療保険の手続はできますか?
住民登録後、公立学校の就学案内が届きます。医療は国民健康保険(または被用者保険の扶養)に加入します。乳幼児医療費助成など自治体制度も活用可能です。
みなし再入国許可は使えますか?
はい。在留カード所持者は1年以内(有効期限内)の出入国でみなし再入国許可が利用できます。パスポート・在留カードの有効期限に注意してください。
日本で子が出生しました。手続はどうすれば良いですか?
出生から14日以内に出生届(市区町村)、30日以内に在留資格取得許可申請(入管)が必要です。許可が下りると「在留資格取得許可通知書」が発行されます。通知書を持参して市区町村役場で住民登録を行い、その後在留カードの発行手続きを進めます。期日管理が重要です。
配偶者と離婚または死別した場合、家族滞在はどうなりますか?
入国管理局へ「配偶者に関する届出」(14日以内)が必要です。家族帯同の根拠が失われるため、引き続き日本に在留するための在留資格変更(就労・定住者など)か出国の選択が必要になります。子の監護状況・就労見込み等で個別設計します。在留資格変更申請は離婚・死別から6か月以内に行う必要があります。
父母(両親)を呼び寄せたいです。家族滞在で可能ですか?
家族滞在は配偶者・未成年の子のみが原則です。親の帯同は原則不可です。
住民税・国保の未納があります。更新に影響しますか?
納税・保険料の滞納は不許可になるリスクが高いです。完納証明、分割納付計画、納付実績を整えてから更新に臨むのが安全です。
扶養者が副業をしています。収入の立証はどうすべきですか?
主たる雇用+副業の収入を合算し、課税・納税証明、支払調書、源泉徴収票、通帳等で総収入の安定性を示します。就業規則上の副業可否にも留意してください。
家族滞在ビザから就労ビザ(技人国)へ切替は可能ですか?
可能です。学歴・職歴の適合、雇用契約、職務内容、報酬(日本人同等以上)を満たせば在留資格変更ができます。許可後に資格外活動許可は不要になります。
配偶者が通信制大学やオンライン課程で学ぶ予定です。家族滞在に影響はありますか?
家族滞在は帯同・扶養が趣旨であり、学びの形態自体は直接の要件ではありません。ただし同居・扶養の実態は変わらず求められます。長期別居になる状況は避けてください。
子どもだけ先に日本に入国させ、配偶者は後から来日できますか?
保護者の監護が確保される体制(日本側の保護者同居や学校寮の監督など)が必要です。原則は保護者同伴を推奨します。
住所地が変わりました。何か届出は必要ですか?
14日以内に住居地の届出(市区町村・入管)が必要です。健康保険・学校も連動するため、転居前後のスケジュールを調整してください。
家族滞在ビザの更新はいつからできますか?
在留期間満了日の3ヶ月前から更新申請が可能です。期限ギリギリでの申請はリスクが高まるため、早めの準備をおすすめします。
必要書類は何ですか?
申請書、写真、旅券、在留カード(該当時)/婚姻証明・戸籍・出生証明(外国書類は公証・アポスティーユ+日本語訳)/住民票(同一世帯)/課税・納税証明、源泉徴収票、雇用契約書・在職証明、残高証明など収入・資産資料/住居関連(賃貸契約・間取り)/理由書。ケース別に学校在籍証明や医療証明等を加えます。
申請先はどこになりますか?
在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。
・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)
注意:出張所では取り扱わない手続があります。案件によって本局・主要支局への提出指定となる場合があります。
申請はオンラインでも可能ですか?
はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。
審査期間はどれくらいかかりますか?
申請内容や時期によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留期間更新許可申請:2週間〜1ヶ月半 混雑状況や追加資料の提出が求められた場合、さらに時間がかかることがあります。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3ヶ月
在留資格変更許可申請:1〜2ヶ月
理由書は必ず必要ですか?
必須ではありませんが、特に学歴や職歴が要件ぎりぎりの場合や、雇用内容と資格要件の関連性を強調したい場合には、理由書が大きな効果を発揮します。理由書は申請者や企業の背景、採用の必要性、業務内容の詳細を論理的に説明するもので、審査官が納得しやすくなります。当事務所では状況に応じたカスタマイズ理由書を作成しています。
不許可になった場合、再申請は可能ですか?
はい、可能です。しかし、一度不許可になった理由を十分に分析し、その問題点を解消した上で再申請することが不可欠です。当事務所では、不許可になった理由を詳細に確認し、許可を得るための戦略的な再申請をサポートします。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。