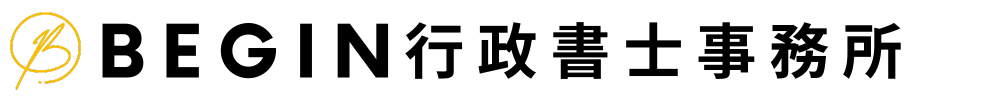Q&A
報道ビザに関するよくある質問
テレビの番組制作に関わります。報道ビザで良いですか?
ニュース報道・時事解説・ニュースドキュメンタリーに従事し、外国報道機関と契約しているなら「報道」が想定されます。
一方、ニュース以外の番組制作でバラエティ・ドラマ・CM・リアリティ番組・商業ドキュメンタリー等は原則「報道」ではありません。内容に応じて興行(出演・公演・商業制作)や技術・人文知識・国際業務(技人国)等が適切になります。番組の性質(ニュース性の有無)と職務内容で報道との線引きを事前に設計を行います。
フリーランス記者/カメラマンでも取得可能ですか?
可能です。外国の報道機関との継続的な委託契約や依頼見込み、報酬計画、実績資料で立証します。
SNS発信中心の“ジャーナリスト”ですが、報道ビザの対象になりますか?
SNSやブログのみで自主発信している方は、その活動が「外国の報道機関との雇用・委託契約」に基づくニュース報道であることを立証できない限り、報道ビザの対象になりにくいです。フォロワー数や再生回数だけでは足りず、外国報道機関との契約書・編集方針・掲載/放送予定などで「報道としての活動実態」を示すことがポイントです。短期の臨時取材(90日以内)は短期滞在(報道)で取り扱われる場合もあります。
日本の報道機関に雇用される場合も「報道」ですか?
いいえ。在留資格「報道」は外国の報道機関(日本支局・在日支社を含む)向けです。日本の報道機関に雇用される場合は、業務内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」が原則の検討対象になります。
日本支局で経理・総務・SEなどバックオフィス業務を担当します。報道ビザになりますか?
報道の取材・編集・送稿が主たる活動でないバックオフィス(経理・人事・総務・法務・営業・IT・マーケ等)は「報道」ではありません。技人国または企業内転勤での申請を検討します。
カメラ・音声・照明などの技術スタッフも報道ビザの対象になりますか?
ニュース報道の制作工程に不可欠な技術スタッフ(ENGカメラ、音声、照明、現場編集、送出等)は対象になり得ます。職務が報道目的であること、編集体制・業務フロー(取材→編集→配信)が明確であることを資料で示すと安心です。
※スタジオ常駐の放送技術・システム運用のみ等は、内容によっては技人国が適切になる場合があります。
複数の外国報道機関と同時に契約しても大丈夫ですか?
可能です。主たる契約先・役割の整理、年間の活動計画、報酬見込み(配分)を示し、就労実態が在留資格「報道」の範囲に収まることを立証します。過度な副業的活動やマーケ・PR中心は対象外になるおそれがあります。
「短期滞在(報道)」と在留資格「報道」の違いは?
短期滞在(報道)は、90日以内の臨時取材など短期の派遣向けです。長期駐在・継続取材・在日支局勤務は在留資格「報道」での設計が必要です。短期滞在から「報道」への切替は原則想定されないため、最初から適切な在留資格を選びましょう。
日本国内で雇用主や担当番組が変わる場合、何か確認は必要ですか?
雇用主変更や報道→バックオフィス等の活動実態の変化がある場合は、在留資格変更や就労資格証明書の取得で適法性を確認しておくと安全です。更新時の説明もスムーズになります。
報酬水準はどの程度が求められますか?
法律上の一律金額はありませんが、日本人と同等以上の報酬水準と、社会保険加入・適正な契約条件が重視されます。契約書・賃金規程・同職比較など数値根拠で示すと評価が安定します。
取材で道路使用・施設撮影・ドローン等が必要です。ビザと関係しますか?
在留資格とは別に、各種許認可(道路使用、施設許可、著作権・肖像権、ドローン飛行許可等)が必要になる場合があります。ビザが許可=全ての撮影が自由ではありません。企画段階で許認可計画を準備しましょう。
「技人国」から「報道」へ(またはその逆)に切り替えられますか?
可能です。活動の実態・契約先の種別(外国報道機関か否か)が変わると、適切な在留資格も変わります。変更の必要性と新活動の適合性を、契約書・体制・理由書で整理して申請します。
家族は帯同できますか?
はい。配偶者・未成年の子は「家族滞在」で帯同可能です(生計要件・同居実態の確認があります)。
海外在住ですが、来日前の手続きは何を選べば良いですか?
海外にいる場合は在留資格認定証明書(COE)→現地の日本大使館・総領事館で査証申請→入国が基本です。日本国内に有効な在留資格で滞在中なら在留資格変更を検討します。
なお、短期滞在から就労系への変更は原則不可(例外あり)なので、来日前にCOEで段取りするのが安全です。
理由書は必須ですか?提出すると有利になりますか?
理由書は出入国在留管理庁(入管)のホームページでは必須ではありませんが、ニュース性・公益性/契約・報酬の適正/体制・安全管理/業務フローを一体的に説明する理由書は非常に有効です。審査官が短時間で全体像を掴めるため、補正や往復照会の予防に役立ちます。
申請先はどこになりますか?
在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。
オンライン申請は使えますか?
はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。
必要書類は何ですか?
企業側:雇用/委託契約、派遣辞令、活動計画、在日支局の概要(登記事項・体制)、報酬根拠(賃金規程・同職比較)。本人側:履歴書、職務実績(紙面/放送クリップ)、プレスカード、旅券、写真等が基本です。 案件により撮影許可方針、権利処理体制等を追加します。当事務所では個々の状況を確認して必要書類をご案内します。
審査期間はどれくらいかかりますか?
ビザの種類や申請内容の複雑さによりますが、一般的な目安は以下の通りです。
在留資格認定証明書交付申請(COE):1〜3か月
在留資格変更許可申請:1〜2か月
在留期間更新許可申請:2週間〜1.5か月
混雑状況や追加資料の要請があれば、さらに時間がかかる場合があります。報道ビザの場合も、活動の適合性(ニュース性・報道目的)や契約・体制の立証が不十分だと補足要求が入ることがあります。余裕を持ったスケジュールをおすすめします。
在留期間はどのくらいですか?更新はできますか?
付与される在留期間は5年・3年・1年・3か月のいずれかで、要件を満たせば更新可能です。更新時は、契約継続・報道実績・生計の安定性・法令遵守状況などが総合的に確認されます。
不許可になった場合、再申請はできますか?
可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが必要です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低くなります。追加の補強資料を準備したうえで、再申請を検討します。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。