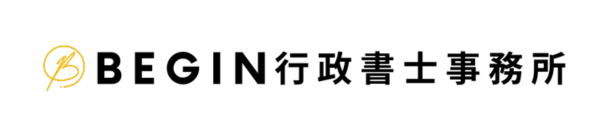Q&A
配偶者ビザに関するよくある質問
結婚して日本で一緒に暮らしたい。最初の手続きは?
相手の“現在の居場所と在留状況”で分岐します。
- 相手が海外在住:日本側で在留資格認定証明書(COE)を申請 → 交付後、海外の日本大使館・総領事館で査証申請 → 入国・在留カード交付。
- 相手が日本在住(別の在留資格):日本で在留資格変更許可申請(例:留学/技人国 → 日本人の配偶者等)。
- 婚姻の法的成立(日本・相手国双方の婚姻手続き)と同居予定の住居、生計維持(収入・貯蓄・支援計画)、交際経緯の立証を同時並行で整えるのが実務的にスムーズです。
短期滞在ビザから配偶者ビザに変更することはできますか?
原則として短期滞在ビザからの変更は認められていません。例外として、短期滞在の間に日本で婚姻届けを提出した場合や病気や妊娠、子どもが生まれた場合などやむを得ない特別な事情があるときには例外的に申請できる場合もあります。ただし、申請書類一式を準備した上で、入管の窓口へ事前相談が必要となります(オンライン申請はできません)。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更申請が不許可になると一度出国し、再度在留資格認定証明書を取得して入国する必要があります。
夫婦ともに海外にいる場合、在留資格認定証明書交付申請(COE)を申請できますか?
申請は可能です。ただし、日本人配偶者が先に帰国して「在留資格認定証明書交付申請」を行うケースや、日本国内の居住する親族に申請代理人を依頼するケースがあります。
在留期間はどれくらい受けられますか?
多くの場合は初回1年が付与されます。結婚期間や収入・貯蓄状況によっては3年または5年が認められるケースもあります。更新申請を重ねることで、より長期間の在留が可能になることもあります。
世帯年収や収入要件はありますか?
明確な基準はありませんが、夫婦が安定した生活を送れるだけの収入があるかがポイントになります。一般的な目安は年収約300万円程度ですが、預貯金や不動産、親族からの援助などがある場合は柔軟な判断もされます。
収入が十分でない場合はどうすれば良いですか?
収入が少ない場合でも、預金残高、不動産収入、家族からの支援計画を示すことで補完できる場合があります。必要に応じて補足資料を収集し「理由書」で説明をすることになります。
生活保護受給中でも取得可能ですか?
現時点で生活保護を受給している場合、不許可となる可能性が高いです。経済的自立の見込み(内定)や家族支援の担保が出来ているなどによっては許可されるケースもあります。
年齢差が大きいと審査で不利になりますか?
年齢差そのものは不許可の理由にはなりませんが、場合によっては偽装結婚と疑われる可能性があるため、審査は厳しくなります。関係性を裏付ける交際経緯や共同生活実例を示す資料が証拠書類が重要になります。
偽装結婚と疑われないようにするにはどうすれば良いですか?
婚姻証明書だけでなく、交際記録(写真、SNS・通話履歴)、家族とのやり取り、婚姻に至るまでの経緯を整理し、審査官に「真実の婚姻」として伝わる構成でまとめることが大切です。
身元保証人は誰でもなれますか?
原則として日本人配偶者が身元保証人となります。収入が十分でない場合などでは、親族など他の方も身元保証人とすることもあります。
同居していない場合でも申請できますか?
原則、同居が求められます。ただし、仕事や学業などやむを得ない別居の場合はその理由を説明し、別居先の事情を証明する資料(契約書・通勤状況など)と一緒に申請が可能です。
就労はどのようにできますか?
配偶者ビザには就労制限がないため、原則として日本人と同様に自由に働くことができます。どのような雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)でも、起業や会社経営も可能です。ただし、特定の業種(風俗営業など)には在留資格の更新時に審査が厳しくなる可能性があります。
海外にいる配偶者を日本に呼ぶには?
基本ルートは在留資格認定証明書交付申請(COE)です。日本側(日本人配偶者など)が管轄入管に申請し、婚姻の実在性・同居の意思・生計の安定性を疎明します。交付後に現地の日本大使館・総領事館で査証申請、入国後に在留カードが発行されます。申請前に必要書類と補足資料(写真・通信記録・送金記録等)を精査しましょう。
すでに日本で暮らしていて結婚しました。配偶者ビザの手順は?
在留資格変更許可申請が基本です。現在の在留資格の在留期限に注意しつつ、婚姻成立書類、同居実態/同居計画、収入・納税/社保の資料、交際経緯を準備。短期滞在中の変更は原則不可(特別の事情は別)なので、該当する場合は在留資格認定証明書交付申請(COE)ルートを含めて設計します。
配偶者ビザの申請と結婚手続き、どちらが先に必要ですか?
婚姻の法的成立が先です。国際結婚の場合、お互いの国の法律に従って結婚手続きを進める必要があります。国によっては、日本で先に結婚したことによって、外国側で必要な書類が発行されなくなることもあるため、相手の国の制度もしっかり確認して結婚手続きを進める必要があります。
- 日本で婚姻届 → 相手国での婚姻登録(必要な国もあり)→ 配偶者ビザ申請。
- 逆に相手国で先に婚姻成立 → 日本での婚姻届出(報告的届出) → 配偶者ビザ申請。
いずれの順でも「双方の法域で婚姻が有効」であることの証明が肝要です。
相手国に渡航したり、相手を日本に呼ばないと婚姻手続きはできない?
日本人の場合は、相手の方が日本にいなくても婚姻手続きをすることができます。外国での婚姻手続きは国・事情により異なりますので、相手の国の制度もしっかり確認して結婚手続きを進める必要があります。
配偶者ビザでは何が審査されますか?
配偶者ビザ取得にあたっては、①結婚の信憑性と真実性、②安定した生活基盤、③同居の継続性、④素行や在留の適正を書面で立証する必要があります。
詳細は配偶者ビザ申請を成功させる4つのポイントも参照ください。
理由書は重要ですか?
重要です。 出入国在留管理庁(入管)のホームページでは必須ではありませんが、実務的には作成を強く推奨しています。
- 交際〜婚姻に至る具体経緯
- 生計・住居の数値計画
- 長期別居・年齢差・言語の壁など
疑義化しやすい点の先回りして補足することで、補正・照会・不許可のリスクを下げられます。
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」から配偶者ビザに変更できますか?
可能です。婚姻の実在性と同居・生計の見込みを立証できれば、在留資格変更許可申請で切替えます。変更後は就労制限なし(法令上の禁止業種は除く)となります。
「留学」から配偶者ビザに変更できる?
可能です。婚姻成立、同居・生計の設計、学業との整合(中退/転学の扱い)などを理由書で明確化します。学費返金や在学証明の取り扱いは学校規程も確認をする必要があります。
外国で暮らす配偶者の子供を呼び寄せるには?
外国で暮らす配偶者の連れ子を日本に呼び寄せるには、「定住者(告示6号)」という在留資格を検討します。こ未成年・未婚の実子、外国人配偶者に扶養される扶養を受ける必要があります。
収入が不安です。共同保証や第三者の支援は有効ですか?
身元保証書は原則日本人配偶者ですが、実親等の支援計画書・送金証憑・残高証明などで生計の安定性を補強可能です。理由書で家計収支(キャッシュフロー)を提示します。
納税・社会保険・住民登録は審査に影響しますか?
影響します。課税・納税証明、年金/健康保険の加入状況は遵法性の重要指標です。未納や未加入はマイナス評価になり得ます。過去分が未納がある場合は早めに是正が必要です。
住居の名義/広さに決まりはありますか?
画一基準はありませんが、同居の実態が取れること(賃貸借契約・同居人欄・間取り・通勤動線などの合理性)がポイントになります。長期別居を予定する場合は、理由と頻繁な往来/生活費負担の実情を補足します。
交際期間が短い場合の注意点はありますか?
期間の短さ自体は即不許可ではありませんが、審査官の疑義を払拭するため、関係の実在性・継続性を厚く立証する必要があります。
- 時系列の可視化:出会い~婚姻までの経緯を日付入りで整理(初回接点/面会回数・滞在期間/プロポーズ時期)。
- 客観資料:双方家族・友人の認知、結婚式・顔合わせの記録、旅行・訪問スタンプ、送金/小包の控え、共同名義の契約等。
- 生活設計の具体性:住居契約、家計収支(収入・預貯金・支援)、就労予定、将来計画(出産・教育など)。
- 理由書で先回り:なぜ短期で婚姻に至ったか、価値観・将来像の一致点、言語コミュニケーション手段を説明。
年齢差が大きい場合の注意点はありますか?
年齢差は直ちに即不許可ではありませんが、年齢差が大きいほど、偽装婚の疑義を払拭する説明が重要です。
- 関係の背景:知り合った文脈(職場・留学・地域コミュニティ等)と継続的な交流の実態。
- 相互理解の立証:家族紹介の有無、互いの母語/文化への適応、医療・介護・将来設計の話し合い履歴。
- 経済的依存の懸念への対応:一方的な経済支援に見えないよう、家計分担や貯蓄計画を数値で提示。
- 長期性の裏付け:同居実績や頻繁な往来、記念日・行事の共同履歴、第三者の推薦・証言。
配偶者が死亡または離婚した場合はどうなりますか?
離婚または死別日から14日以内に、出入国在留管理庁に「配偶者に関する届出」を行う義務があります。
離婚または死別後も日本に在留を希望する場合は、他の在留資格への変更申請が必要です。
配偶者ビザの更新はいつからできますか?
在留期間満了日の3か月前から申請可能です。更新漏れに注意してください。
在留資格変更と在留期間更新の違いは?必要書類も変わる?
在留資格変更では婚姻・同居・生計の立証が手厚く必要です。
在留期間更新では同居継続・収入・納税/社保の実績確認が重視されます。必要書類は申請類型で異なるため、最新の提出書類一覧+補足資料の設計が重要です。
必要書類は何が必要ですか?
出入国在留管理庁のHPに在留許可毎に提出書類一覧が掲載されています。
日本人の配偶者(夫又は妻)であれば、申請には、以下のような書類が必要です。
・在留資格申請書、パスポート、写真(4×3cm)
・日本人配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票、身元保証書
・経済基盤を証明する資料(住民税の課税証明書又は非課税証明書、納税証明書、残高証明、雇用証明書、内定通知書など)
・婚姻関係を証明する書類(外国人配偶者の国籍国の機関が発行した結婚証明書、スナップ写真、SNS・通話履歴、質問書など)
日本語以外の書類は翻訳文も必要です。
当事務所では、個人の状況を踏まえて、必須書類以外の補足書類をリストアップしてご提示します。
申請先はどこになりますか?
在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。
・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)
注意:出張所では取り扱わない手続があります。案件によって本局・主要支局への提出指定となる場合があります。
申請はオンラインでも可能ですか?
はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。
審査期間はどれくらいかかりますか?
・在留資格認定証明書交付申請(海外在住の配偶者を呼び寄せる場合):通常1~3ヶ月程度が目安です。
・在留資格変更許可申請(国内在住者が婚姻によりビザ変更):通常1〜2ヶ月程度が目安です。
・在留期間更新許可申請(現在の配偶者ビザを延長する場合):通常1〜2ヶ月程度が目安です。
申請の内容や証拠書類の充実度、入管の混雑状況、複雑性、個別審査状況によって、さらに時間がかかることがあります。
審査期間の目安はあくまで「スムーズに許可された場合の期間」と考え、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。
不許可になった場合、再申請は可能ですか?
可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが必要です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低くなります。追加の証拠資料や改善を行ったうえで、再申請可能な状況かを検討します。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。