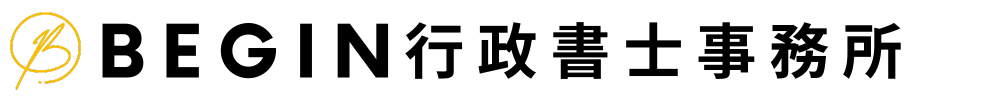本記事では、高度専門職ビザの取得を検討されている方々に対し、その詳細なポイント基準、高度専門職ビザの類型、高度専門職ビザの多様な優遇措置について、詳細な情報を掲載しています。複雑な制度を理解し、潜在的な申請者が自身の状況を正確に把握し、適切な申請戦略を立てましょう。
高度専門職ビザを取得するための最も重要な要件は、「高度人材ポイント制」に基づき、合計で70点以上を獲得することです 。
このポイント計算は、申請者の学歴、職歴、年収、年齢、研究実績などを総合的に評価するものであり、各項目で定められた基準を満たすことでポイントが加算されます。
詳細なポイント基準
ポイント計算の核心:70点以上の獲得が必須
高度専門職ビザの申請において、ポイント計算は許可の可否を決定する根幹をなす要素です。申請者の学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、そして様々な特別加算項目を網羅的に評価し、その合計点が70点以上であることが必須条件となります 。この基準を満たさなければ、他のいかなる要件を満たしていても高度専門職ビザの取得は認められません。
学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、特別加算の各項目における詳細なポイント基準
各項目における詳細なポイント基準は以下の通りです。これらの基準は、高度専門職ビザの申請において、ご自身の強みを最大限に活かすための重要な情報となります。
学歴
学歴は、申請者の専門性を示す重要な指標であり、以下の基準でポイントが加算されます。高等専門学校や専修学校の専門課程を卒業した外国人(高度専門士)も「大学と同等以上の教育を受けた者」として扱われます 。
- 博士の学位:30ポイント
- 修士または専門職学位(博士の該当者を除く):20ポイント
- 大学を卒業または同等以上の教育(博士・修士・専門職学位の該当者を除く):10ポイント
- 博士、修士、専門職学位を2以上保有(複数の分野):5ポイント
職歴
職歴は、実務経験の長さに基づいて評価されます。なお、職歴には大学での学習期間やアルバイト期間は含まれないため、実務経験のみが対象となります 。
- 7年以上の実務経験:15ポイント
- 5年以上7年未満の実務経験:10ポイント
- 3年以上5年未満の実務経験:5ポイント
年収
年収は、高度専門職ビザの取得において特に複雑な要素であり、単に一定額以上であれば良いというものではありません。ポイント加算の対象となる年収とは、申請に係る高度専門職外国人としての活動に日本において従事することにより受ける(予定)年収を意味し、契約機関および外国所属機関から受ける報酬の年額を指します 。
高度専門職ビザの年収要件には、二重の構造が存在します。まず、高度専門職1号(ロ)と(ハ)の活動類型においては、年収が300万円以上であることが最低限の前提条件となります 。この300万円はポイント加算の対象ではなく、ビザ申請の資格を得るための「足切りライン」として機能します。この最低ラインを満たさなければ、他の項目でいくら高得点を獲得しても、高度専門職ビザは許可されません。
この最低条件をクリアした上で、実際のポイント加算はより高い年収に対して行われます。さらに、年収のポイントは申請時の年齢によって変動するという重要な条件があります。これは、若年層には比較的低い年収でもポイントが付与される一方で、年齢が上がるにつれてより高い年収が求められることを意味します。この制度設計は、日本が単に「量」だけでなく、「質」の高い外国人材、特に経済的貢献度の高い人材を優先的に誘致しようとする政策的な意図を反映していると考えられます。
以下に、年収ポイントの正確な基準(年齢別)を示します。
- 1000万円以上:40ポイント
- 900万円以上1000万円未満:35ポイント
- 800万円以上900万円未満:30ポイント
- 700万円以上800万円未満:25ポイント
- 600万円以上700万円未満:20ポイント
- 500万円以上600万円未満:15ポイント
- 400万円以上500万円未満:10ポイント
年齢による加点条件:
- 30歳以上35歳未満の方は、年収500万円以上でポイント加算対象 。
- 35歳以上40歳未満の方は、年収600万円以上でポイント加算対象 。
- 40歳以上の方は、年収800万円以上でポイント加算対象 。
- 例えば、年収400万円の場合、29歳以下であれば10ポイントが加算されますが、30歳以上では0ポイントとなります 。
年齢
申請時の年齢もポイント計算の対象となります。
- 30歳未満:15ポイント
- 30歳以上35歳未満:10ポイント
- 35歳以上40歳未満:5ポイント
研究実績
研究実績は、特定の要件を満たすことでポイントが加算されます。
- 以下の①~④のうち2つ以上に該当:25ポイント
- 特許を受けた発明が1件以上ある
- 外国政府から補助金等を受けた研究に3回以上従事
- 学術論文データベース登録の論文が3本以上
- 上記と同等の研究実績として法務大臣が認めるものがある
- 以下の①~④のうち1つに該当:20ポイント
特別加算
上記の基本項目に加え、特定の条件を満たすことで特別加算ポイントが得られます。
- 日本の大学・大学院を修了し学位を取得:10ポイント
- 日本語能力試験N1合格相当:15ポイント
- 日本語能力試験N2合格相当:10ポイント
- 所属会社がイノベーション創設促進支援措置を受けている(中小企業):20ポイント
- 所属会社がイノベーション創設促進支援措置を受けている(中小企業以外):10ポイント
- 世界の権威ある3つの大学ランキングのうち2以上で上位300位以内の大学・大学院を修了し学位を取得:10ポイント
- 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業を担うものであること(IT分野など):10ポイント
- その他、試験研究費・開発費の合計額が売上高の3%超(中小企業):5ポイント、国または国から委託を受けた機関が実施する研修(1年以上)を修了:5ポイントなどがあります 。
高度専門職ビザ ポイント計算表(詳細版)
| 項目 | 区分 | ポイント | 備考 |
| 学歴 | 博士の学位 | 30 | |
| 修士または専門職学位 | 20 | 博士の該当者を除く | |
| 大学を卒業または同等以上の教育 | 10 | 博士・修士・専門職学位の該当者を除く | |
| 博士、修士、専門職学位を2以上保有(複数の分野) | 5 | ||
| 職歴 | 7年以上の実務経験 | 15 | |
| 5年以上7年未満の実務経験 | 10 | ||
| 3年以上5年未満の実務経験 | 5 | ||
| 年収 | 1000万円以上 | 40 | 年齢により加点対象年収が異なる |
| 900万円以上1000万円未満 | 35 | ||
| 800万円以上900万円未満 | 30 | ||
| 700万円以上800万円未満 | 25 | ||
| 600万円以上700万円未満 | 20 | ||
| 500万円以上600万円未満 | 15 | ||
| 400万円以上500万円未満 | 10 | ||
| 年齢 | 30歳未満 | 15 | |
| 30歳以上35歳未満 | 10 | ||
| 35歳以上40歳未満 | 5 | ||
| 研究実績 | ①~④のうち2つ以上に該当 | 25 | ①特許1件以上、②外国政府補助金研究3回以上、③学術論文データベース論文3本以上、④同等の研究実績 |
| ①~④のうち1つに該当 | 20 | ||
| 特別加算 | 日本の大学・大学院を修了し学位を取得 | 10 | |
| 日本語能力試験N1合格相当 | 15 | ||
| 日本語能力試験N2合格相当 | 10 | N1合格者を除く | |
| 所属会社がイノベーション創設促進支援措置を受けている(中小企業) | 20 | ||
| 所属会社がイノベーション創設促進支援支援措置を受けている(中小企業以外) | 10 | ||
| 世界大学ランキング上位300位以内の大学・大学院を修了し学位を取得 | 10 | 3つの主要ランキングのうち2つ以上 | |
| 将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業を担う | 10 | IT分野など | |
| 試験研究費・開発費の合計額が売上高の3%超(中小企業) | 5 | ||
| 国または国から委託を受けた機関が実施する研修(1年以上)を修了 | 5 |
ポイント計算の複雑性
上記で示した通り、高度専門職ビザのポイント計算は多岐にわたり、個々の状況によって加算ポイントが細かく変動します。特に、年収の年齢別加点条件や、研究実績、特別加算の各項目は複雑であり、申請者自身が全ての該当項目を正確に把握し、それを裏付ける証明書類を適切に揃えることは容易ではありません 。
計算にわずかな誤りがあった場合でも、審査官に不信感を与え、審査の長期化や不許可に繋がる可能性があります。ご自身のポイントが何点になるかを正確に把握し、許可の可能性を最大限に高めることが不可欠です。
※出入国在留管理庁のホームページで最新のポイント計算表や加算ポイントに関する資料が入手できます。
高度専門職1号の活動区分(イ・ロ・ハ)とそれぞれの特性
高度専門職1号ビザは、申請者が日本で行う活動内容に応じて、以下の3つの類型に分類されます 。申請者は、自身の活動がどの区分に該当するかを明確にし、その区分に応じた活動内容であることを証明する必要があります。
各区分の定義と該当する職種例
高度専門職1号イ(高度学術研究分野)
この区分は、日本の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導、または教育をする活動に従事する外国人を対象とします 。具体的には、大学の教授や研究機関の研究者などが該当します 。関連する在留資格としては、「教授」や「研究」などが挙げられます 。
高度専門職1号ロ(高度専門・技術分野)
この区分は、日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学または人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事する活動を行う外国人を対象とします 。システムエンジニア、プログラマー、国際弁護士など、専門的な知識や技術を活かして企業で働く技術者や専門職が該当します 。関連する在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「法律・会計」、「医療」などが挙げられます 。
高度専門職1号ハ(高度経営・管理分野)
この区分は、日本の公私の機関において事業の経営を行い、または管理に従事する活動を行う外国人を対象とします 。具体的には、企業の経営者や管理職などが該当します 。関連する在留資格としては、「経営・管理」や「法律・会計」などが挙げられます 。
高度専門職ビザの大きなメリットの一つとして、通常の就労ビザでは認められない「複合的な在留活動」が可能である点が挙げられます 。例えば、大学で教鞭をとりながら、その研究成果を活かして関連事業の経営を行うといった活動が認められます。この柔軟性は、高度な専門性を持つ人材が日本で多様なキャリアパスを築く上で非常に有利な点となります。
高度専門職ビザ取得の優遇措置
高度専門職ビザは、日本の産業や社会に貢献する優秀な外国人材を積極的に受け入れるため、他の就労系ビザに比べて多くの優遇措置が設けられています 。
高度専門職1号の優遇措置
高度専門職1号ビザの取得者は、以下の優遇措置を受けることができます。
- 複合的な在留活動の許可: 通常、外国人は一つの在留資格の範囲内でしか活動が認められませんが、高度専門職の在留資格を取得すると、例えば大学での研究活動と関連事業の経営を同時に行うなど、複数の活動が可能になります 。
- 在留期間5年の付与: 高度専門職1号の在留資格には、法律上の最長期間である「5年」が一律に付与され、更新も可能です。これにより、毎年更新が必要な他の在留資格と比較して、更新にかかる手間やコストを大幅に削減できます 。
- 永住許可要件の緩和: 通常、永住許可を得るには10年以上の在留期間が必要ですが、高度人材ポイント制で70点以上を取得し、高度外国人材としての活動を3年以上行っている場合、または80点以上を取得し、高度専門職の活動を1年以上継続している場合は、永住許可の対象となります 。
- 配偶者の就労が可能: 通常、就労資格を持つ外国人の配偶者が日本で働くには特定の要件を満たす必要があります。しかし、高度人材の配偶者の場合は、学歴や職歴の要件を満たさなくても、「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」などに該当する活動が無制限で可能です 。
- 一定の要件を満たせば、親の入国・在留が可能: 通常、就労目的の在留資格では外国人の親を日本に呼び寄せることはできません。しかし、高度人材の場合、世帯年収が800万円以上であること、7歳未満の子の養育や妊娠中の配偶者の介助などを行う場合に限り、高度人材またはその配偶者の親(養親を含む)の日本への受け入れが可能です 。
- 一定の要件を満たせば、外国で雇っていた家事使用人の入国・在留が可能: 高度人材の世帯年収が1,000万円以上などの条件を満たせば、外国で雇用していた家事使用人を日本に呼び寄せ、滞在させることが可能です 。
- 入国・在留手続きの優先処理: 高度人材の入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。入国事前審査の申請は受理から10日以内、在留審査の申請は受理から5日以内が目安とされていますが、詳細確認が必要な場合はこの期間を超えることがあります 。
高度専門職2号の優遇措置
高度専門職2号は、高度専門職1号の資格で3年以上活動を行っていた方が対象となる在留資格です 。この在留資格は、高度専門職1号の優遇措置をさらに発展させたものであり、日本での長期的な定着とキャリア形成を強力に支援します。
- 在留期間が無期限となる: 高度専門職2号の最大のメリットは、在留期間が無期限となることです(ただし、在留カードは7年に一度更新が必要です) 。これにより、ビザ更新の手間が不要となり、日本での生活とキャリアプランをより自由に、長期的に設計することが可能になります。
- 活動範囲の拡大: 「高度専門職1号」で認められる活動に加えて、就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動が可能になります 。これは、高度専門職1号よりもさらに広範な職務や兼業が可能になることを意味し、キャリアの柔軟性を大きく高めます。
- 高度専門職1号の優遇措置の継続: 高度専門職1号で受けられる優遇措置(永住許可要件緩和、配偶者就労、親・家事使用人帯同)は、高度専門職2号でも引き続き適用されます 。
永住許可要件の緩和は、日本政府が優秀な外国人材の長期的な定着を強く望んでいることを示唆しています。これは、彼らが日本経済に継続的に貢献することを期待しているためです。高度専門職2号への移行は、その貢献をさらに促進するためのものであり、ビザ更新の手間をなくし、より広範な活動を認めることで、人材が日本でのキャリアパスを自由に設計できる環境を提供します。これらの優遇措置は、単に「ビザが取りやすい」というだけでなく、申請者にとって「日本での生活の質」と「将来の安定性」を大きく向上させるものです。特に、家族帯同の要件緩和は、優秀な人材が家族と共に日本に移住し、安心して生活基盤を築く上で極めて重要な要素となります。
特別高度人材制度(J-Skip)の概要
2023年4月からは、「特別高度人材制度(J-Skip)」が導入されました 。これは従来のポイント制とは別に、学歴または職歴と年収が一定水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、現行よりもさらに拡充された優遇措置を認める制度です。
- 主な要件例:
- 高度学術研究活動/高度専門・技術活動(1号イ・ロ):修士号以上取得かつ年収2,000万円以上、または実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上 。
- 高度経営・管理活動(1号ハ):実務経験5年以上かつ年収4,000万円以上 。
- 優遇措置の拡充例:
- 永住許可申請に要する在留期間が1年に短縮 。
- 世帯年収3,000万円以上の場合、外国人家事使用人を2人まで雇用可能 。
- 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用が可能 。
J-Skip制度の導入は、日本が外国人材誘致において「量」だけでなく「質」をさらに重視し、特に世界トップクラスの「超エリート」層に焦点を当てていることを示唆しています。これは、グローバル競争が激化する中で、より直接的かつ強力なインセンティブを提供することで、他国との人材獲得競争に打ち勝とうとする政策的な動きと解釈できます。
高度専門職ビザの優遇措置一覧
| 優遇措置項目 | 高度専門職1号 | 高度専門職2号 | J-Skip(特別高度人材) |
| 複合的な在留活動 | 可能 | ほぼ全ての就労活動が可能 | 可能 |
| 在留期間 | 5年(一律付与、更新可) | 無期限(在留カード7年更新) | 5年(一律付与、更新可) |
| 永住許可要件緩和 | 70点以上で3年、80点以上で1年 | 70点以上で3年、80点以上で1年 | 1年 |
| 配偶者の就労 | 学歴・職歴不問で広範な就労が可能 | 学歴・職歴不問で広範な就労が可能 | 学歴・職歴不問で広範な就労が可能 |
| 親の帯同 | 世帯年収800万円以上、7歳未満の子の養育等で可能 | 世帯年収800万円以上、7歳未満の子の養育等で可能 | 世帯年収800万円以上、7歳未満の子の養育等で可能 |
| 家事使用人の帯同 | 世帯年収1,000万円以上で1名まで可能 | 世帯年収1,000万円以上で1名まで可能 | 世帯年収1,000万円以上で1名、3,000万円以上で2名まで可能 |
| 入国・在留手続きの優先処理 | 入国10日以内、在留5日以内が目安 | 優先処理の対象外(1号から移行のため) | 入国10日以内、在留5日以内が目安 |
| プライオリティレーンの使用 | なし | なし | 可能(大規模空港等) |
申請取次行政書士によるサポートの価値
高度専門職ビザの申請は、複雑なポイント計算、各区分に応じた活動内容の証明、そして申請者の能力と日本への貢献を具体的に示す説得力のある理由書の作成など、専門的な知識が不可欠です。特に、曖昧な情報に基づく自己判断で申請を進め、不許可になった場合、その後のリカバリーが非常に困難になるケースも少なくありません 。
申請取次行政書士の専門性と役割
申請取次行政書士とは、出入国に関する一定の研修を修了し、地方出入国在留管理局長に届け出た行政書士のことです 。彼らは「法務知識」と「入管に関する知識」を兼ね揃えた入管業務の専門家であり、めまぐるしく変わる法律や運用を常に把握し、研鑽を積んでいます 。
行政書士は、膨大な申請を受け付けている入国管理局に代わり、虚偽申請を未然に防ぎ、国益を維持する役割も担っています 。この専門性と公共性は、申請者にとって信頼できるパートナーとなる基盤を形成します。
複雑な手続きの代行と時間・労力の削減
高度専門職ビザの申請は、通常の就労ビザと異なり、ポイント計算をいかに正確に行い、それを裏付ける説得力のある書類を作成するかが鍵となります。多岐にわたる必要書類の準備、正確なポイント計算、そして入管への申請手続きは、多忙な申請者にとって大きな負担となります 。
申請取次行政書士に依頼することで、申請者はご自身で入管に出頭する必要がなくなり、多忙な方でもスムーズに手続きを進めることができます 。これにより、申請者は本業や日常生活に集中しながら、安心してビザ申請を進めることが可能になります。
当事務所は、申請取次行政書士として、最新の法改正や運用状況を常に把握し、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な申請戦略をご提案いたします。正確な書類作成から入管への提出代行、そして万全のサポート体制で、皆様の高度専門職ビザ取得を力強く支援し、安心して日本での新たな一歩を踏み出せるよう尽力いたします。高度専門職ビザの取得をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。