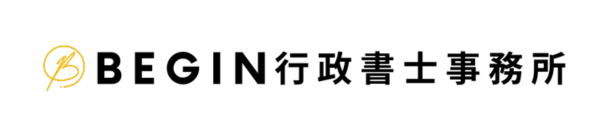はじめに
外国人が日本で日本人の配偶者と共に生活を営むためには、「日本人の配偶者等」という在留資格、いわゆる配偶者ビザの取得が不可欠です。このビザが許可されることで、就労制限なく日本に滞在でき、夫婦として安定した生活を築くことが可能になります。
しかし現実には、配偶者ビザの申請は必ずしもスムーズにいくとは限りません。むしろ、不許可通知を受け取る方も少なくなく、その背景には婚姻の信憑性に対する疑念、経済的基盤の不足、同居の実態が認められないこと、さらには過去の在留歴や素行の問題など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
さらに、2025年現在、入管当局の審査姿勢は以前にも増して厳格化の方向にあります。偽装結婚の摘発や社会保険・税金未納問題の増加を背景に、わずかな不備や矛盾があるだけでも「本当にこの婚姻は真実に基づくものなのか?」という強い疑念を持たれる傾向が顕著になってきました。
したがって、配偶者ビザの取得・更新を確実に成功させるためには、審査で重視される観点を理解し、不許可になりやすい典型的なケースを知ったうえで、具体的な回避策を講じることが極めて重要です。
本記事では、日本人配偶者ビザの不許可リスクとその回避方法を徹底解説します。はじめての申請で失敗したくない方や、過去に不許可になってしまい再申請を検討している方にとって、実務に役立つ知識を網羅的に提供します。
日本人配偶者ビザの基本概要
日本人配偶者ビザとは?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人と結婚した外国人が日本に在留し、夫婦として生活を営むためのビザです。一般的に「配偶者ビザ」と呼ばれていますが、正式には「日本人の配偶者等」と定められています。
このビザの最大の特徴は、就労制限がない点です。取得後は、日本国内でフルタイムの就労はもちろん、アルバイトやパート、自営業など幅広い活動が可能となります。つまり、生活基盤を築く上で大きな自由度が与えられるビザと言えます。
✅ 出入国在留管理庁の該当ページ
在留資格「日本人の配偶者等」 | 出入国在留管理庁
在留資格「永住者の配偶者等」 | 出入国在留管理庁
配偶者ビザが必要となる場面
典型的なケースとしては以下が挙げられます。
- 日本人と結婚した外国人が、日本に移住して夫婦として生活する場合
- 日本に既に在留中の外国人(留学生や就労ビザ保持者)が、日本人と結婚して配偶者ビザに在留資格を変更する場合
- 海外で結婚した日本人と外国人夫婦が、日本に帰国して生活を開始する場合
いずれの場合でも、婚姻の実態や生活基盤の安定性を入管に対して十分に証明することが求められます。
配偶者ビザの審査における特徴
配偶者ビザは、単なる「書類審査」ではなく、夫婦関係の真実性を多角的に検証するプロセスです。婚姻届や戸籍謄本といった形式的な書類だけでは足りず、実際に同居しているか、安定的に生活できるか、互いに家族としての理解と関わりを持っているかを、申請書類や理由書、場合によっては入管の調査を通じて確認されます。
配偶者ビザ審査で重視される4つの観点
配偶者ビザの審査は、大きく次の4つの観点に分類して考えると分かりやすいです。これらはすべて「立証責任」が申請者側にあるため、入管に対して十分な証拠を提示することが不可欠です。
婚姻の信憑性と真実性の証明
最も重要なのは「この婚姻が真実のものであるか」という点です。偽装結婚防止の観点から、交際の経緯、出会いのきっかけ、交際期間、同居の実態などが厳しくチェックされます。写真、チャット履歴、渡航履歴なども重要な証拠になります。
経済的基盤の安定性
日本で安定して生活できるかどうかも審査の大きなポイントです。具体的には、世帯収入、雇用形態、納税状況、社会保険の加入状況などが確認されます。収入が低い、非正規雇用しかない、税金を滞納している場合は、不許可リスクが高まります。
同居の継続性
夫婦が実際に同居し、家庭生活を営んでいるかが確認されます。別居や短期的な同居では「実体のある婚姻」とは認められにくいです。特に、住民票の記載住所、賃貸契約書、公共料金の名義など、生活の一体性を示す資料が重要です。
素行および在留の適正
過去の在留歴や素行の適正も審査対象です。オーバーステイや資格外活動違反、納税・保険料未納、交通違反の繰り返しなどは不利に働きます。配偶者本人だけでなく、日本人配偶者の素行も間接的に影響を与える場合があります。
配偶者ビザが不許可になる背景
配偶者ビザ申請の場合、書類や理由書が不十分で不許可となるケースが多発しています。この不許可リスクが高まる背景には以下の要因があります。
- 偽装結婚摘発の強化
- 経済的困窮を理由とする安易な婚姻申請の増加
- 税金・社会保険料未納問題の拡大
- 入管の審査基準の厳格化
これらを踏まえると、「細部まで丁寧に証拠を整えること」が求められていると言えます。
再申請での難易度上昇
一度不許可になった場合、その後の再申請はさらにハードルが上がります。不許可理由を克服できていないまま同じ資料を提出しても、許可される可能性はほぼありません。再申請の際には、不許可理由を正確に把握し、改善策を理由書や追加資料で立証する必要があります。
不許可になりやすい典型的なケース
婚姻の信憑性と真実性に疑念があるケース
配偶者ビザ審査で最も重視されるのは「この結婚が真実に基づくものかどうか」です。偽装結婚の疑いがあると判断されれば、他の条件を満たしていても不許可となります。典型的なケースとしては以下のようなものがあります。
- 交際歴が極端に短い
出会ってすぐに結婚、婚姻届提出から申請までの期間が短すぎる場合、婚姻の実態が薄いと見なされやすいです。 - 夫婦の年齢差が大きい
20歳以上の差がある場合、入管は「ビジネス的な婚姻」「在留資格目的の婚姻」の可能性を疑います。 - 出会いの経緯が特殊
SNSや出会い系サイト、結婚紹介所を介した出会いそのものが不利ではありません。しかし、その場合は「本当に親密な関係が築かれているか」を厳しくチェックされます。 - 互いの親族が結婚を知らない/理解していない
親族の証言や結婚式の有無も、婚姻の真実性を補強する要素です。親族に一切周知されていない場合は不自然と判断されることがあります。 - 入管調査で答えに食い違いがある
審査過程で夫婦それぞれに対するヒアリングや調査が行われることがあります。その際に、出会いの日付や生活習慣などに矛盾があると信憑性が疑われます。
経済的基盤が不十分なケース
次に多いのが「経済的に安定していない」と判断されて不許可になるケースです。入管は「夫婦が日本で安定して生活できるか」を非常に重視します。典型例は以下の通りです。
- 収入が低すぎる/不安定
アルバイトや非正規雇用のみ、あるいは年収が200万円未満などのケースでは「生活が成り立たない」とされます。 - 雇用形態が不安定
転職を繰り返している、勤続期間が短い場合、安定性に欠けると見なされやすいです。 - 納税や社会保険に未加入・未納
住民税や所得税、国民健康保険や年金の未加入・滞納がある場合、重大なマイナス要素です。 - 所得証明の提出ができない
税務署からの課税証明書を出せない場合、収入の裏付けが取れないため不許可リスクが高まります。
同居の継続性が立証できないケース
夫婦が実際に同居していることは「実体ある婚姻」を証明するための大前提です。同居実態が不明確だと、不許可に直結します。
- 住民票が別々になっている
住民票上で住所が一致していない場合、特段の合理的理由がなければ「同居していない」と判断されます。 - 結婚後に別居している
仕事や学業の都合で一時的に別居しているケースでも、証拠が不十分だとマイナス評価になります。 - 住居の実態に疑念がある
極端に狭い住居や、実際には生活できていない疑いのある住所(知人宅の名義借りなど)は、偽装の疑念につながります。 - 生活実態を示す証拠がない
公共料金の名義や銀行口座、郵便物など、夫婦としての生活の痕跡が乏しい場合は信憑性が弱まります。
素行や在留の適正に問題があるケース
最後に、過去の素行や在留状況が原因で不許可となるケースです。たとえ婚姻が真実であっても、これに問題があればビザは下りません。
- 過去にオーバーステイ歴がある
一度でも不法滞在があると、その後の配偶者ビザ審査で強く不利に働きます。 - 資格外活動違反をしていた
留学ビザや就労ビザの範囲を超えて働いていた場合、不許可の大きな要因となります。 - 税金や社会保険料の滞納
配偶者本人だけでなく、日本人配偶者の滞納も問題になります。 - 犯罪歴や繰り返しの交通違反
軽微な違反でも積み重なると「素行善良要件」に反するものとされます。
不許可を回避するための具体的なポイント
配偶者ビザの審査は「疑わしいものは許可しない」という厳格な姿勢で運用されています。つまり、少しでも矛盾や不自然さがあると、不許可に傾く可能性が高いということです。したがって、不許可を避けるためには「疑念を持たれないように、客観的資料で立証する」ことが最重要です。以下に4つの観点ごとに、具体的な回避策を解説します。
婚姻の真実性を証明するための対策
婚姻の信憑性を疑われやすいケースでは、とにかく「出会いから結婚までの経緯を具体的に可視化」することが重要です。
- 交際写真や旅行の記録、LINEやメールの履歴、通話記録を提出する
- 結婚式や親族との集合写真を準備する
- 婚姻届や婚姻証明書のほか、両国での婚姻手続きを整える
- 質問書では「出会いの経緯」「交際開始時期」「同居開始時期」を具体的に記載する
経済的基盤を立証するための対策
経済的基盤は「夫婦が安定した生活を営めるかどうか」を示す最も客観的な要素です。ここでは次のような対策が有効です。
- 日本人配偶者の所得課税証明書、確定申告書、源泉徴収票を準備する
- 在職証明書や雇用契約書を添付し、安定雇用を示す
- 自営業の場合は決算書や事業計画書を用意する
- 世帯全体での生活費計画を提示し、生活の見通しを明示する
- 税金・年金・保険料の納付状況を証明する
同居の継続性を示すための対策
同居の実態を疑われないようにするためには、住民票以外にも生活を裏付ける証拠を多角的に揃えることが有効です。
- 住民票を同一住所に整える
- 公共料金の領収書や請求書を夫婦どちらかの名義で揃える
- 郵便物や宅配の受領記録、共用口座などを準備する
- アパートや住宅の賃貸借契約書に夫婦の名前を記載する
素行・在留適正を維持するための対策
素行や在留適正に不安があると、婚姻の真実性が認められても不許可となるリスクがあります。そのためには以下の点を徹底する必要があります。
- 過去の違反歴がある場合は、反省文や改善策を提出する
- 税金や社会保険料は滞納せず、納付済証明書を揃える
- 軽微な違反であっても再発防止のための取組みを理由書に記載する
- 素行に関する不安要素がある場合は、勤務先や地域社会からの推薦状を添える
不許可を回避するために大事な視点
不許可を避けるために大切なのは「入管にとっての疑問点を先回りして解消すること」です。婚姻の真実性、経済的安定、同居の実態、素行の適正――これらすべてを裏付ける資料を準備し、矛盾のない形で提出することが不可欠です。
配偶者ビザ更新で不許可になりやすいケース
配偶者ビザの更新申請は「一度許可されているから大丈夫」と考えがちですが、実際には更新で不許可となるケースも少なくありません。入管は更新の際、婚姻生活の実態が継続しているか、経済的基盤が安定しているかを改めて審査します。本章では、特に不許可リスクが高いケースを取り上げ、その背景と対応策を解説します。
赤字や収入減少時の対応
更新審査では、世帯の収入が安定しているかどうかが重視されます。会社員であれば源泉徴収票や課税証明書、自営業であれば確定申告書や決算書を提出することになります。
- 自営業で赤字決算が続いている
- コロナ禍や景気後退で売上が減少した
- 勤務先で収入が減少した
このような場合、単に「収入が少ない」と見られてしまうと不許可の可能性が高まります。
しかし、実際には配偶者ビザ更新において「赤字だから必ず不許可」というわけではありません。補足資料として以下を提出することで、生活維持能力を補強できます。
- 預貯金残高証明
- 親族からの仕送りや扶養証明
- 今後の売上回復を示す契約書や注文書
- 副収入(アルバイトや配偶者の収入)に関する資料
別居中の更新申請
婚姻生活の実態は「同居」が原則とされます。そのため、別居中での更新申請は極めて不利です。
- 仕事の都合で一時的に別居している
- 出産や育児のため一方が実家に戻っている
- 留学や単身赴任などやむを得ない理由がある
こうした場合には、単なる別居ではなく「婚姻生活が継続している」ことを証明する必要があります。
- 定期的な面会や交流の記録(交通費の領収書、訪問時の写真)
- 通話やメッセージの履歴
- 仕送りや生活費の送金記録
離婚調停中や別居和解中のケース
離婚調停中や和解交渉中の場合、実質的に「夫婦生活が破綻している」と見なされる可能性が高く、更新は極めて困難になります。
- 家庭裁判所で調停中
- 弁護士を介して協議を行っている
- 配偶者との同居実態がなくなっている
この場合、原則として配偶者ビザの更新は認められません。もし日本に引き続き在留を希望する場合は、状況に応じて 「定住者ビザ」への変更申請 を検討することになります。例えば、長期間日本で生活している場合や、日本に子どもがいる場合は、定住者ビザに切り替えられる可能性があります。
更新申請は「現状維持」ではなく「再審査」
配偶者ビザの更新は、単に期間を延長するだけではなく「再び婚姻の実態と生活基盤を審査する」手続きです。赤字や収入減少、別居、調停中といったリスク要因がある場合は、その事情を客観的に説明し、証拠資料を提出することが不可欠です。
これらのケースでは、専門家の助言を受けながら、在留継続の道筋を慎重に検討することを強くおすすめします。
不許可となった場合の対応(不許可通知後の流れと再申請のポイント)
配偶者ビザ申請が不許可になると、大きなショックを受ける方が多いですが、不許可になったからといって永遠に取得できないわけではありません。重要なのは「なぜ不許可になったのか」を正確に把握し、その原因を取り除いたうえで再申請することです。本章では、不許可通知を受けた後に取るべきステップを解説します。
不許可通知を受け取ったら最初にすべきこと
不許可の通知書には「標準文言」が記載されており、理由が簡単に書かれているだけで具体的な内容は明らかにされていません。したがって、通知を受け取ったらすぐに 入管に不許可理由の詳細を確認すること が必要です。
- 入管で「不許可理由の開示」を求める
- 取次行政書士のアドバイスを受ける、行政書士と入管へ同行して一緒に説明を受けるなど、専門的な解釈を確認する
- 口頭での説明となるため、メモを残しておくことが重要
不許可の原因を整理・分析する
不許可となった理由は、大きく次の4つの類型に整理できます。
- 婚姻の信憑性・真実性が疑われた
- 経済的基盤が不足していると判断された
- 同居の継続性が不十分とみなされた
- 素行・在留適正に問題があるとされた
それぞれの原因ごとに、再申請の際に補強すべき書類や説明方法が変わります。例えば「交際期間が短い」と指摘されたなら、追加の写真や通信記録を提出する必要がありますし、「収入不足」とされたなら、最新の源泉徴収票や家族からの扶養証明を加えるべきです。
再申請に向けた準備
不許可の原因を取り除いたら、次は再申請の準備です。再申請では 前回と同じ内容で提出するのは絶対にNG です。
- 不許可理由を克服したことを理由書に明確に記載する
- 新たな証拠資料を追加して、審査官の疑問を解消する
- 提出書類の矛盾や不備を徹底的に修正する
また、再申請は「不許可直後にすぐ行う」のではなく、状況改善に一定の期間をかけてから行うことが望ましい場合があります。たとえば収入不足で不許可になった場合は、数か月後に新しい収入証明を出せるようにしてから再申請するほうが効果的です。
※不許可となった場合には「再申請」だけでなく「審査請求」という方法もあります。審査請求とは不許可処分に不服がある場合に法務大臣宛に異議を申し立てる手続きです。ただし、審査請求は長期間かかることが多く、また「不許可理由を克服する」方が実効性が高いため、実務上は再申請が一般的です。
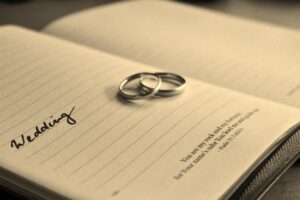
まとめ|不許可を防ぐために意識すべきこと
配偶者ビザの審査は、単に「結婚している事実」だけでは許可されません。入管は、婚姻が真実であるか、夫婦が安定して生活できるか、日本社会に適応しているかを総合的に見極めています。つまり、形式的な婚姻届や必要書類の提出だけでは不十分であり、実際に夫婦としての生活実態があることを丁寧に示す必要があるのです。
そのためには、❶婚姻の信憑性(交際歴や写真・やり取りの証拠)、❷経済的安定(収入証明や納税状況)、❸同居の継続性(住民票や生活の証拠)、❹素行・在留の適正(違反歴や滞納の有無)という4つの柱を意識して、客観的資料で裏付けることが不許可を避けるためには不可欠です。
また、不許可になる典型ケースには共通の傾向があります。交際期間が極端に短い、収入が不安定、別居中である、税金や保険料を滞納している――こうしたリスク要素がある場合は、そのまま申請せず、補足資料や理由書で十分に説明・改善策を提示することが重要です。
加えて、更新申請でも油断は禁物です。事業収入の減少や赤字決算、別居や離婚調停中などは不許可リスクが高まるため、状況を正直に説明し、生活継続の見通しを具体的に示すことが求められます。
結局のところ、配偶者ビザの審査は「疑わしいものは許可しない」という原則で運用されています。したがって、不許可を防ぐためには「疑念を持たれないように、証拠を揃えて可視化する」姿勢が大切です。
当事務所では、申請取次行政書士が不許可リスクを踏まえ、初回無料相談から書類作成・理由書作成・入管申請代行まで一貫してサポートいたします。
👉配偶者ビザでお悩みの方は、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。