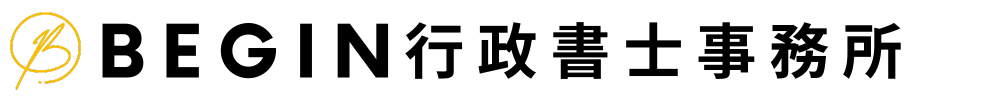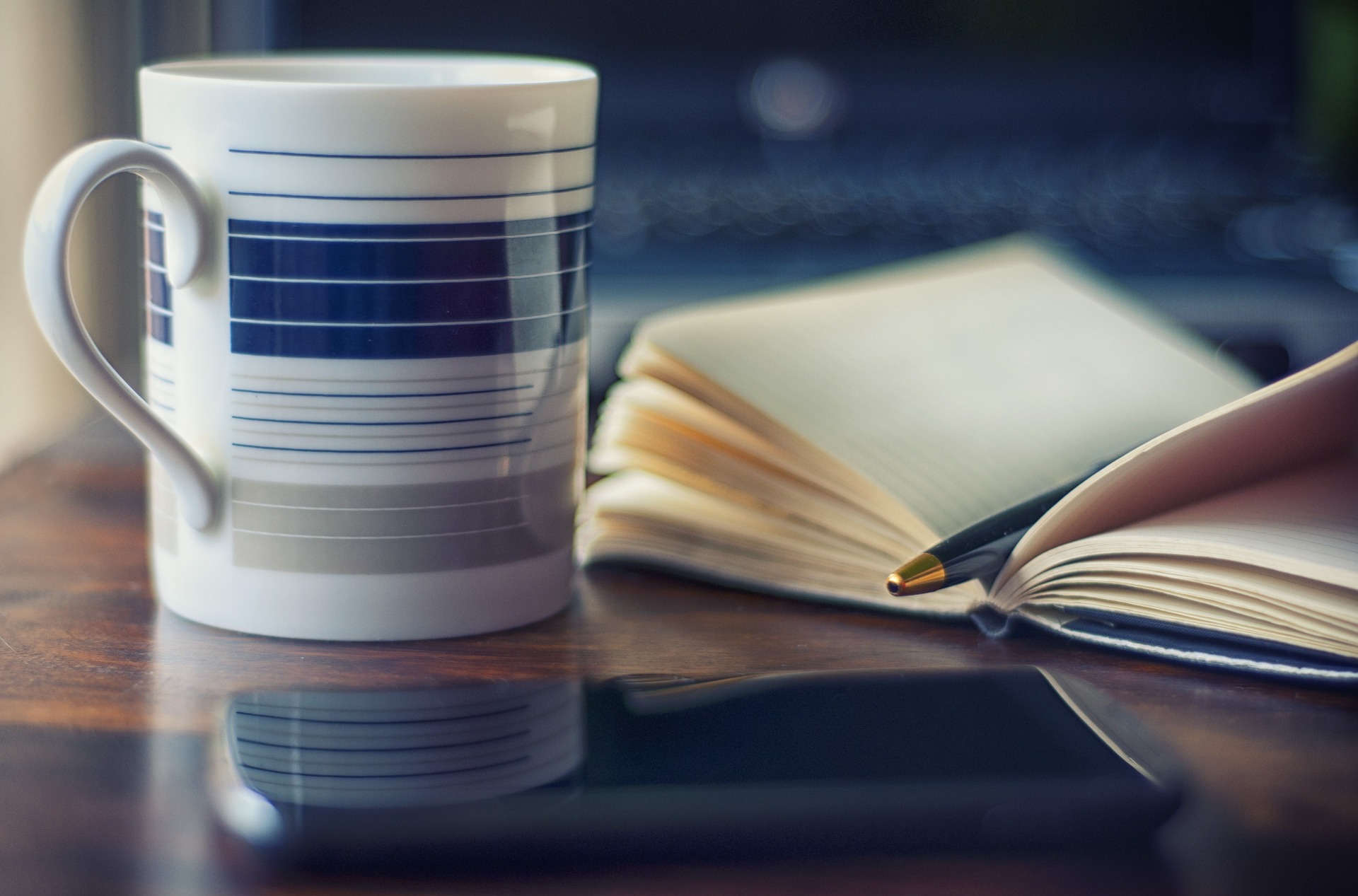Q&A
定住者ビザに関するよくある質問
定住ビザで就労できますか?
はい、定住者ビザには就労制限がありません。職種や業種に制限はなく、アルバイトから正社員、自営業まで幅広い活動が可能です。
「配偶者ビザ」から「定住ビザ」への変更はできますか?
可能です。代表的な例は以下の通りです。
・日本人配偶者と離婚後、子どもを養育している場合
・配偶者が亡くなった後も日本で生活を続けたい場合
・DVなど人道的事情で婚姻関係が破綻した場合
ただし、婚姻期間や生活実態、扶養状況などが重要な判断基準になります。
離婚後すぐに定住者ビザに変更できますか?
離婚から時間が経っていなくても、子の親権を持ち扶養している、またはDV被害を受けた場合などは、変更申請が認められる可能性があります。ただし、個別事情に応じた慎重な申請が必要です。
永住ビザとの違いは何ですか?
定住者ビザは在留期間が指定されており、更新が必要です。一方、永住ビザは無期限で更新不要ですが、申請には長期間の在留歴・安定収入・素行良好など高い要件が求められます。定住者ビザから永住への切り替えも可能です。
連れ子を日本へ呼び寄せたい。定住者ビザ(告示6号ニ)の要件は?
原則として次の全てを満たす必要があります。
- 子が未成年・未婚(日本法の未成年=原則18歳未満)であること。
- 扶養者が「日本人/永住者/特別永住者/在留期間1年以上の定住者」またはその**配偶者(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)**で、継続的に監護・扶養できること。
- 実親(他方親)による同意や親権・監護権の法的地位が明確であること(離婚判決・同意書・監護実績)。
- 生計の安定性(収入・貯蓄・居住の確保・学校就学の見込み等)が示せること。
在外からは在留資格認定証明書申請(COE)、国内在留中なら事情により在留資格変更申請を検討します。
婚姻によらない日本人との子(日本人の実子)を海外から呼べますか?
まず国籍の確認が重要です。
- 子が日本国籍を有するなら在留資格は不要です(旅券・戸籍等の手続へ)。
- 外国籍のまま日本人の実子である場合は「日本人の配偶者等」で在留資格認定証明書(COE)が基本となります(日本人の配偶者等には、日本人の実子、日本人の特別養子が含まれます)。認知・親子関係の立証(出生証明・認知書・DNA鑑定結果を要する場合あり)を整える必要があります。
配偶者に成人の連れ子がいます。呼び寄せは可能でしょうか
告示6号ニは未成年・未婚が要件のため、成人は原則不可です。強い人道的事情がある場合に限り、国内で告示外定住(在留資格変更)を個別審査で検討する余地があります。
海外の配偶者が「日本人の配偶者等」を取得する際、未成年の連れ子は一緒に入国できますか?
同時期に申請は可能ですが、在留資格は別になります。配偶者は日本人の配偶者等、連れ子は定住者(告示6号ニ)で各々で在留資格認定証明書申請(COE)をします。審査の中心(立証ポイント)が異なるため、書類は分けて構成します。
連れ子の定住者ビザで重視される審査ポイントはありますか?
①身分関係の実在性(戸籍・出生・認知・親権)②監護実態の継続性(同居・送金・訪問・学校の在籍予定)③生計の安定(収入・税証明・住居)④他方親の同意⑤素行・在留履歴、の5点が柱です。理由書で時系列に可視化すると効果的です。
「未成年」は何歳までですか?どの時点で判定されますか?
日本法の未成年=原則18歳未満。運用上は申請時点で未成年・未婚であることが求められます(※個別判断あり)。早めの申請計画が安全です。
短期滞在で呼び寄せてから国内で「定住者」に変更できますか?
原則不可です(長期在留目的での短期利用は不適切)。ただしやむを得ない特別事情や人道的配慮が認められる例外はあり得ます。筋としては在外で在留資格認定証明書申請(COE)を取得する計画をお勧めします。
日本人が連れ子と養子縁組すれば、子は日本国籍になりますか?
養子縁組だけで自動的に日本国籍は取得しません。 国籍取得は別途の帰化申請の要件を満たす必要があります。
日本人による特別養子縁組の在留上のメリットはありますか?
特別養子縁組(原則6歳未満、家裁審判)は、子が「日本人の配偶者等(日本人の実子等)」での申請対象になり得ます。通常の連れ子定住(告示6号ニ)と比べ、身分関係の安定性の点で有利に働くことがあります。※手続・要件は厳格です。
収入が少ないのですが、連れ子の定住者ビザは可能ですか?
固定基準額はありませんが、世帯収入+貯蓄+居住確保+親族支援計画などで総合的な生計維持能力を示す必要があります。課税・納税証明、雇用証明、残高証明、家計表を数値で揃え、理由書で持続性を説明します。
定住者本人は配偶者・実子を「家族帯同(家族滞在)」で呼べますか?
定住者の配偶者・実子は「家族滞在」ではなく、原則として定住者(告示5号・6号)で検討します。区分や要件が異なるため、号の判定を誤らないことが重要です。
在外のCOEと国内の在留資格変更、どちらを選べばよい?
告示定住は在外からのCOEが原則です。国内在留中の子は、在留資格変更での可否を検討します。告示外定住は原則国内変更(個別事情立証が重い)です。
理由書は提出すべき?何を書けばよい?
理由書は出入国在留管理庁(入管)のホームページでは必須ではありませんが、実務的には作成を強く推奨しています。
- 身分関係の経緯(親権・同意・監護)
- 生活設計(住居・学校・医療・保険・家計)
- 生計の根拠(収入・貯蓄・支援の具体額と期間)
- 来日後の運用(同居実現時期、転校手続、扶養スキーム)
を時系列と数値で示すと補正・照会・不許可のリスクを下げられます。
年齢差が大きい再婚で連れ子申請をする際の注意点はありますか?
年齢差自体は直ちに不利ではありませんが、年齢差が大きいほど、偽装や利益婚の疑義を排除する説明が必要になります。交際・家族紹介の実績、共同生活の準備、家計運営の実態を第三者資料で積み上げましょう。
留学・就労など他の在留資格から「定住者」へ変更できますか?
要件に該当する事情(例:日本人の子を監護、DV・人道的配慮 等)がある場合に在留資格変更で検討します。告示外定住に該当し得るための、理由書・証拠の厚みが鍵となります。
連れ子の実親の同意が得られない場合は?
親権者の同意が原則です。例外は、裁判所の判断や単独親権の法的根拠が明確なとき等に限られます。まずは親権・監護権の法的整理から着手してください。
学校編入・医療・保険など生活面の準備はどこまで必要ですか?
居住の確保・編入相談の記録・保険加入方針・支援体制など、生活設計の具体性は審査加点になります。自治体窓口の相談記録や学校の受入見込みを資料化すると効果的です。
必要書類は何が必要ですか?
出入国在留管理庁のHPに在留許可毎に提出書類一覧が掲載されています。
用途(在外COE/国内変更/更新)と類型(告示定住/告示外定住)で追加書類が異なります。ここでは概ね共通で必要となる資料と、類型別の主な追加書類(連れ子定住 告示6号ニ)のケースを記載します。
共通(COE・変更・更新に概ね共通)
- 申請書一式(在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請)
- 写真(4×3cm)
- 旅券(パスポート)・(国内手続は)在留カード
- 身元保証書(主にCOE時)+保証人資料(住民票、課税・納税証明、在職証明 等)
- 生計資料:課税(非課税)証明・納税証明、在職(内定)証明、給与明細/源泉徴収票、残高証明、家計表 等
- 住民票(世帯全員・続柄入り)、住居資料(賃貸借契約書 等)
- 理由書(事情説明・生活設計・扶養計画を時系列+数値で)
- 外国語書類の日本語翻訳(必要に応じて公証/アポスティーユ・領事認証)
※COEは手数料不要、変更・更新は許可時に収入印紙が必要です。
類型別の主な追加書類(連れ子定住 告示6号ニ)
- 出生証明書(実親の記載が分かるもの)
- 親権・監護権を示す資料、または他方親の同意書
- 離婚判決・親権に関する合意書 等(該当時)
- 監護・扶養実績(送金記録・訪問記録・写真・連絡履歴)
- 就学関係(在学証明/編入予定の受入見込み など)
- 扶養者(日本人/永住者/特別永住者/定住者1年以上)の身分・収入資料
申請先はどこになりますか?
在留資格の変更・更新など国内申請は、原則として申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所を含む)に提出します。
在外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請=COE)は、所属機関や招へい人の所在地を基準に提出先が決まります。
・身分系ビザ(日本人の配偶者等・家族滞在・定住者 など)
COE(呼び寄せ): 日本側の扶養者/招へい人の住居地管轄
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄
・就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務/高度専門職/企業内転勤/技能/経営・管理 など)
COE(呼び寄せ): 受入企業(所属機関)の所在地管轄
※「経営・管理」で会社設立前は、事務所(予定地)の所在地管轄が目安。
国内申請(変更・更新): 申請人の住居地管轄(会社所在地が他地域でも原則は住居地)
当事務所は申請取次行政書士として申請代行が可能で、オンライン申請にも対応しています(※一部手続は窓口限定/本局・支局指定あり)。
申請はオンラインでも可能ですか?
はい。出入国在留管理庁のオンラインシステムを利用した申請が可能です 。ただし、利用できるのは、申請人本人(マイナンバーカード所持者に限る)、申請取次行政書士、所属機関の職員、弁護士、登録支援機関の職員、および一部の公益法人や親族、法定代理人などが申請できます。海外からは在留資格のオンライン申請はできません。
申請取次行政書士は、入管への申請取次資格を持つ専門家であり、申請人本人に代わってオンラインで申請手続を行うことができます。
在留期間はどれくらいですか?
告示定住の場合は6ヶ月・1年・3年・5年のいずれかが指定されます。初回は1年となることが多く、その後の更新で長期在留が認められることもあります。
告示外定住の場合は法務大臣が個々に指定する期間です。
審査期間はどのくらいかかりますか?
告示定住:通常1〜3ヶ月程度
告示外定住:3ヶ月〜半年以上かかることもあります(個別事情の審査が入るため)
定住者ビザの更新は簡単ですか?
初回の定住者ビザの在留期間終了時には、更新許可申請が必要です。扶養関係や生計の安定性、日本での生活実態が確認され、要件を満たせば更新は可能です。ただし、過去に問題がある場合は不許可の可能性もあるため注意が必要です。
不許可になった場合、再申請は可能ですか?
可能です。ただし、不許可通知書に記載された理由を十分に分析し、改善策を講じることが必要です。同じ書類や説明で再申請しても許可の可能性は低くなります。追加の証拠資料や改善を行ったうえで、再申請可能な状況かを検討します。
安心して前へ進むために
申請取次行政書士による在留資格申請サポート
当事務所は、申請取次行政書士として、依頼者様に代わり在留資格に関する各種申請書類の作成、入国管理局へ申請を代行することが可能です。
これは、ご自身での入管への出頭が不要となる利便性の高い制度であり、多忙な方や遠方在住の方でもスムーズに手続きを進めることができます。
申請取次行政書士とは、出入国在留管理庁に対して在留資格等の申請を「本人に代わって」行うことができる行政書士のことです。
法務省が定めた研修を受講し、所定の効果測定に合格したうえで、入管に届出を行った行政書士に限り、この取次資格が認められています。